シラバス情報
|
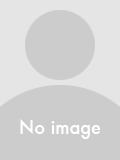
教員名 : 愼 蒼健
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
科学技術研究の倫理 (前期・水2)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Research Ethics (前期・水2)
授業コード Class code
99KTM16
科目番号 Course number
L3LBART534
教員名
愼 蒼健
Instructor
Chang-Geon SHIN
開講年度学期
2025年度前期
Year
2025年度
Semester
①First semester
曜日時限
水曜2限
Class hours
Wednesday 2nd, Period
開講学科・専攻 Department
理学研究科 応用物理学専攻(一般教養科目)、工学研究科(一般教養科目)、先進工学研究科(一般教養科目)、薬学研究科(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Department of Applied Physics, Graduate School of Science A course of liberal arts, the Graduate School of Engineering A course of liberal arts, the Graduate School of Advanced Engineering A course of liberal arts, Graduate School of Pharmaceutical Sciences 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
<授業のやり方について>
この授業は、ブレンド型を予定している。第1回目は対面型。 <概要> 1 本授業のテーマ 本授業にて問いたいのは、科学技術研究の現場での問いである。例えば、次のような2種類が考えられる。 (1) 研究の社会的倫理の問題/果たして、私はこの研究はしてもよいのか。拡大する科学技術の可能性に対して、研究者としてどこまで関与してよいのかなど。 (2) 研究・発表倫理の問題/例えば、研究論文の量産を強いられる環境下にて、データの取捨選択はどこまで許させるのか。あるいは、写真・データの加工は全く許されないのかなど。 (1) このような状況下において既存の「してもよい/してはいけない」の境界とルールを機械的に適用するだけでは、事態に太刀打ちできない場合も起こってくいる。 (2) 既に合意形成された研究倫理を学ぶことは重要だが、決まり切ったルールを学んだ上で、実際の研究現場での誘惑や不正・ミスに対して思考を諦めない強い力を養成したい。 そのために、本授業では講義だけでなく、院生諸君に「事例検討」の発表をしてもらい、議論を行う予定である。 なお、この科目は葛飾キャンパスの大学院研究科全体に開かれており、異なる研究科、異なる専攻、異なる研究室の院生が例年参加している。異なる研究背景を持つ者同士が議論することは、専門性を開く市民性の涵養にとって重要な経験となるはずである。 目的 Objectives
教養教育の目標にある以下の能力を獲得するための授業である。
「1.専門分野の枠を超えて広い視野で多元的・複眼的に自然・人間・社会を俯瞰できる能力」 「3.課題を自ら発見し、主体的に考え、解決に取り組むための論理的・批判的思考力」 「4.正解のない課題に対しても積極的に挑むための判断力・行動力」 「5.社会の激しい変化の中でも自らを律し、自らの位置付けやキャリア形成を確立するとともに、心身ともに自己を管理する能力」 より具体的に言えば、本授業は大学院生を対象として、科学技術研究を推進する上で生じる諸問題への対処を考えるための「頭づくり」をすることが目的である。 到達目標 Outcomes
(1) 研究者の遵守すべき研究倫理、果たすべき責任について理解し、それを説明できる。
(2) 個別事例を踏まえた上で、研究不正が起こる構造的問題について説明できる。 (3) レジュメを作成し発表、高度な議論をすることができる。 (4) 学問的なエッセイを書くことができる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
(1) 教科書は使うが、受講生と協議の上で決定するので、教科書販売サイトは使用しない。
(2) 前提知識は不要であるが、少人数でのディスカッションを行うので、意欲のある学生の履修を望む。なお、ゼミ形式を想定しているので、受講者は15名程度を上限とする。受講志望者が多い場合は、選抜を行うこともある。 (3) 第1回目から、教室にて対面型授業を行う。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/ディベート・ディスカッション Debate/Discussion/プレゼンテーション Presentation
ゼミなので、そもそもアクティブである。
準備学習・復習 Preparation and review
<準備学習>授業で扱う文献を必ず読んでくること。発表者は発表準備をすること。
<復習>タームレポート作成のため、授業での論点をまとめておくこと。 成績評価方法 Performance grading policy
参加状況(30%)、発表内容(30%)、タームレポート(40%)で総合的に評価する。
ただし、ゼミ生が少なく、発表の回数が多くなる場合には、タームレポートの提出は求めず、 参加状況(50%)、発表内容(50%)で総合的に評価する。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
Y
書誌情報 Bibliographic information
下記の「参考書」の中から、受講生と相談して決定する。
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
<研究不正の歴史>
ウィリアム・ブロード『背信の科学者たち:論文捏造、データ改ざんはなぜ繰り返されるのか』講談社、2006年。 アレクサンダー・コーン『科学の罠:過失と不正の科学史』工作舎、1990年。 <研究倫理> 日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会『科学の健全な発展のために: 誠実な科学者の心得』丸善出版、2015年。 https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf 黒木登志夫『研究不正:科学者の捏造、改竄、盗用』中公新書、2016年。 山崎茂明『科学者の発表倫理: 不正のない論文発表を考える』丸善出版、2013年。 <事例検討> (シェーン事件)村松秀『論文捏造』中公新書ラクレ、2006年。 (バルサルタン臨床試験疑惑)河内敏康・八田浩輔『偽りの薬:バルサルタン臨床試験疑惑を追う』毎日新聞社、2014年。 (STAP細胞事件)須田桃子『捏造の科学者:STAP細胞事件』文藝春秋、2014年。 <科学技術研究の両義性> 池内了・小寺隆幸編『兵器と大学:なぜ軍事研究をしてはならないのか』岩波ブックレット957、2016年。 池内了『科学者と軍事研究』岩波新書、2017年。 杉山滋郎『「軍事研究」の戦後史:科学者はどう向きあってきたか』ミネルヴァ書房、2017年。 <レポート・論文の書き方> 松原洋子・伊吹友秀編『生命倫理のレポート・論文を書く』東京大学出版会、2018年。 授業計画 Class plan
第1回(講義)ガイダンス:何が問われているのか
受講生の決定、授業の進め方、テキストの決定、発表分担者の決定など 第2回(講義)研究者の世界(1) 文献:『科学の健全な発展のために: 誠実な科学者の心得』 第3回(講義+議論)研究者の世界(2) 文献:『科学の健全な発展のために: 誠実な科学者の心得』 第4回(講義)研究倫理の問題とは(1) 文献:山崎『科学者の発表倫理』、黒木『研究不正』 第5回(発表と議論)研究倫理の問題とは(2) 文献:山崎『科学者の発表倫理』、黒木『研究不正』 第6回(発表と議論)研究倫理の問題とは(3) 文献:山崎『科学者の発表倫理』、黒木『研究不正』 第7回(発表と議論)研究倫理の問題とは(4) 文献:山崎『科学者の発表倫理』、黒木『研究不正』 第8回:(議論)研究倫理の問題とは(5) 文献:山崎『科学者の発表倫理』、黒木『研究不正』 第9回(資料映像鑑賞)事例検討 「史上空前の論文捏造」シェーン事件 第10回(発表と議論)その研究するの?(1) 文献:杉山『「軍事研究」の戦後史』 第11回(発表と議論)その研究するの?(2) 文献:杉山『「軍事研究」の戦後史』議論) 第12回(発表と議論)その研究するの?(3) 文献:杉山『「軍事研究」の戦後史』 第13回(発表と議論)その研究するの?(4) 文献:杉山『「軍事研究」の戦後史』 第14回(発表と議論)その研究するの?(5) 文献:杉山『「軍事研究」の戦後史』 第15回(最終回)タームレポートの提示 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
繰り返しになるが、本授業は院生同士の議論を重視するため15名程度の少人数ゼミとする。本授業は前期と後期に開講するが、学生はどちらかの学期の受講のみ(前期のみ、あるいは後期のみ)認める。
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

