シラバス情報
|
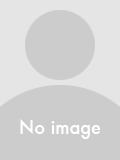
教員名 : 愼 蒼健
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
科学史 (前期水3)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
History of Science (前期水3)
授業コード Class code
99KT502
科目番号 Course number
L3IDSTS101
教員名
愼 蒼健
Instructor
Chang-Geon SHIN
開講年度学期
2025年度前期
Year
2025年度
Semester
①First semester
曜日時限
水曜3限
Class hours
Wednesday 3rd, Period
開講学科・専攻 Department
理学部第一部 応用物理学科(一般教養科目)、工学部(一般教養科目)、先進工学部(一般教養科目)、薬学部(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Department of Applied Physics, Faculty of Science Division Ⅰ A course of liberal arts, the Faculty of Engineering A course of liberal arts, the Faculty of Advanced Engineering A course of liberal arts, the Faculty of Pharmaceutical Sciences 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
<授業のやり方について>
この授業は、第1回目から対面型で授業を行う。 <概要> 科学史という特別な歴史があるのだろうか。文学史、美術史、政治史、経済史、社会史、・・・・とさまざまなジャンルの歴史学が学問として存在するが、科学史とはどのような学問なのか。ニュートンやガリレイに代表される天才・英雄の物語ならば、それ以前の人々は暗黒時代に生きていた愚か者なのか。 天文学史が天動説から地動説への「正しい進歩の歴史」、地上の運動論がアリストテレスからガリレイ・ニュートンへの「正しい進歩の歴史」であるならば、繰り返しになるが、人類は常に後から生まれた者が正しく、過去は間違った「修正すべき歴史」となってしまう。 この授業で展開する科学史とは、上記のような見方を根底から批判し、新しい見方を提示するものである。天才的科学者による発見発明の歴史という英雄史観を徹底的に排除し、科学の歴史を人間的・社会的営為として捉える視点を重視する。講義は、古代ギリシアの自然哲学、数学、自然史に始まり、19世紀科学革命で終わる。取り上げる話題は、物質「科学」に限定することなく、数学や医学の歴史にも及ぶ。科学史を単純な進歩史観とは異なる立場から論じるため、ヒストリオグラフィー(歴史叙述)の問題にも言及することになるだろう。 目的 Objectives
教養教育の目標にある以下の能力を獲得するための科目である。
「1.専門分野の枠を超えて広い視野で多元的・複眼的に自然・人間・社会を俯瞰できる能力」 「3.課題を自ら発見し、主体的に考え、解決に取り組むための論理的・批判的思考力」 より具体的に言えば、歴史的思考力の基盤を獲得し、現代の科学社会に対する批判力を身につけることにある。 到達目標 Outcomes
(1) ギリシア自然哲学から西欧近代科学成立を経て、現代科学・技術の姿が現れる19世紀までの「西欧」科学史全体の流れを把握し、それを説明できる。
(2) 授業中に疑問・関心を抱いた問題を問題化し、ショート・エッセイを書くことができる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
予備知識は必要ないが、この授業を履修する学生には次の点を望む。
(1) 教養を身につけ、自由で厚みのある思考をする人間になりたい。 (2) 学問は刺激的、挑戦的、そしてスリリングだ。そんな世界の入り口を見てみたい。 (3) 科学を内部からではなく、外の視点から見つめてみたい。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test
アクティブでない授業があるのだろうか。
準備学習・復習 Preparation and review
<準備学習>授業用スライドに目を通し、可能ならば参考文献を読んでおく。
<復習>講義内容を整理し、疑問点・問題を抽出しておくこと。 成績評価方法 Performance grading policy
小テスト・小レポート(20点)
最終試験(80点) 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
配布プリントが教科書である。
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
G.E.R.ロイド『初期ギリシア科学−タレスからアリストテレスまで』法政大学出版局、1994年。
G.E.R.ロイド『後期ギリシア科学−アリストテレス以後』法政大学出版局、2000年。 伊東俊太郎『近代科学の源流』中央公論新社、2007年。 伊東俊太郎『十二世紀ルネサンス』講談社学術文庫、2006年。 リチャード・E・ルーベンスタイン『中世の覚醒:アリストテレス再発見から知の革命へ』ちくま学芸文庫、2018年。 トーマス・クーン『コペルニクス革命−科学思想史序説』講談社学術文庫、1989年。 ジョン・ヘンリー『ヨーロッパ史入門:一七世紀科学革命』岩波書店、2005年。 ハーバート・バターフィールド『近代科学の誕生』上下、講談社学術文庫、1978年。 村上陽一郎『科学史の逆遠近法−ルネサンスの再評価』講談社学術文庫、1995年。 佐々木力『科学革命の歴史構造』上下、講談社学術文庫、1985年。 古川安『科学の社会史:ルネサンスから20世紀まで』ちくま学芸文庫、2018年。 授業計画 Class plan
第1回:科学史への誘い
内容:現代科学と歴史的思考の関係、科学を歴史的に問うことの意味について理解する。 第2回:ギリシアの自然哲学(1) 内容:科学史の授業をなぜギリシアから始めるのか。タレス、ミレトス学派、ピュタゴラス学派、イオニア学派とエレア学派、デモクリトス、プラトンまでの流れを理解する。 第3回:ギリシアの自然哲学(2) 内容:ヒポクラテスの医学論、アリストテレスの自然哲学について理解する。 第4回:ギリシア・ローマの自然哲学 内容:ヘレニズムの時代から、エピクロス派とストア派の論争を概観し、プトレマイオスの天動説とガレノス解剖学、さらにグノーシス主義、キリスト教、ギリシア思想の関係について理解する。 第5回:ラテンとビザンツの自然哲学からアラビア科学へ 内容:東西ローマ分裂からビザンティン帝国の歴史、新プラトン主義の台頭、フィロポノスのアリストテレス批判を理解する。さらに異端派キリスト教の歴史、アラビアの数学、マイル概念、医学、錬金術について理解する 第6回:12世紀ルネサンスとラテン世界の変貌 内容:12世紀ルネサンスの歴史的意義について理解する。大翻訳運動、スコラ哲学、12世期ルネサンス前後の医学史。 第7回:ラテン科学の展開 内容:中世運動論の特徴を把握し、近代科学との連続性と断絶を理解する。、インペトゥス理論、オクスフォード学派、パリ学派、中世の自然観と近代科学。 第8回:ルネサンス期の科学と医学 内容:イタリア・ルネサンスの科学史的意義について理解する。魔術的自然観の再考。ダ・ヴィンチ、ヴェサリウスの登場。 第9回:ルネサンスから科学革命へ(1) 内容:キリスト教文化と近代科学、大学史と学会の誕生。フランシス・ベーコン、科学と信仰、神=機械製作者、デカルト、ロンドン王立協会、パリ王立科学アカデミー。 第10回:ルネサンスから科学革命へ(2) 内容:自然と技術、啓蒙主義と科学。ガリレイ、ボイル、百科全書派、科学の大衆化。 第11回:第二の科学革命(1) 内容:フランス革命と科学、エコール・ポリテクニク、ジャコバン主義、ナポレオン時代の科学。 第12回:第二の科学革命(2) 内容:ドイツ近代大学の誕生。フンボルト、ベルリン大学、ゼミナール方式、テーハー、純粋な学問。 第13回 科学の専門分化と職業化、そして産業と科学 内容:科学の専門分化・職業化のプロセス、工学者の誕生、産業革命とイギリス科学、アメリカにおける産業と科学。 第14回 科学とナショナリズム、戦争 内容:科学者の国家意識、万国博覧会、軍事技術と科学、第一次世界大戦、第二次世界大戦。 第15回 まとめ 内容:理解度を確かめるため試験を行う。 SBOsコード(薬学部薬学科のみ 2023年度以前カリキュラム適用者対象)
学修事項(薬学部薬学科のみ 2024年度以降カリキュラム適用者対象)
担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

