シラバス情報
|
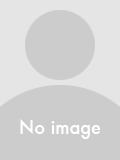
教員名 : 神野 潔
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
法の歴史と思想 (後・火3)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
History and Philosophy of Law
授業コード Class code
99K1297
科目番号 Course number
L1HSSSCc22
教員名
神野 潔
Instructor
Kiyoshi JINNO
開講年度学期
2025年度後期
Year
2025年度
Semester
②Second semester
曜日時限
火曜3限
Class hours
Tuesday 3rd Period
開講学科・専攻 Department
理学部第一部(一般教養科目)、経営学部(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Faculty of Science Division Ⅰ A course of liberal arts, the School of Management 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
本講義では、歴史学の視点と哲学の視点(思想史の視点も含む)から、法について考えていきます。今年度は特に「裁判」というものを講義全体を貫くテーマに据えて、前半では古代から近代に至るまでの日本の裁判・法曹の歴史を、西洋のそれと比較しつつ見ていきます。後半では、①そもそも「裁判」とは何か、②裁判官は法を発見しているのか創造しているのか、③「裁判」は社会の中でどのような意味を持っていると考えられるか、④「裁判」において裁判官はどのように思考しているのか、その際に感情とどのように向き合うのかなどについて広く考えていきます。
目的 Objectives
一般市民は、日常的な社会生活を営む中で、常に法的な関係に立ち入ることになり、よって法に対する正しい知識が求められます。特に近年は、市民を取り巻く法的課題が多様化・複雑化する中で(例えば婚姻のあり方や労働環境の問題など)、市民の法に対する理解力がさらに問われる状況になってきていると言えるでしょう。
その中で、本講義では、「裁判」を全体を通してのテーマとして設定し、歴史学や哲学などの学際的な視点と方法から裁判について考え、基礎的な知識を得ることと、多様な思考方法を修得することの2つを大きな目的とします。 この①・②を通して、対象を相対的・客観的に捉える力や、集めた情報を分析する力、自身の考えを他者に説明する力などを伸ばしていくことも、本講義の目的です。 到達目標 Outcomes
本講義の到達目標は、
①市民として裁判なるものと向き合い、裁判とはどのようなものなのか、歴史学・哲学などの視点と方法で説明できるようになること、 ②それを通して、物事を相対的・客観的に捉え、丁寧な思考で本質を見極め、その考えを他者に論理的に説明できるようになること、 の2つです。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
法学以外にも、歴史学、哲学などの分野に関心を持ち、文献やニュースなどに積極的に目を向ける・目を通すようにすること。担当教員とコミュニケーションを取ることを心がけ、積極的に講義に参加してください。
アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test/ディベート・ディスカッション Debate/Discussion/フィールドワーク Practice/Fieldwork
-
準備学習・復習 Preparation and review
各回の内容について、予習をして臨むこと(毎回、参考文献を示します)。また、講義後は、ノートを整理して復習すること。予習には2時間程度、復習には2時間程度かけることが望ましいと考えています。
成績評価方法 Performance grading policy
平常点課題(26点)、レポート(24点)、学期末試験(50点)の合計で評価します。
平常点課題(26点)は、第2回から第14回まで1回2点×13回分とします。 レポート(24点)は、10月から1月までのあいだに各自で法務省の資料展示室などの見学に行っていただき(もちろん行き方は詳細に説明します)、その内容と感想とを1200字程度でまとめていただくものです。 学期末試験は(50点)は、持込可で行う50分間の論述試験です。 詳細は第1回のガイダンスにおいて説明します。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
出口雄一・神野潔・十川陽一・山本英貴編『概説日本法制史〈第2版〉』、弘文堂、2023年、ISBN:978-4-335-35954-5
神野潔『三淵嘉子—先駆者であり続けた女性法曹の物語』、日本能率協会マネジメントセンター、2024年、ISBN:978-4-800-59178-4授業計画 Class plan
第1回 ガイダンスと「基礎法学」の世界
講義の進め方、成績評価の方法について説明し、また、法学と歴史学・哲学・社会学との関わり方について概観する。 第2回 法を歴史学的・哲学的に考える意味について そもそも法を歴史学・哲学に考えようとする思考や方法はどこから来たものなのか、19世紀〜20世紀のドイツ法学や明治時代〜昭和前期の日本の法学のあり方について概観する。 (第3回〜第10回は、法を歴史学的に考えていく内容である) 第3回 前近代日本の法と訴訟① 律令国家の法と裁判について、律令とはどのような法典なのかを示しつつ、制度やその背景にある思想・意識を理解する。 第4回 前近代日本の法と訴訟② 鎌倉幕府の法と裁判について、中世ヨーロッパのそれと比較しつつ、制度やその背景にある思想・意識を理解する。 第5回 前近代日本の法と訴訟③ 鎌倉幕府法の中心にある「御成敗式目」について、関するいくつかの条文を具体的に選んで(「悪口」・「謀書」・「悔返」に関する規定を予定している)読解する。 第6回 前近代日本の法と訴訟④ 戦国大名の法と裁判について(分国法の世界について)、制度やその背景にある思想・意識を理解する。 第7回 前近代日本の法と訴訟⑤ 江戸幕府の法と裁判について、刑事訴訟(吟味筋)を中心に、画像史料なども用いて、制度やその背景にある思想・意識を理解する。 第8回 近現代日本の法と訴訟(三淵嘉子を素材に)① 日本で最初の「女性法曹」である三淵嘉子は1938年に高等試験司法科に合格し、弁護士試補を経て弁護士となる。ここに見られる試験制度や試補制度などは、日本が近代的な司法制度を整備していく過程で導入されたものであった。これらのことを中心に、明治〜昭和の司法制度全般の形成と展開について理解する。 第9回 近現代日本の法と訴訟(三淵嘉子を素材に)② 三淵嘉子、そしてともに弁護士となった中田正子・久米愛は、弁護士として勤務しながら母校の教壇にも立ち、後進の指導にあたった。また、雑誌の法律相談に積極的に応じるなど、女性たちにとって法を身近なものにしようとする努力を惜しまなかった。この2点を中心にして、「女性法曹」の誕生が社会に与えた変化・意義について考える。 第10回 近現代日本の法と訴訟(三淵嘉子を素材に)③ 三淵嘉子・中田正子・久米愛に続いて、石渡満子、渡辺道子、野田愛子、鍛治千鶴子など多くの「女性法曹」たちが現れた。彼女たちのキャリアと功績を辿りながら、主に1950年代から1960年代にかけての「女性法曹」の展開を追う。また、日本統治時代の朝鮮で生まれ、戦後に韓国初の女性弁護士となる李兌栄(彼女は偶然にも三淵嘉子と同年の生まれであった)についても紹介することにしたい。 (第11回〜第14回は、法を哲学的に考えていく内容である) 第11回 裁判をめぐる法思想① H.L.Aハートとドウォーキンの論争について紹介し、20世紀を代表する二人の法学者(法哲学者)が、裁判なるものをどのように捉えていたのかを見ていく(この第8回の内容を理解した上で、第9回・第10回で法思想史を遡る内容とする)。 第12回 裁判をめぐる法思想② ホッブズやロックなど17世紀から18世紀にかけての近代自然法論を紹介し、また、それへの批判というかたちで登場してくる法実証主義の内容を理解して、そこで裁判というものがどのように捉えられていたかを見ていく。 第13回 裁判をめぐる法思想③ 19世紀から20世紀にかけて(WWⅡ以降まで)のドイツの法思想史を整理し、概念法学や再生自然法論について理解しながら、そこで裁判というものがどのように捉えられていたかを見ていく。 第14回 裁判をめぐる法思想④ 「法を解釈する」ということをめぐる方法と理論について、特に法的三段論法似ついての近年の議論を理解する。 第15回 到達度の確認と総括 到達度を確認し、また講義の内容に関する総括を行う。 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

