シラバス情報
|
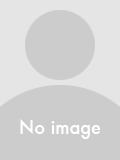
教員名 : 田村 早苗
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
初年次教養ゼミB
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Arts and Sciences Seminar in First-YearExperience B
授業コード Class code
9989G69
科目番号 Course number
L1IDSEMn25
教員名
田村 早苗
Instructor
Sanae Tamura
開講年度学期
2025年度後期
Year
2025年度
Semester
②Second semester
曜日時限
水曜2限
Class hours
Wednesday 2nd Period
開講学科・専攻 Department
経営学部 国際デザイン経営学科(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Department of International Digital and Design Management, School of Management 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
演習
Seminar 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
MIT(マサチューセッツ工科大学)メディアラボが開発したプログラミング言語学習環境「Scratch (スクラッチ)」を使って『オリジナルな作品』を作るプログラミングのゼミです。全寮制の北海道・長万部キャンパスの特徴を活かした少人数ゼミで、履修者が自主自立的に作品を作り上げていくとともに、担当教員とゼミメンバーの前で進捗状況を発表し、その内容について、議論(ディスカッション)します。授業期間の最後には、成果発表(プレゼン)を行います。
2022年度から 高校でプログラミングが必修(情報I)になったこともあり、これまでに Scratchを使ったことがある人も多いと思います。でも、Scratchといえば「小学校のプログラミング教育の教材」という印象があって、「子供だましの単純なプログラムしか作れないんじゃないか」と思っている人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。大学生が使えば、けっこう複雑で高度なプログラム、ゲームやアニメーション、音楽だって、ビジュアル的にプログラミングしていけるのがScratchの特徴です。 プログラミングの授業では、教科書に載っている「正解」のプログラムを見ながら入力したりするので、入力ミスや文法の間違いに気を取られて、楽しくないと感じる人もいると思います。この授業では、『自分が作りたいもの』つまり「正解が教科書に載っているわけではないけど、「こういうことをプログラムにやらせたい」というものを、自分で組み立てて作り上げていきます。 そして「最初は思ったように動かなかったけど、ここを直したらうまく動くようになった」という体験を繰り返しながら、「文法」ではなく、「アルゴリズム(なぜ、こういうプログラムになるのか)」を学び、自力でプログラムを組み立てる能力を身につけます。 目的 Objectives
企画(テーマ)立案から発表(プレゼン)までを経験することで、将来の卒業研究などに必要な基礎力を身につけます。また、指導教員やゼミメンバーとの議論(ディスカッション)を通して、論理的・批判的思考力、コミュニケーション能力を養います。
国際デザイン経営学科のディブロマ・ポリシーの8に規定される「自然・人間・社会に係る幅広い教養を修得し、専門分野の枠を超えて横断的に物事を俯瞰できる能力」を育てるための科目であるとともに、同学科のカリキュラム・ポリシーの4に規定される「自然・人間・社会を幅広く俯瞰できる能力、論理的・批判的思考力、コミュニケーション能力、国際性、自己管理能力を養う」ための科⽬です。 到達目標 Outcomes
・自力でプログラミングできるようになる
・他者が公開しているScratchのプログラム(スクリプト)をアレンジしたり カスタマイズしたりして 利用できるようになる ・テーマに関して図書館の蔵書やweb等を利用して調査し、適切に引用できるようになる ・テーマに関して自主自立的に方向性を考え、計画を立てることができるようになる ・教員やゼミメンバーに分かりやすく説明し、建設的議論ができるようになる ・進捗状況や結果について発表(プレゼン)ができ、質疑応答に的確に対応できるようになる 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
履修者が所有するPC(BYOD)でプログラミングや発表(プレゼン)を行うので、「入学のしおり」に記載の条件を満たすPCを準備し、授業時に教室(PC室、電源コンセントあり)に持参して下さい。もし、PCに故障等が起こって授業に支障が生じた場合には、大学の自分のメールアカウント(学籍番号@ed.tus.ac.jp)から授業の担当者宛(tam@rs.tus.ac.jp)に直ちにメール連絡し、指示を仰いで下さい。
同一科目名「初年次教養ゼミ」で、異なる教員による複数クラスが開講されていますが、担当教員によって内容が異なるので注意して下さい。 自主自立的に計画をたててプログラミングを進めることが求められます。そのことを充分に留意して履修して下さい。 本ゼミでは定員を10名以下としていますので、希望者が定員を超えた場合は抽選等を行う場合があります。 本ゼミでは、毎回の授業時間は進捗状況の報告と議論にあてます。授業時間中にプログラミング作業を行うわけではありません。 原則として、対面形式で授業を実施します。なお、新型コロナやインフルエンザ等の感染爆発の恐れがあるために、学寮生活の維持が困難と大学が判断し、学寮が閉寮となった場合には、オンライン授業に切り替える場合があります。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
ディベート・ディスカッション Debate/Discussion/プレゼンテーション Presentation/実習 Practical learning
-
準備学習・復習 Preparation and review
毎回の進捗報告の際には、現在取り組んでいる課題(解決が必要な問題点)を明確にするとともに、必要な情報を書籍やweb等で調査し、スライドを作成して進捗報告の準備をして下さい(準備学習)。ゼミの終了後には、進捗報告での議論の内容をまとめ、次の準備に生かして下さい(復習)。授業の各回における具体的な準備学習・復習については、「授業計画」を参照して下さい。
成績評価方法 Performance grading policy
成績は、毎回の進捗報告の「発表」「議論」に対する評価(成績評価の60%程度を予定、正当な理由なしに欠席した回は評価されないので注意)と、授業期間の最後に行う成果発表(プレゼン、成績評価の40%程度を予定)で評価します。『オリジナルな作品』でないものは評価しません。
この授業では、シラバスの「目的」の項にあるように、プログラミング能力を養うだけでなく、毎回の進捗報告での指導教員やゼミメンバーとの議論(ディスカッション)を通して、論理的・批判的思考力、コミュニケーション能力を養います。毎回の進捗報告における「議論」を重視しますので、自分が良いアドバイスをもらうためにも、他のゼミメンバーに良いアドバイスをしてあげましょう。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
「Scratchではじめよう!プログラミング入門」https://scratch.mit.edu/
「Scratchではじめよう!プログラミング入門 チュートリアル」https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=all 「Scratch Coach チュートリアル」 https://scratch.coach/how-to/ 授業計画 Class plan
すべての履修学生に対して、全ての授業回を対面で受講することを求めています。
1 合同ガイダンス 初年次教養ゼミの概要、目的、評価方法などを理解する。 【指定された日までに】授業担当者に「履修したい」or「履修しない」を旨を正式に連絡する。 【次回までの宿題】Scratchのアプリのインストール(https://scratch.mit.edu/download) 2 Scratchの使い方演習① 自分のノートPCにScratchのアプリをインストールし、Scratchの使い方を演習する。 【第4回までの宿題①】自分がScratchでやってみたいことについて、第4回の授業で発表する準備をする。 【第4回までの宿題②】自分がやってみたいことの参考になりそうな、他のScratch作品の例を調べ、どうすれば「自分がやってみたいこと」が実現できそうか発表する準備をする。 3 Scratchの使い方演習② Scratchの使い方を演習する。 【次回までの宿題①】自分がScratchでやってみたいことについて、第4回の授業で発表する準備をする。 【次回までの宿題②】自分がやってみたいことの参考になりそうな、他のScratch作品の例を調べ、どうすれば「自分がやってみたいこと」が実現できそうか発表する準備をする。 4 テーマの検討 担当教員とゼミメンバーの前で、Scratchを使って自分がやってみたいことを発表する。 自分がScratchでやってみたいことの参考になりそうな他のScratch作品を適切に引用し、どのようにすれば「自分がやってみたいこと」が実現できそうか、担当教員やゼミメンバーと議論する。 【授業終了時の提出物】発表に使ったスライドファイル 【次回までの宿題①】テーマ(自分がやってみたい事柄)を再検討・再構成し、今後のプログラミング指針やタイムスケジュールをまとめ、次回の授業で発表する準備をする。 【次回までの宿題②】Scratchでのプログラミングを開始し、次回の進捗報告の準備をする。 5 テーマの決定、進捗報告① 担当教員とゼミメンバーの前で、テーマ(自分がやってみたい事柄)を再検討・再構成した結果と、今後のプログラミング指針やタイムスケジュールを発表・議論し、 自身のテーマを決定する。 担当教員とゼミメンバーの前で進捗状況を発表し、その内容について議論する。 【指定された時刻までの事前提出物】Scratchファイル、発表に使うスライドファイル 【次回までの宿題①】自分でたてた計画にしたがってScratchでのプログラミングを進め、次回の進捗報告の準備をする。 【次回までの宿題②】必要に応じて方向性を軌道修正し、タイムスケジュールをまとめ直す。 6〜10 進捗報告②〜⑥ 担当教員とゼミメンバーの前で進捗状況を発表し、その内容について議論する。期待した結果が得られなかった場合には、問題点を明確にし、解決のためにはどうしたらよいか議論する。 【指定された時刻までの事前提出物】Scratchファイル、発表に使うスライドファイル 【次回までの宿題①】自分でたてた計画にしたがってScratchでのプログラミングを進め、次回の進捗報告の準備をする。 【次回までの宿題②】必要に応じて方向性を軌道修正し、タイムスケジュールをまとめ直す。 11 成果発表に向けての準備 過去の先輩たちがおこなった成果発表の動画を見ることによって、第14回に実施する成果発表のイメージをつかむとともに、プログラミングの方向性を再度吟味し、軌道修正を行う。 【次回までの宿題①】成果発表に向けて方向性を軌道修正し、タイムスケジュールをまとめ直す。 【次回までの宿題②】修正した計画にしたがってプログラミングを進め、次回の進捗報告の準備をする。 12 進捗報告⑦・成果発表の準備① 成果発表を念頭において、これまでの結果を系統的に整理し、考察を加える。 当教員とゼミメンバーの前で進捗状況を発表し、その内容について議論する。 【指定された時刻までの事前提出物】Scratchファイル 【授業終了時の提出物】発表に使ったスライドファイル 【次回までの宿題】発表の構成上不足している事柄を検討し、次回の進捗報告の準備をする。 13 進捗報告⑧・成果発表の準備② 成果発表を念頭において、これまでの結果を系統的に整理し、考察を加える。 当教員とゼミメンバーの前で進捗状況を発表し、その内容について議論する。 【指定された時刻までの事前提出物】Scratchファイル 【授業終了時の提出物】発表に使ったスライドファイル 【次回までの宿題①】次回の成果発表会に向けて、スライドや発表原稿を完成させる。 【次回までの宿題②】成果発表の練習やリハーサルを行うとともに、質疑応答の対策を立てる。 14 成果発表 自ら成果発表するとともに、他のゼミメンバーの発表を聴き、質疑や討論を行うことにより、多能な価値観に触れ、自らの成果発表を客観的に評価する。 【指定された時刻までの事前提出物】成果発表で使うスライドファイル、発表原稿、Scratchファイル 15 総括 これまで行ってきた、プログラミング、進捗報告、ゼミメンバーとのディスカッション、成果発表などを振り返り、反省点や問題点を明確にし、各自の活動を評価する。 【提出物】自己評価(LETUSの「フィードバック」で回答、※提出物扱い) 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

