シラバス情報
|
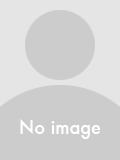
教員名 : 田村 早苗
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
情報基礎および演習1 (j,k,l)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Information Basics 1 (j,k,l)
授業コード Class code
9989B44
科目番号 Course number
89COZZZ101
教員名
田村 早苗
Instructor
Sanae Tamura
開講年度学期
2025年度前期
Year
2025年度
Semester
①First semester
曜日時限
月曜3限
Class hours
Monday 3rd Period
開講学科・専攻 Department
経営学部 国際デザイン経営学科
Department of International Digital and Design Management, School of Management 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
演習
Seminar 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
高校で必修の「情報I」などの情報系科目で習得した基礎的な情報/コンピューター活用能力を前提に、大学生活および将来の研究・仕事に不可欠な、情報/コンピューター利用スキルを身につけます。
目的 Objectives
・理科大の学内ITサービス(学内Wi-Fi、CLASS、LETUS、Microsoft365メール、Box、Zoom)を使えるようになる。
・主流ビジネスアプリケーションである Word, Excel, Power Pointを 理科大生として恥ずかしくないレベルで使えるようになる。 ・大学図書館のデータベース等の学習リソースにアクセスして情報検索ができるようになる。 ・大学のレポートやプレゼンなどにおける引用と参考文献の書き方(出所の明示)のルールを理解する。 ・プライベートで使うSNSでのメッセージ交換と、大学のアカウントを使ったメールのやりとりの違いを理解し、送信マナーを身につける。 ・著しいスピードで発展・変化していくネット社会に必要なルール、マナー及びモラルを身につける。 国際デザイン経営学科のカリキュラム・ポリシーの6 に規定される、「基礎学⼒を強化した上で、「専⾨科⽬」との接続を図る」ための科⽬であり、また、カリキュラム・ポリシーの1 に規定される、「定量的および定性的なアプローチにより、経営・経済活動及び⼈間⾏動を解析・理解するための科学的理論体系と分析⼿法」の基礎を⾝に着けるための科⽬の⼀つです。 到達目標 Outcomes
・理科大の学内ITサービス(学内Wi-Fi、CLASS、LETUS、Microsoft365メール、Box、Zoom)を使えるようになる。
・主流ビジネスアプリケーションである Word, Excel, Power Pointを 理科大生として恥ずかしくないレベルで使えるようになる。 ・大学図書館のデータベース等の学習リソースにアクセスして情報検索ができるようになる。 ・大学のレポートやプレゼンなどにおける引用と参考文献の書き方(出所の明示)のルールを理解する。 ・プライベートで使うSNSでのメッセージ交換と、大学のアカウントを使ったメールのやりとりの違いを理解し、送信マナーを身につける。 ・著しいスピードで発展・変化していくネット社会に必要なルール、マナー及びモラルを身につける。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
履修者が所有するPC(BYOD)で演習を行うので、授業開始までに「入学のしおり」に記載の条件を満たすPC(演習では、Webカメラとマイク、イヤホン等も使用)を準備して下さい。原則として、Windows11を使用していることを前提に、授業中の説明を行います。演習の性質上、スマホやタブレットのみでの受講は不可です。異なる曜日や時間帯に、同じ科目名で複数のクラスを開講していますが、クラスにかかわらず内容は同一で、成績評価もクラスごとではなく全体で行います。
授業の際には、教室(PC室、電源コンセントあり)に、履修者が所有するPCを持参して下さい。PCに故障等が起こって授業に支障が生じた場合には、大学の自分のメールアカウント(学籍番号@ed.tus.ac.jp)から授業の担当者宛に直ちにメール連絡して、指示を仰いで下さい。 原則として対面形式で授業を実施します。なお、新型コロナやインフルエンザ等の感染爆発の恐れがあるために、学寮生活の維持が困難と大学が判断し、学寮が閉寮となった場合には、オンライン授業に切り替える場合があります。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
小テストの実施 Quiz type test/グループワーク Group work/プレゼンテーション Presentation/実習 Practical learning
-
準備学習・復習 Preparation and review
文部科学省の「大学設置基準」により、大学での単位の認定には、単位あたり45時間の学修が必要であると定められています。したがって、この科目(2単位)の単位認定に必要な学修は90時間となり、授業時間以外に毎週4時間程度の準備学習・復習が必要です。各回の講義資料は、原則としてその前の回の授業終了後からLETUSで事前公開するので、十分な授業外準備学習(目安として2時間程度)を行い、授業時間内に課題を提出できるように準備して下さい(授業時間内に提出できなかった場合には授業当日であれば提出遅延を認めますが、減点対象となります)。
演習内容や課題に関しては、オフィスアワーに質問を受け付けるとともに、各自の大学のメールアカウント(学籍番号@ed.tus.ac.jp)から授業担当者宛(tam@rs.tus.ac.jp)のメールでの質問を随時受け付けます。加えて、授業時間内に教室(PC室)で直接質問に対応しますので、これらの質問対応を十分に活用して、授業時間内に課題を提出して下さい。また十分な復習(目安として2時間程度)を行い、確認テストの準備を行って下さい。 成績評価方法 Performance grading policy
この科目はいわゆる 座学(講義形式の授業)ではなく、演習を伴う授業です。教室(PC室)に来て自分のPCで演習することが成績評価の前提であり、教室(PC室)に来ないで課題だけ出しても、評価の対象としません。
成績は、確認テスト(あわせて5回実施予定)の得点(成績評価の30%程度を予定)および 提出物の提出状況と内容(70%程度を予定)に、授業態度(減点法)を加味して評価し、到達度評価(試験)は行いません。確認テストや提出課題等で不正行為が明らかになった場合には、不正行為を行った者も、不正行為を手助けした者も、相応の処置をとります。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
Y
書誌情報 Bibliographic information
『情報リテラシー アプリ版 Windows11/Office2021対応』、富士通エフ・オー・エム株式会社(FOM出版)、ISBN978-4-938927-56-1
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
参考書として特定の書籍を購入する必要はありません。
必要な参考書を、各自の経験や必要に応じて各自で準備して下さい。 授業計画 Class plan
すべての履修学生に対して、全ての授業回を対面で受講することを求めています。
1 ガイダンス、演習環境の構築 この授業の概要、目的、到達目標を理解し、授業の受け方、必要な準備学習および復習について知る。 学内Wi-Fi、CLASS、LETUS、Box、Zoomなどの理科大の学内ITサービスが使えることを確認する。 ファイル名の拡張子が表示されるように、自分のノートPCのOSの設定を変更する。 大学のアカウントを使用して、自分のPCにMicrosoft Officeサブスク版をインストールする。 2 Zoomを使ったオンライン授業のために Zoomミーティングへの参加、リアクションのしかた、名前の変更、背景の変更、画面共有などを実習するとともに、ブレークアウトルーム機能を体験する。 加えて、自分が「ホスト」になり、自分のZoomミーティングに他の人を「招待」することを実習する。(※この実習はグループワークで実施する) 3 理科大のメールアカウント、情報倫理 大学のメールアカウントに署名を設定し、教職員とのメールのやりとりのマナーを身につける。 新入生に義務付けられているe-learning 情報セキュリティ教育「INFOSS情報倫理2025(速習版)」を受講し、修了テストを受験する。(※修了テスト得点を確認テスト10点分に換算し、成績に算入) PC室にあるレーザープリンターを使って印刷できるようになる。(印刷に必要なので、学生証を持参) 4 Power Pointを使ったオンラインプレゼン(1) LETUS上でオンラインプレゼンをするためのPower Pointの利用法を身につける。 具体的には、PowerPointで練習用スライドを作成して音声を録音したものを動画ファイルにエクスポートし、LETUSの「ワークショップ(=学生間で相互閲覧ができるツール)」に提出する。 (マイク(※ノートPCに内蔵されていない場合)とイヤホン等を持参) 5 Power Pointを使ったオンラインプレゼン(2) 著作権や肖像権等に配慮し、オンラインで公開することを考慮した上で、PowerPointを用いて 自己紹介スライド(.pptx、1分程度)を作成し、それに音声を録音した上で動画ファイルにエクスポートし、LETUSの「ワークショップ(=学生間で相互閲覧ができるツール)」に提出する。 (マイク(※ノートPCに内蔵されていない場合)とイヤホン等を持参) 6 大学図書館データベースの利用 自分のPCにVPN接続(自宅など、学外から大学図書館データベースを利用する際に必要)用のアプリをインストールし、VPN接続ができるようになる。 大学図書館のデータベースなどの学習リソースにアクセスし、情報検索ができるようになる。 7 正しい「引用」と 参考文献の書き方 大学のレポート、プレゼンなどにおける引用と参考文献の書き方(出所の明示)のルールを理解する。 実際に 適切な「引用」と「出所の明示」を行ったレポートを作成する。 LETUSの課題提出に付随する「剽窃チェック」機能を体験する。 8 Word(1)〜表現力をアップする機能を使ってみよう ページ罫線の設定、ワードアートの挿入、段組み、タブとリーダー、インデント、PDFファイルとして保存を演習する。 PC室にあるレーザープリンターを使ってWordファイルを印刷する。(印刷に必要なので、学生証を持参) 9 Word(2)〜長文のレポートを編集しよう ページ番号の挿入、改ページの挿入、見出しの設定、脚注の挿入、引用文献一覧の作成、数式の入力(数式ツール)を演習する。 10 Word(3)〜文章を校閲しよう 自動文章校正、表記ゆれチェック、自動スペルチェック、検索と置換、コメントの利用、変更履歴の利用を演習する。 11 Excel(1) データの入力、表の作成・編集・印刷を演習する。相対参照と絶対参照を使えるようになる。 12 Excel(2) グラフの作成、データベースの操作、複数シートの操作を演習する。 13 Excel(3) 関数、ユーザー定義の表示形式の設定、条件付き書式の設定を演習する。 14 Excel(4) 高度なグラフの作成、ピボットテーブルの作成、ExcelデータのWordへの取り込みを演習する。 15 まとめ これまで行ってきた授業内容を振り返り、各自の到達度を自己評価する。 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
Microsoft Office(Word, Excel, Power Point)
備考 Remarks
-
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

