シラバス情報
|
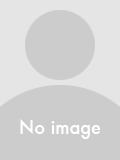
教員名 : 小島 尚人
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
リモートセンシング
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Remote Sensing
授業コード Class code
9976403
科目番号 Course number
76CEPLG301
教員名
小島 尚人
Instructor
Hirohito Kojima
開講年度学期
2025年度後期
Year
2025年度
Semester
②Second semester
曜日時限
水曜4限
Class hours
Wednesday, 4th Period
開講学科・専攻 Department
創域理工学部 社会基盤工学科
Department of Civil Engineering, Faculty of Science and Technology 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
② [対面]ハイフレックス型授業/ [On-site] Hybrid-Flexible format (must include 50%-or-more classes held on-site)
概要 Description
国土の姿を「見る、測る」ことは、測量の基本となる。本講義では、数多くの先端測量・観測技術のうち、特に国土の姿を「見る、測る」技術としての「リモートセンシング(遠隔探査技術)」について解説する。指定する教科書、映像等を用いて、講義形式で実施する。
理大e-learningシステム(LETUS)にアップする講義資料による復習(受講学生のみ)を通して、講義内容の理解を深める。本講義の内容は、別途開講する国土情報工学(3CV:専門選択科目)の基礎知識にもなる。 目的 Objectives
国土の姿を観測する技術として広く利用されているリモートセンシングの観測原理を学ぶとともに、リモートセンシングデータの「収集、処理・解析、活用」といった一連の処理の流れについて理解、説明できるようになることを目的とする。
リモートセンシングデータの適用事例として、気象観測、陸域観測、海域観測の3種類に大別した上で、リモートセンシングデータの活用事例について幅広く解説する。利用者の立場から見た「リモートセンシングの位置付けと役割」、「効用と限界」、「今後の展望」について学習、説明できるようになる。 到達目標 Outcomes
到達目標は、以下のとおりである。
1)測量の歴史を含めて、リモートセンシングの誕生から現在までの技術開発の状況を学習するととも に、今後の展望(次世代リモートセンシング)について理解、説明できるようになる。 2)「広域同時性、反復性、多波長性」といった特徴を有するリモートセンシングという技術の観測原理 を理解、説明できるようになる。 3)リモートセンシングデータの「収集、処理・解析、活用」といった一連の処理の流れを学習するとともに、リモートセンシングの「位置付け、役割」を理解、説明できるようになる。 4)気象観測、陸域観測、海域観測の3種類に大別した上で、リモートセンシングデータの活用事例について学習し、国土の姿を観測する技術としてのリモートセンシングの「効用と限界」を理解、説明できるようになる。さらに、今後の展望として、次世代のリモートセンシングに求められる要件を理解、説明できるようになる。 *社会基盤工学科が定める学習・教育目標との関連 上記到達目標は、下記の「主として関連する学習・教育目標」に基づいている。 主として関連する学習・教育目標: 目標(B):土木工学のすべての主要専門分野(構造・材料、地盤、水理、環境・情報、計画)の基礎知識を習得するとともに、応用できるようになる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
・本科目は、他学科履修および他学科聴講の受付は「無し」としていただいております。
・1回目の講義から下記の指定「教科書」を使用しますので、 必ず購入して講義に持参下さい。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
-
-
準備学習・復習 Preparation and review
準備学習:各回の講義に該当する教科書の章・節の部分を事前に読んでおく。
復習:教科書と配布資料について、授業で読み合わせした箇所を再度、復習し、理解を深め、達成度評価試験に反映させる。 成績評価方法 Performance grading policy
・到達度評価試験 100%(得点取得率60%以上で合格)
[フィードバックの方法] ・解答例は、LETUSに掲載。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
Y
書誌情報 Bibliographic information
基礎からわかるリモ−トセンシング 理工図書
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
・LETUS上に適宜アップロードするコンテンツ(音声付き&音声無し)
授業計画 Class plan
[対面]ハイフレックス型授業:半数以上の授業回を対面で受講することを求める。
以下の各回の講義をとおして、各項目の内容を学習、理解し、説明できるようになる。 1.リモートセンシングとは 下記の内容について、理解、説明できる。 ・リモートセンシングとは何か ・リモートセンシングの歴史 ・リモートセンシングのタイプ 2.大気へのリモートセンシングの応用 下記の内容について、理解、説明できる。 ・雲、降雨、エアロゾルの観測 ・成層圏オゾンの観測 ・気象業務におけるリモートセンシングの利用 3.陸域へのリモートセンシングの応用(その1) 下記の内容について、理解、説明できる。 ・土地利用・土地被覆 ・DEM、地図 ・都市の熱環境 ・災害: 災害発生前、災害発生中、災害発生後 4.陸域へのリモートセンシングの応用(その2) 下記の内容について、理解、説明できる。 ・農業 ・自然環境 ・森林・林業 ・砂漠化 ・氷河・氷河湖 5.水域へのリモートセンシングの応用(その1) 下記の内容について、理解、説明できる。 ・水質・海色:水質と分光特性、沿岸域・湖沼、外洋、油汚染 ・海面水温:海面からの熱放射、海面水温推定のための大気補正、 沿岸域と外洋域への応用 6.水域へのリモートセンシングの応用(その2) 下記の内容について、理解、説明できる。 ・水深推定、サンゴ礁・藻場、水生生物 ・マイクロ波による外洋の観測:海氷、海上風と波浪、海面高度と表層海流、海面塩分 ・水産業 7.リモートセンシングに関わる専門用語の整理 ・これまでに学習した内容とディジタル教材をもとに、 リモートセンシングに関する特有の専門用語について整理し、理解、説明できる。 8.電磁波とリモートセンシング 下記の内容について、理解、説明できる。 ・リモートセンシングの概念(一部復習含む) ・電磁波の性質 ・物質と電磁波の相互作用 ・電磁波の波長帶域(一部復習) ・波長帶域による]リモートセンシングの種類 ・放射量の定義 ・物体の分光反射特性 9.プラットフォーム 下記の内容について、理解、説明できる。 ・プラットフォームとは ・プラットフォームの高度 ・人工衛星 ・軌道 ・航空機 ・成層圏プラットフォーム ・UAV(Unmanned Aerial Vehicle)、車両、船舶 10.画像強調と特徴抽出(スペクトル情報)その1 下記の内容について、理解、説明できる。 ・画像濃度値の変換:線形変換、区分線形変換、3角波変換、連続関数変換 ・無相関ストレッチ ・ヒストグラム変換 ・色空間への変換:シュードカラー表示、カラー合成表示 11.画像強調と特徴抽出(空間情報・時間情報)その2 下記の内容について、理解、説明できる。 ・空間情報の画像強調と特徴抽出 ・鮮鋭化、エッジ・線の抽出:画像微分処理、フィルタ処理、フィルタによる微分処理 ・テクスチャ特徴量の抽出 ・時系列画像間処理 12.画像分類 下記の内容について、理解、説明できる。 ・画像分類の流れ ・トレーニングデータとは ・教師付き分類と教師無し分類の定義 ・画像分類精度の評価方法 13.SAR(Synthetic Aperture Radar:合成開口レーダ)の基礎 下記の内容について、理解、説明できる。 ・SARの観測原理 ・実開口レーダ(RAR:Real Aperture Radar)とSAR ・SAR画像の幾何学的歪:フォアショートニング、レイオーバ、シャドウイング ・SAR画像の特徴:マイクロ波散乱とSAR画像強度 ・表面散乱と体積散乱 14.講義全体のコンテンツ整理 ・講義全体のコンテンツ、データ整理、とりまとめ。 15. 到達度評価試験 ・当該授業の到達度を到達度評価試験により確認する。 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
下記の実務経験を活かし、本科目の講義を実施する。
・企業での環境情報関連のシステム設計・開発 ・建設コンサルタント業務:土木計画系、環境計画系 ・国土調査事業(リモートセンシング含む) 教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
特になし
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

