シラバス情報
|
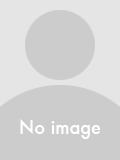
教員名 : 和田 直之
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
生物科学特別講義3
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Lecture in Biological Science 3
授業コード Class code
9964161
科目番号 Course number
64BIZZZ305
教員名
市川 寛子、大石 勝隆、菅野 茂夫、笹沼 博之、和田 直之
Instructor
Naoyuki WADA, Katsutaka OHISHI, Shigeo SUGANO, Hiroyuki SASANUMA, Hiroko ICHIKAWA
開講年度学期
2025年度前期
Year
2025年度
Semester
①First semester
曜日時限
月曜4限、月曜5限
Class hours
Monday, 4-5 periods
開講学科・専攻 Department
創域理工学部 生命生物科学科
Department of Applied Biological Science, Faculty of Science and Technology 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
目的 Objectives
社会的課題に力点を置いた応用生物科学研究について専門の研究者の取り組みについて学び,それぞれの重要性を理解する。
到達目標 Outcomes
それぞれの講義内容の要旨について説明でき,また講義担当者による課題に対して取り組むことで,研究の意義や重要性を理解し,説明できる。
卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
・原則,すべての授業を対面で実施する。
・時間割上,この科目と教職科目が重なった場合には、3年次または4年次のどちらかで履修して下さい。 ・成績評価基準については,初回講義の時に説明するので,必ず出席して下さい。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test
-
準備学習・復習 Preparation and review
オムニバス形式の授業なので,準備学習は求めない。
講義後は,各回の講義内容について,それぞれの分野の現状と発展について復習すること。 成績評価方法 Performance grading policy
授業に臨む姿勢、レポート、試験等を総合して評価します。
なお,授業に臨む姿勢に問題がある,各教員による課題(レポートなど)への取り組みが不十分である,などと判断される場合は,単位認定されません。 評価の基準については初回講義の時に説明するので,必ず出席して下さい。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
各教員から,授業中に資料を配布する。
授業計画 Class plan
担当教員
大石勝隆先生(国立研究開発法人,産総研), 菅野茂夫先生(国立研究開発法人,産総研), 笹沼博之先生(都医学研), 市川寛子先生(教養教育研究院野田) 日程 ※原則,すべての授業を対面で実施する。 4/14 オリエンテーション(和田) 続いて 1, 2回 笹沼 4/21 3,4回 笹沼 4/28 5,6回 市川 5/12 7,8回 大石 5/19 9,10回 大石 5/26 11,12回 菅野 6/2 13,14回 菅野 (第14回で終了予定です) 講義内容 第1回:和田 オリエンテーション 第1-4回:笹沼博之(都医学研) 1回目. 正常細胞とがん細胞を区別するもの:ゲノムの安定性維持機構とその破綻 増殖シグナル伝達、細胞周期は厳密に制御される。その破綻はただちに、細胞の異常増殖、種々の染色体異常などを引き起こし、がんなどの疾患あるいは老化の原因となる。本講義では、私達の研究室で行われている染色体安定性維持機構についての最新の研究成果を示しながら、ゲノムの安定性を脅かす、種々の生体ストレス、及びそれらから生体を守るシステムを説明する。 2回目. 個体を形作る細胞の多様性とその制御 個体を形作る細胞の種類は多岐にわたるが、個体を形成する細胞の中で最も異なる細胞分裂様式は、体細胞と生殖細胞である。体細胞と生殖細胞の違いを染色体構造という観点から解説する。また本講義では、ゲノム編集技術の発展と臨床応用に向けた倫理的問題を説明する。 3回目. 染色体安定維持機構の普遍性と多様性 本講義では、DNA損傷と複製の種を超えた普遍的メカニズムを紹介する。最近、新たに作製したDNA修復・複製因子の変異マウスの解析から、細胞を使った研究では見えてこなかった、臓器や組織特異的なDNA複製・修復因子の機能について講義する。また、染色体不安定性に起因する疾患、特にがんを中心に、最先端研究を紹介する。 4回目. ゲノム不安定化と発がん 2011年に最も権威のある学術誌Cellに掲載された論文『Hallmarks of Cancer: The next generation』で記述された8つのがん細胞の生存戦略の中の「免疫逃避」「ゲノム不安定化と変異」を説明する。また近年のがん罹患の国内外の現状を紹介と最新のがん治療を紹介する。 第5,6回 市川寛子(教養教育研究院野田) 第5回 感情と身体 感情と身体の相互関係について、最新の心理学・神経科学の知見をもとに学ぶ。 古典的な感情理論、内受容感覚(身体内部の感覚)が感情に与える影響や、ダマシオのソマティックマーカー仮説を中心に、身体の変化が意思決定や情動調整にどのように関与するかを探る。理論と実証研究を交えながら、感情の身体的基盤に対する理解を深めることを目指す。 第6回 笑いの健康効果 第5回で説明した感情のうち快感情に注目し、笑うことが健康に与える影響を、自律神経系と表情表出の観点から探る。ポリヴェーガル理論に基づき、腹側迷走神経が社会的交流やストレス緩和に果たす役割を解説し、笑いがどのように副交感神経を活性化し、心身の健康を促進するかを考察する。また、表情筋と情動の双方向的関係(顔面フィードバック仮説)にも触れ、笑いの心理的・生理的効果を理解する。理論と実証研究を交えながら、笑いの健康効果について深く学ぶ。 第7-10回:大石勝隆(国立研究開発法人,産総研) 7. 時間生物学(1)〜生物とリズム〜 微生物からヒトに至るまで、地球上のほとんどの生物には、様々な周期のリズム現象がみられる。これらのリズム現象には、地球の自転や公転に伴う24時間あるいは1年間の環境変化に対する受動的なものと、生物に内在する時計機構に支配された自律的なものが存在する。本講義では、生物が持つ様々なリズム現象について、哺乳類における概日リズム(サーカディアンリズム)を中心に概説する。 8. 時間生物学(2)〜中枢時計と末梢時計〜 体内時計のリズム発振を制御している時計遺伝子は、脳内の時計中枢のみならず、肝臓や腎臓、脂肪、皮膚、血球に至るまで、体を構成しているほぼ全ての細胞において発現が認められる。時計分子は、個体の行動リズムのみならず、糖・脂質代謝や免疫機能、薬物代謝など、多様な生理機能に関与している。本講義では、時計遺伝子によるリズム発振メカニズムや、哺乳類における体内時計の階層性について概説する。 9. 時間生物学(3)〜体内時計と生活環境〜 本講義では、体内時計の外部環境への同調性について、食餌による影響を中心に概説する。社会の24時間化に伴い、国民成人の5人に1人が睡眠に不満を感じているといわれている。睡眠障害は、うつ病や精神疾患のみならず、糖尿病や肥満、高血圧などの生活習慣病とも深く関連しており、大きな社会問題となっている。本講義では、体内時計の乱れと睡眠障害との関係についても概説する。 10. 時間生物学(4)〜時間生物学研究の実例〜 私たちの研究室では、①睡眠障害や体内時計に関連する様々な疾患の発症メカニズムの解明、②睡眠障害の診断技術の開発、③体内時計を積極的に操作するための技術開発、を目指した基礎研究から産業応用化への橋渡し研究を行っている。本講義では、いくつかの企業との共同研究による時間栄養学的な研究成果を含めて紹介する。 第11-14回:菅野 茂夫(国立研究開発法人,産総研) 11. ゲノム解析技術:シークエンサーの動作原理 生命の根本となるDNA配列はどのように解析されるのか。サンガー法からはじめ、Sequence by synthesis法を概説し、最新の遺伝子解析装置を含めてその原理、現状の課題を整理する。 12. ゲノム決定と機能注釈 11.にてDNA配列決定のための原理を学んだところで、次に、実際に生物のゲノム決定がどのように実施されているかを概観する。加えて、ゲノム配列が決定されたとしても、ゲノムはただの配列の塊であり、有効利用するためには機能注釈が必要である。機能注釈の方法とその問題点、課題についても紹介する。 13. 遺伝子機能の推定および決定 包括的な手段でゲノムに機能注釈ができたとしても、その機能の実験的な証明は不可欠である。大腸菌ですら、機能が実験的に証明されている遺伝子は50%に満たない。分子遺伝学的手法によってどのように遺伝子機能を明らかにする手段を概説し、CRISPR-Cas9と1細胞解析の登場に一変しつつある機能遺伝学について説明する。 14. ゲノム配列のデザイン 本講義では、最新の知見(深層学習を使用した遺伝子発現調節領域の可視化)を紹介するとともに、ゲノムをデザインするとはどういうことなのかを考えてみたい。時間がゆるせば、合成生物学的なアプローチについても概説する。 15回については別途指示します。 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
講義日程は変更になる場合があります。事前にBS事務前掲示板やCLASSで確認して下さい。
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

