シラバス情報
|
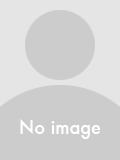
教員名 : 坂本 徳仁
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
経済学基礎特殊講義 (木3)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Basic Topics in Economics (木3)
授業コード Class code
9960514
科目番号 Course number
L2IDSEMb24
教員名
坂本 徳仁
Instructor
開講年度学期
2025年度後期
Year
2025年度
Semester
②Second semester
曜日時限
木曜3限
Class hours
Thursday 3rd
開講学科・専攻 Department
創域理工学部(一般教養科目)
A course of teacher education, the Faculty of Science and Technology 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
経済・社会現象に関わる諸問題について、少人数(20名前後)のゼミ形式で研究します。履修者の関心に応じて、以下の3つの問題群について専門文献を講読し、経済・社会現象を数理的に分析する能力を涵養します。
1.望ましい社会的意思決定方法の構築可能性について: 多くの組織では、多数決やそれに準じた方法で集団の意思決定を行っています。しかし、多数決には「AがBに勝ち、BがCに勝ち、CがAに勝つ」という「どの選択肢を選んでも必ずそれに勝つ選択肢が存在する」という病理的な現象が発生することが知られています。本課題では、①このような病理的な状況を回避できる望ましい社会的意思決定の方法が存在するか否か、②望ましい基準が複数ある中で、各基準はどの程度まで両立可能であるのか、といった問題を数理的に分析します。 2.望ましいマッチング方法の設計問題について: 本課題では、①新米医師の研修先としてどの病院を割り当てるべきか、②入園を希望する幼児をどの保育園に入れるべきか、といった問題のように、「限られた枠や資源を人々に割り当てる」という問題について考えます。具体的には、①望ましいマッチング方法の解の存在と一意性、②望ましいマッチング方法の計算アルゴリズム、③望ましいマッチング方法の公理的特徴づけ、といった問題について分析します。 3.格差の評価方法と望ましい社会保障政策について: 19世紀以降の所得と資産の分布を調べた諸研究によれば、資本主義社会のもとでは格差が拡大する傾向にあることが指摘されています。本課題では、①人々の生活状況の格差をどのように計測するのが望ましいのか、②格差を適切に縮小するには、どのような社会保障政策が望ましいのか、といった問題を数理的に分析します。 目的 Objectives
前述の3つの問題を数理的に分析することで、①経済・社会現象の問題への理解を深めること、②数学は自然現象のみならず、経済・社会現象を理解する上でも強力な分析道具になることを理解すること、の2点を本講義の目的とします。
なお、本講義は、教養教育の編成方針に定める (1)自然・人間・社会を幅広く俯瞰できる能力、(2)論理的・批判的思考力、(3)コミュニケーション能力、(4)国際性(異文化・異言語・異民族・国際問題の理解力)、を涵養するための科目です。 到達目標 Outcomes
授業の到達目標は以下の3つのものになります。
1.社会的意思決定の方法にまつわる諸問題を理解し、代表的な社会的意思決定の方法の長所と短所を説明できる。 2.望ましいマッチングの方法とその性質について理解し、解を計算できる。 3.社会保障政策がもたらす諸問題を理解した上で、望ましい所得・資産の分配のあり方について自分の考えを説明できる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
1.履修者の定員を20名前後とします。履修希望者が多い場合には、履修者の選抜を行います。選抜を行う場合、初回の授業でレポートを作成・提出してもらい、そのレポートをもとに履修者を選抜します。選抜に落ちた学生の単位認定はできません。なお、選抜方法の詳細については4月中にCLASSおよび講義棟一階の掲示板にて告知する予定なので、履修希望者は必ず掲示を確認し、必要な手続きを取るようにしてください。
2.履修選抜を行わない場合であっても、初回の授業では講義で扱う研究テーマや授業の進め方について説明するので、履修希望者はできるかぎり初回の授業に出席してください。 3.他の履修抽選科目に落選した上で、本講義の履修を希望する学生は、3回目の授業に必ず出席し、担当の講師に履修可能であるか確認するようにしてください。 4.履修選抜を行った結果、履修登録を認められた学生は、途中で履修登録を取り消すことが認められません。責任をもって履修登録するようにしてください。 5.積極的な発言を意識して授業に参加してください。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/ディベート・ディスカッション Debate/Discussion/グループワーク Group work/プレゼンテーション Presentation
-
準備学習・復習 Preparation and review
1.発表の準備および前回の発表の反省点のまとめを行うことが求められます。
2.各回の授業後に、グループごとに小レポートを提出してください。 成績評価方法 Performance grading policy
平常点(講義での発言、発表内容等)50%、レポート50%で評価します。
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
教科書はありません。参考文献リストはLETUSで配布します。また、以下の書籍が参考になるので、関心のある人は図書館で借りてください。
1.アマルティア・セン(2000)『集合的選択と社会的厚生』,勁草書房. 2.坂井豊貴,藤中裕二,若山琢磨(2008)『メカニズムデザイン:資源配分制度の設計とインセンティブ』,ミネルヴァ書房. 3.岡田章(2011)『ゲーム理論 新版』,有斐閣. 4.坂井豊貴(2010)『マーケットデザイン入門:オークションとマッチングの経済学』,ミネルヴァ書房. 5.トマ・ピケティ(2014)『21世紀の資本』,みすず書房. 授業計画 Class plan
1. オリエンテーション
参加者全員で話し合い、各参加者の研究テーマを決定する。 2〜12. 研究テーマについての調査・研究・発表 参加者が自分で調査した内容を発表し、それを基に参加者全員でディスカッションを行う。質疑応答を活発に行うことで研究内容への理解を深める。 13〜15. 研究テーマのまとめ これまでに報告してきた研究内容をまとめ、よりよい期末レポートを作成するための足掛かりとする。 ※参考までに、これまでの受講生のレポート課題の例を挙げておきます。どれも非常に面白い研究テーマばかりで、学科によっては卒論・修論・博論の立派な研究対象になるものです。 ・論理的に性能のよい社会的意思決定のルールを作ることの不可能性について(アローの不可能性定理) ・多数決における循環と票割れ(多数派が望まない候補者が勝ってしまうという逆説的な現象)の問題を解決するための社会的意思決定の方法について(ケメニー=ヤングの最尤法、ボルダ投票) ・社会的意思決定における戦略的な虚偽表明の問題について(ギバード=サタースウェイトの定理) ・選好の単峰性と中位ルール、熟議の役割について ・人々が社会的に望ましい結果を自発的に選択するような制度構築の可能性について(マスキンの定理) ・公共財供給におけるフリーライダーの問題を解決する方法について(ハーヴィッツの定理、クラーク=グローブス・メカニズム、その他実験経済学の分析) ・さまざまなオークション制度の性能の違いと上手なオークション制度の設計・利用方法について ・腎臓移植におけるドナーと患者のマッチング、研修医と研修先の病院のマッチング、入学希望者と公立学校のマッチング問題について ・論理的に性能のよい不平等尺度の作り方について ・貧困、所得・資産格差の歴史的推移とその要因について ・貧困問題に対する費用対効果の高い介入策について 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
なし
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

