シラバス情報
|
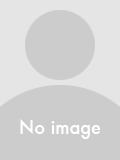
教員名 : 池口 徹
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
コンピュータサイエンス序論(計算機工学)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Introduction to Computer Science
授業コード Class code
994617G
科目番号 Course number
46CSARO101
教員名
池口 徹
Instructor
Dr. Tohru Ikeguchi, Professor
開講年度学期
2025年度前期
Year
2025年度
Semester
①First semester
曜日時限
水曜5限
Class hours
5th period on Wednesday
開講学科・専攻 Department
工学部 情報工学科
Department of Information and Computer Technology, Faculty of Engineering 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
情報工学において重要な内容は多種多様であるが、これらの中でも特に重要な
(1) コンピュータとその歴史 (2) 計算とは何か (3) 情報セキュリティ (4) コンピュータサイエンスに関する最新の話題 について基本的な内容を講義する。 目的 Objectives
情報工学においてコア技術となる (1) コンピュータの内部構造、 (2)計算とは何か、(3) 情報セキュリティの基本的な原理とその周辺の話題、(4) コンピュータサイエンスに関する話題について学ぶことで、情報工学の幅広い分野を学ぶための素養を身につけることが目的である。
本学科のディプロマ・ポリシーに定める「情報⼯学に必要な基礎学⼒と専⾨知識」を⾝に付けるための科⽬である。 到達目標 Outcomes
情報工学科の学生として、 (1) コンピュータの内部構造、(2) ネットワークの仕組み、(3) 計算とは何か、(4) 情報セキュリティの基礎について容易に説明できるようになることを到達目標とする。
卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
特にないが、大学生らしい積極的な履修を期待する。
アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay
-
準備学習・復習 Preparation and review
大学の講義では予習よりも復習が重要である。授業後に講義内容の復習を十分にしておくこと。 その際、参考書にリストアップした書籍を適宜読むなどして知識の定着を心がけよう。
成績評価方法 Performance grading policy
最終評価は、数回の宿題、最終試験により総合的に評価する。最終試験では、A4サイズ1枚の手書きメモの持ち込みを可とする。ただし、毎回の授業参加度も考慮する。評価の詳細は、第1回目の講義時に改めて説明する。
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
特に指定しないが、以下を参考書としてあげる。 また、講義においては必要に応じてプリント等を配布する。
・矢沢久雄著,日経ソフトウエア監修: コンピュータはなぜ動くのか, 日経BP社, 2003年1版1刷,2014年. ・矢沢久雄著,日経ソフトウエア監修: プログラムはなぜ動くのか, 日経BP社, 2007年2版1刷,2015年2版. ・戸根勤著,日経NETWORK監修: ネットワークはなぜつながるのか, 日経BP社, 2007年2版1刷,2015年2版. ・渡辺治著,今度こそわかるP≠NP予想,講談社,2014年1刷, 2015年. ・サイモン・シン著,青木薫訳: 暗号解読ーロゼッタストーンから量子暗号までー,新潮社,2001年1版1刷,2010年. ・結城浩: 暗号技術入門第3版, SBクリエイティブ, 2015年初版. ・今井秀樹監修, 伊豆哲也, 岩田晢, 佐藤証, 田中実, 花岡悟一郎著: トコトンやさしい暗号の本, 日韓工業新聞社, 2010年. ・矢野啓介, プログラマのための文字コード技術入門, 技術評論社, 2010年1版1刷, 2015年. ・深沢千尋, 改訂第2版 文字コードの超研究, 株式会社ラトルズ, 2011年2版. ・半谷精一郎, 見山友裕, 長谷川幹雄, コンピュータ概論, コロナ社, 2008年1刷, 2014年. ・稲垣耕作, 理工系のコンピュータ基礎学, コロナ社, 2006年1刷, 2014年. ・白鳥則郎監修, コンピュータ概論, 共立出版, 2013年1刷, 2014年. ・岡本龍明, 山本博資, 現代暗号, 産業図書, 1997年1刷, 2000年. ・甘利俊一,めくるめく数理の世界,情報幾何学,人工知能,神経回路網理論,サイエンス社,2024年. ・今井むつみ,秋田喜美,言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか (中公新書 2756),中央公論社,2023. ・今井むつみ,AIにはない「思考力」の身につけ方——ことばの学びはなぜ大切なのか? (ちくまQブックス),筑摩書房,2024. 授業計画 Class plan
(第01回目): ガイダンス,講義の進め方、講義概要
本講義の内容について概要を説明します。 参考書等について、講義の内容について 評価方法などについても説明します。 (第02回目): コンピュータの歴史 コンピュータの発達の歴史 コンピュータの現状 (第03回目): コンピュータを支える技術 ハードウエア ネットワーク Operating System ソフトウエア (第04回目): 計算とは何か (1) そもそも計算とは何かを考える アルゴリズム ハノイの塔 アルゴリズムと計算量 (第05回目): 計算とは何か (2) ナップザック問題 巡回セールスマン問題 多項式時間 指数関数時間 (第06回目): 計算とは何か (3) 易しい問題と難しい問題 多項式時間 P vs NP (第07回目): セキュリティ(1) コンピュータにおけるセキュリティ 暗号理論入門 暗号の歴史 (第08回目): セキュリティ(2) 対称暗号 XOR 使い捨てパッド 非対称暗号(公開鍵暗号)の考え方 (第09回目): セキュリティ(3) mod 演算 Deffie-Hellman 鍵共有の仕組み RSA暗号の仕組み (第10回目): セキュリティ(4) Elgamal 暗号の仕組み 楕円曲線暗号 一方向ハッシュ関数 メッセージ認証コード ディジタル署名 (第11回目): セキュリティ(5) 楕円曲線暗号 一方向ハッシュ関数 メッセージ認証コード ディジタル署名 暗号理論とその周辺分野に関する話題 (第12回目): コンピュータサイエンスとその周辺分野の話題 (1) 脳神経科学と人工知能 (第13回目): コンピュータサイエンスとその周辺分野の話題 (2) 人工知能とフレーム問題 人工知能と記号接地問題 (第14回目): まとめ この講義のまとめ (第15回目): 到達度評価 到達度評価試験 解説 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
可能であれば、量子計算の理論についても触れたいと考えている。
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

