シラバス情報
|
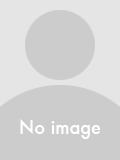
教員名 : 内呂 拓実
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
有機化学1及び演習
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Organic Chemistry and Practice 1
授業コード Class code
993M007
科目番号 Course number
3bBPCHP102
教員名
森田 瞬也、内呂 拓実
Instructor
Prof. Hiromi Uchiro
開講年度学期
2025年度前期
Year
2025年度
Semester
①First semester
曜日時限
火曜1限、金曜2限
Class hours
Tuesday/1st Period
Friday/2nd Period 開講学科・専攻 Department
薬学部 生命創薬科学科
Department of Medicinal and Life Sciences, Faculty of Pharmaceutical Sciences 単位数 Course credit
3.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
基本的な有機化合物の構造と性質、反応および合成について学習する。特に構造と性質については、それらを決定付けている様々な要因について学ぶことを通じて、本質的な理解を得ることを目指す。反応については、それに伴う電子の移動に関する基礎的な知識を身につける。合成については、目的とするものだけを作る際に重要となる選択性の概念を養う。
目的 Objectives
薬学における有機化学の必要性について述べ、有機化合物の構造と性質に加えて、反応や合成について知ることを通じて、これらを理解する上で重要な法則を学ぶことを目的とする。
到達目標 Outcomes
薬の創製や代謝などを有機化学の視点から理解するための基礎的な知識を習得することを目標とする。
卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
・計31回の講義のうち、演習(小テストと解説)を6回実施する。
・第29回の講義は補講として実施する。 ・上記の補講実施日は7月22日(火)の授業予備日を予定しており、実施教室等の詳細は別途LETUSおよびCLASSの掲示等で連絡する。 ・演習の日程については、別途LETUSおよびCLASSの掲示等で連絡する。 ・演習において実施する小テストの点数は成績に反映されるので、必ず出席して受験すること。 ・特別な事情(不慮の怪我や入院など)のある場合を除き、全講義回数の3分の2以上に出席していない場合には単位を与えない。 ・特別な事情などにより演習に出席できなかった場合には、欠席した回を除く他の小テストにおける成績を考慮して評価する。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
小テストの実施 Quiz type test
-
準備学習・復習 Preparation and review
・有機化学は薬学の要である。学修簿に記載のある学修時間を満たすように予習・復習をしっかりと行い、基礎学力を身に付けるよう努めること。
・講義の中で取り扱った有機化合物の模型を組み立てることにより、分子の三次元的な構造(立体構造)を理解するように努めること。 ・(授業外学習の指示)教科書の当該部分を必ず読んでから講義に臨み、講義後は教科書の問題を解くことなどを通じて講義内容の復習を行うこと。 成績評価方法 Performance grading policy
学期末に実施する到達度試験(期末試験)の点数(70%)と演習において実施する小テストの点数(30%)の合計から総合的に評価する。
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
Y
書誌情報 Bibliographic information
マクマリー「有機化学 第9版(上)」(東京化学同人)ISBN978-4-8079-0912-4
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
日本薬学会編「スタンダード薬学シリーズⅡ3/化学系薬学/I.化学物質の性質と反応」(東京化学同人)
日本薬学会編「スタンダード薬学シリーズ3/化学系薬学/II.ターゲット分子の合成と生体分子・医薬品の化学」(東京化学同人) マクマリー「有機化学概説 第8版」(東京化学同人) 授業計画 Class plan
第1回 薬学と有機化学 【講義】
<講義内容と到達目標> ・医薬品の創出において有機化学が果たしてきた役割とその重要性について説明できる。(SBOs:*) ・基本的な有機化合物の構造式を書くことができる。(SBOs:Pre(5)②5) ・基本的な有機化合物の分子模型を組み(授業外学習の指示)特に立てることができる。(SBOs:AdvC3②1) 第2回 分子の構造と化学結合(1)-化学結合- 【講義】 <講義内容と到達目標> ・原子,分子,イオンの基本的構造について説明できる。(SBOs:Pre(5)①1) ・原子の電子配置について説明できる。(SBOs:Pre(5)①3) ・周期表に基づいて原子の諸性質(イオン化エネルギー,電気陰性度など)を説明できる。(SBOs:Pre(5)①4) ・原子軌道の種類と形状について説明できる。(リSBOs:C1(1)①2) ・化学結合の種類とそれぞれの特徴について説明できる。(SBOs:Pre(5)②1, C1(1)①1) 第3回 分子の構造と化学結合(2)-混成軌道- 【講義】 <講義内容と到達目標> ・混成軌道について説明できる。(SBOs:C1(1)①2) 第4回 分子の構造と化学結合(3)-Lewis構造式と共鳴- 【講義】 <講義内容と到達目標> ・分子の極性について概説できる。(SBOs:Pre(5)②2) ・Lewis構造式を用いて化合物を表すことができる。(SBOs:C3(1)①3) ・電子不足もしくは電子過剰の化学種のLewis構造式中に形式電荷を正しく割り当てることができる。(SBOs:C3(1)①3) ・共鳴のもつ意味について説明できる。(SBOs:C1(1)①3) ・共鳴関係にある複数の化学種の極限構造式を書き、これらを含む共鳴構造式を示すことができる。(SBOs:C3(1)①4) 第5回 <演習(小テスト)1> 分子の構造と化学結合 【演習】 <講義内容と到達目標> ・「分子の構造と化学結合(化学結合、混成軌道、Lewis構造式と共鳴、酸と塩基)」に関する問題を解くことにより、自己の理解度を確認する。(SBOs:第1回〜第6回の講義を参照) ・上記の問題に関する解答・解説を聞くことにより、さらに理解度を高める。 第6回 官能基とその性質(1)-酸と塩基- 【講義】 <講義内容と到達目標> ・酸と塩基の基本的な性質および強弱の指標を説明できる。(SBOs:Pre(5)③4) ・酸・塩基平衡の概念について説明できる。(SBOs:C2(2)①1) ・pHおよび解離定数について説明できる。(知識・技能)(SBOs:C2(2)①2) ・酸および塩基を正しく定義し、その強さを比較することができる。(SBOs:C3(1)①) ・有機化合物が酸もしくは塩基として働く場合の構造的な特徴を説明することができる。(SBOs:*) 第7回 官能基とその性質(2)-官能基- 【講義】 <講義内容と到達目標> ・代表的な化合物の名称と構造を列挙できる。(SBOs:Pre(5)②5) ・有機化合物中に含まれる官能基について、その名称を列挙することができる。(SBOs:C3(3)①1) ・薬学領域で用いられる代表的な化合物を慣用名で記述できる。(SBOs:C3(1)①2) ・有機化合物中に含まれる官能基について、その性質や電子効果を説明することができる。(SBOs:C3(3)⑥1) 第8回 アルカンとその立体化学(1) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・代表的な化合物の名称と構造を列挙できる。(SBOs:Pre(5)②5, C3(1)①2) ・アルカンの各種異性体について説明できる。(SBOs:C3(2)①2) ・IUPAC法を用いてアルカンを命名できる。(SBOs:C3(1)①1) 第9回 アルカンとその立体化学(2) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・アルカンの性質について説明できる。(SBOs)C3(2)①1 ・アルカンの立体配座をNewman投影式を用いて表すことができる。(SBOs)C3(1)②7 ・アルカン(エタン、ブタン)の立体配座とその安定性の違いについて説明できる。(SBOs)C3(1)②8 第10回 <演習(小テスト)2> 官能基とその性質、アルカンとその立体化学 【演習】 <講義内容と到達目標> ・「官能基とその性質」および「アルカンとその立体化学」に関する問題を解くことにより、自己の理解度を確認する。(薬改コアカリSBOs:第8回〜第9回の講義を参照) ・上記の問題に関する解答・解説を聞くことにより、さらに理解度を高める。 第11回 シクロアルカンとその立体化学(1) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・IUPAC法を用いてシクロアルカンを命名できる。(SBOs:C3(1)①1) ・シクロアルカンのシス-トランス異性体について説明できる。(SBOs:C3(1)②1) ・シクロアルカンの環のひずみとそれを決定する要因について説明できる。(SBOs:C3(2)①3) 第12回 シクロアルカンとその立体化学(2) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・シクロアルカンの安定な立体配座とそれを決定する要因について説明できる。(SBOs:*) 第13回 シクロアルカンとその立体化学(3) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・シクロヘキサンのいす形配座における水素の結合方向(アキシアル,エクアトリアル)を図示できる。(技能)(SBOs:C3(2)①4) ・置換シクロヘキサンの安定な立体配座とそれを決定する要因について説明できる。(SBOs:C3(2)①5) 第14回 <演習(小テスト)3> シクロアルカンとその立体化学 【演習】 <講義内容と到達目標> ・「シクロアルカンとその立体化学」に関する問題を解くことにより、自己の理解度を確認する。(SBOs:第11回〜第13回の講義を参照) ・上記の問題に関する解答・解説を聞くことにより、さらに理解度を高める。 第15回 有機反応(1) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・有機化学反応の種類(置換,付加,脱離,転位)の特徴を理解して分類し、それぞれの機構の違いについて説明できる。(SBOs:C3(1)①6) ・代表的な有機反応の機構を電子の動きを表す矢印を用いて示すことができる。(SBOs:C3(1)①9) ・ラジカル反応の各段階について説明できる。(SBOs:C3(1)①7) 第16回 有機反応(2) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・極性反応における反応中間体について説明できる。(SBOs:C3(1)①7) ・反応の進行についてエネルギー図を用いて説明できる。(SBOs:C3(1)①8) 第17回 有機反応(3) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・代表的な化学変化に伴う熱力学量(エンタルピー変化,エントロピー変化,ギブズエネルギー変化など)を説明し,求めることができる。(技能)(SBOs:AdvC1①1) ・反応速度を決定する要因を列挙できる。(SBOs:C1(3)①1, C1(3)①6, C1(3)①7) ・生体内で進行する代表的な化学反応の特徴について説明できる。(SBOs:*) 第18回 アルケン(1) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・IUPAC法を用いてアルケンを命名できる。(SBOs:C3(1)①1) ・アルケンをはじめとする有機化合物の不飽和度について説明できる。(SBOs:*) ・アルケンの代表的な合成法を説明できる。(SBOs:AdvC3⑪1) 第19回 アルケン(2) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・アルケンの立体異性(cis, trans異性およびE, Z異性)について説明できる。(SBOs:C3(1)②6, C3(1)②1) ・IUPAC法を用いてアルケンの各立体異性体にE,Zの符号をつけて命名できる。(SBOs:C3(1)①1) ・アルケンの各立体異性体の安定性の違いについて説明できる。(SBOs:*) 第20回 <演習(小テスト)4> 有機反応とアルケン 【演習】 <講義内容と到達目標> ・「アルケンの化学(命名法、性質、合成)」に関する問題を解くことにより、自己の理解度を確認する。(SBOs:第15回〜第19回の講義を参照) ・上記の問題に関する解答・解説を聞くことにより、さらに理解度を高める。 第21回 アルケンの反応(1) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・アルケンの求電子付加反応(ハロゲンの付加、ハロゲン化水素の付加、水の付加)を列挙できる。(SBOs:C3(2)②1) ・アルケンの求電子付加反応(ハロゲンの付加、ハロゲン化水素の付加、水の付加)の機構を電子の動きを表す矢印を用いて説明できる。(SBOs:C3(1)①9) 第22回 アルケンの反応(2) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・アルケンの求電子付加反応について、反応中間体および生成物の安定性をエネルギー図を用いて説明できる。(SBOs:C3(1)①8) ・Markovnikov則について説明できる。(SBOs:AdvC3⑬1) ・Hammondの仮説について説明できる。(SBOs:*) ・カルボカチオンの転位反応とそれが進行する理由について説明できる。(SBOs:AdvC3①2) 第23回 アルケンの反応(3) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・アルケンのヒドロホウ素化-酸化反応について説明できる。(SBOs:C3(2)②1, C3(2)②2) ・アルケンの水素添加反応について説明できる。(SBOs:C3(2)②1, C3(2)②2) ・アルケンのジヒドロキル化反応について説明できる。(SBOs:C3(2)②2) ・アルケンの酸化開裂反応について説明できる。(SBOs:C3(2)②2) 第24回 アルキン(1) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・IUPAC法を用いてアルキンを命名できる。(SBOs:C3(1)①1) ・アルキンの代表的な合成法について説明できる。(SBOs:AdvC3⑪2) ・アルキンの付加反応について説明できる。(SBOs:C3(2)②3) 第25回 アルキン(2) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・アセチリドの生成とそれを用いた合成反応について説明できる。(SBOs:C3(2)②3) ・アセチレンを出発物質として用い、増炭反応および官能基変換を経て目的物に至る合成経路を立案できる。(SBOs:AdvC3⑭1, AdvC3⑪11) 第26回 <演習(小テスト)5> アルケンの反応、アルキン 【演習】 <講義内容と到達目標> ・「アルケンの反応」、「アルキン」に関する問題を解くことにより、自己の理解度を確認する。(SBOs:第21回〜第25回の講義を参照) ・上記の問題に関する解答・解説を聞くことにより、さらに理解度を高める。 第27回 立体化学(1) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・キラル、アキラルの概念を説明できる。(SBOs:C3(1)②2) ・光学活性について説明できる。(SBOs: C3(1)②2) ・エナンチオマーについて説明できる。(SBOs:C3(1)②3) ・旋光性と立体化学および光学活性の関係を説明できる。(SBOs:AdvC3⑨2) ・比旋光度の算出法について説明できる。(SBOs:AdvC3⑨1) 第28回 立体化学(2) 【講義】 <講義内容と到達目標> ・不斉炭素原子の絶対配置をR,S順位則を用いて表すことができる。(SBOs:C3(1)②5) ・ラセミ体について説明できる。(SBOs:C3(1)②4) ・Fischer 投影式とNewman 投影式を用いて有機化合物の構造を書くことができる。(SBOs:C3(1)②7) 第29回 立体化学(3) 【講義】(補講) <講義内容と到達目標> ・ジアステレオマーについて説明できる。(SBOs:C3(1)②3) ・メソ体について説明できる。(SBOs:C3(1)②4) ・反応機構と立体化学の関係について説明できる。(SBOs:AdvC3⑬2) ・代表的な光学異性体の入手法を列挙できる。(SBOs:AdvC3⑬4) 第30回 <演習(小テスト)6> 立体化学 【演習】 <講義内容と到達目標> 「立体化学」に関する問題を解くことにより、自己の理解度を確認する。(SBOs:第27回〜第29回の講義を参照) ・上記の問題に関する解答・解説を聞くことにより、さらに理解度を高める。 第31回 到達度評価のための試験 【試験】 期末試験を通じて本科目全体の到達度を評価する。 SBOsコード(薬学部薬学科のみ 2023年度以前カリキュラム適用者対象)
学修事項(薬学部薬学科のみ 2024年度以降カリキュラム適用者対象)
担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
内呂 拓実
製薬企業において8年間創薬研究(探索・プロセス開発)に従事した経験を活かして、薬学における有機化学の重要性に配慮した講義を実施する 教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
薬学教育モデル・コアカリキュラム(平成25年度改訂版)に対応する項目(SBOs)及び薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)に対応する項目(学修事項)を授業計画欄下部に示す。
なお、各項目に紐づく内容については、以下URL先に示す。 URL:https://tus.box.com/s/ilc2p0ygiyz4ncj23ckp310rmaa0efdk 授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

