シラバス情報
|
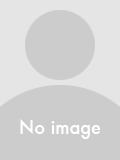
教員名 : 佐竹 彰治
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
有機化学1−2
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Organic Chemistry (1-2)
授業コード Class code
992343B
科目番号 Course number
23CHORC202
教員名
佐竹 彰治
Instructor
Akiharu SATAKE
開講年度学期
2025年度後期
Year
2025年度
Semester
②Second semester
曜日時限
金曜6限
Class hours
Friday 6th Period
開講学科・専攻 Department
理学部第二部 化学科
Department of Chemistry, Faculty of Science Division Ⅱ 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
本授業では有機化学を学ぶ。
有機化学は有機化合物を基盤とする様々な科学技術(例えば医薬品、農薬、食品、生命化学、化成品、合成高分子化学、機能性材料化学など)を支える非常に重要な学問であり、将来この分野に進もうとする学生諸君にとっては必要不可欠である。 目的 Objectives
有機化学1−1に引き続き本教科は、様々な官能基を有する有機化合物の性質や反応性、反応機構、合成法、スペクトルによる構造解析などについて学び、有機化学の基礎的知識を確実なものとすることを目的とする。
到達目標 Outcomes
本講義では、有機化学反応における実験事実とその論理的説明を総合的に学習することを目標とする。また、これまでに学習した有機化学反応を組み合わせることによって分子をつくるテクノロジーである有機合成化学を学ぶ。また、有機化合物の構造決定法についてさらに理解を深め、3年次に履修する有機化学実験に必要な実験的に生成した化合物を同定できるように訓練を行う。
具体的には、①イオン的な反応において電子の動きを曲がった矢印(巻矢印)を用いて的確に記述することができる、②多段階の反応を用いて指定された原料から指定された目的物を合成する手法を提案することができる、③各種機器分析データから測定された化合物の構造を明らかにすることができる. 以上を目標とする。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
基礎有機化学と有機化学1−1の内容をしっかり習得していること。
アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
小テストの実施 Quiz type test/反転授業 Flipped classroom
-
準備学習・復習 Preparation and review
本授業は、下記に示す「1.予習」「2.授業受講」「3.復習」の継続的な取り組みが極めて重要である。
また理解度を確認するために、授業内レポートを複数回実施する。またLETUSを通じて「レポート課題」を課すこともある。期限までに必ず提出すること。 「1.予習」 授業で取り上げる内容についてはあらかじめLETUSで公開する。この内容は問題形式になっており、内容について授業前に確認し、何を学ぶかを明確にしてから授業に臨むこと。事前に可能な限り問題に取り組んでおくことが望ましい。 また予習のためのQuizがLETUS上にアップされている場合には受講前に必ず取り組み、授業に出てくる用語等について事前に確認しておくこと。 本科目専用のノートを用意し、予習した内容は専用のノートにまとめて授業の際に持参すること。 「2.授業受講」 授業中は「自らが考えること」と「考えたことを記述する」ことを重要視するため、それに必要な時間を与える。教員がその場で課題を出し、受講生に「1分程度時間を与える。」と宣言したら、集中してその課題に取り組むこと。 この授業形式は受講生本人が自身の理解度を的確に認識できるため、学習を進めるために極めて有効である。この授業形式を理解し、授業中は考えることに集中すること。 「3.復習」 授業後に、問題形式で公開された授業内容について記述回答できるように復習すること。 15回の授業は関連付けられているため、前回までの授業内容が理解できていないと次の授業についてゆけなくなる。必ず復習を行い、前回までの内容を理解しておくこと。 教科書としては従来より採用しているJ.McMurry著(伊東ら訳)『マクマリー有機化学』(第9版)上・中・下(東京化学同人)のうち、特に上中巻を用いる。また、副教科書として『ウォーレン有機化学』第2版 上・下(東京化学同人)を使用する。授業資料中にウォーレン有機化学の関連する箇所を示すので、授業受講後の復習の際に参照すると効果的である。ウォーレン有機化学は「なぜ?」に答える教科書なので、マクマリー有機化学と組み合わせることで、さらに詳しく知りたい学生諸君にとってはより理解が進むと考えている。 成績評価方法 Performance grading policy
定期試験 60〜50%
授業内レポート・LETUS上の小テスト・課題 40〜50% 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
Y
書誌情報 Bibliographic information
マクマリー有機化学(上)第9版、J. McMurry 著、伊東 椒、児玉 三明、荻野 敏夫、深澤 義正、通 元夫 訳、東京化学同人、2017、ISBN: 9784807909124
マクマリー有機化学(中)第9版、J. McMurry 著、伊東 椒、児玉 三明、荻野 敏夫、深澤 義正、通 元夫 訳、東京化学同人、2017、ISBN: 9784807909131 マクマリー有機化学(下)第9版、J. McMurry 著、伊東 椒、児玉 三明、荻野 敏夫、深澤 義正、通 元夫 訳、東京化学同人、2017、ISBN: 9784807909148 ウォーレン 有機化学 上 第2版、J. Clayden、N. Greeves、S.Warren 著、野依 良治、奥山 格、柴崎 正勝、檜山 爲次郎 監訳、東京化学同人、2015、ISBN: 9784807908714 ウォーレン 有機化学 下 第2版、J. Clayden、N. Greeves、S.Warren 著、野依 良治、奥山 格、柴崎 正勝、檜山 爲次郎 監訳、東京化学同人、2015、ISBN: 9784807908721 MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
最新有機合成法(第2版)設計と戦略 G.S.Zweifel 著 M.H.Nantz 著 Peter Somfai 著 檜山 爲次郎 訳
化学同人 2018 ISBN 9784759819618 有機スペクトル解析入門 横山 泰 著, 石原 晋次 著, 生方 俊 著, 川村 出 著 東京化学同人 ISBN 9784807909735, 出版日 2022/02/15 有機化合物のスペクトルによる同定法(第8版) R. M. Silverstein ・F. X. Webster ・D. J. Kiemle ・D.L.Bryce 著 岩澤 伸治 ・豊田 真司 ・村田 滋 訳,東京化学同人 ISBN 9784807909162, 出版日 2016/12/08 有機化学のためのスペクトル解析法 第3版 化学同人 UV,IR,NMR,MSの解説と演習, S. Bienz, L. Bigler, ISBN 9784759823493, 出版日 2024/5/10 他の参考書については授業内で適宜お伝えします。 授業計画 Class plan
全ての授業を対面で受講することを求める
1 ガイダンス 「有機化学を系統的に学ぶ上でのポイント」を聞き、学習の取り組み方について理解することができる。 命名法:アルカン、アルケン、アルキン、ハロゲン化アルキル、アルコールの命名法について説明できる アルコールの酸性度pKaについて、立体効果、誘起効果、共鳴効果の観点から説明できる 2 アルコールの合成: アルケンからの合成,カルボニル化合物の還元・グリニヤール試薬との反応などについて説明できる アルコールの反応:ハロゲン化アルキルへの反応、トシラートへの変換などについて説明できる 3 アルコールの反応: アルコールの脱水、酸化,保護基などについて説明できる 4フェノールの合成・酸化反応について説明できる アルコールとフェノールの分光学:NMRやIRスペクトルについて解析することができる。 アルコールの合成・反応の復習:多段階有機合成反応の問題を解くことができる。 5 エーテル:エーテルの構造と性質,エーテルの合成反応について説明できる エーテルの反応続き:Claisen転位(ペリ環状反応の1つ)について説明できる. エポキシ化合物の合成と反応について説明できる. 6クラウンエーテルについて説明することができる. チオールとスルフィド、スルホキシド、スルホンの構造を説明できる. 7 命名法:有機化合物の命名を行うことができる.アルデヒド、ケトンの命名ができる. アルデヒドの製法:アルコールの酸化、カルボン酸誘導体の還元について説明できる ケトンの製法:アルケンのオゾン分解、酸クロリドとGilman試薬との反応、アルケンから1,2-ジオールを経る方法について説明できる. アルデヒドとケトンの求核付加反応:アミンとの反応によるイミンの生成、水との反応による1,1-diolの生成、 8 アルデヒドとケトンの求核付加反応の続き.HCNとの反応によるシアノヒドリンの生成、ヒドリド試薬やGrignard試薬との反応について説明できる. カルボニル化合物の種類や反応性(概論) カルボニル化合物の種類や反応性について概論を説明できる 9 アルデヒドとケトンの反応における反応機構を曲がった矢印で説明できる:アミンとの反応によるイミン・エナミンの生成、Wolff-Kishner還元、1,2-diolとの反応によるアセタールの生成、1,2-エタンジチオールとの反応によるチオアセタールの生成、環状ヘミアセタールの生成 ケトンアルデヒドの保護基を用いた有機合成について考えることができる. Wittig反応について説明できる α,β-不飽和アルデヒド・ケトンに対する共役付加について説明できる. 求核剤の硬さと軟らかさについて説明できる. 10 アルデヒドとケトンのまとめと分光学:7〜10回目の内容を説明することができる.アルデヒドとケトンのNMRやIRスペクトルについて解析することができる. 11 カルボン酸とニトリル: (命名法)有機化合物の命名ができる.カルボン酸とニトリル類の命名ができる. カルボニル化合物・ニトリルの赤外分光(IR)スペクトルについて解析することができる. 12 カルボン酸を含む有機化合物の酸性度pKaについて、立体効果、誘起効果、共鳴効果の観点から説明できる. 13 酸性度pKaの違いを利用した化合物の分液操作による分離について説明できる. カルボン酸の合成: 下記のカルボン酸合成法について説明できる. Grignard試薬とドライアイス(CO2)を用いる合成.メタノールから酢酸を合成するMonsanto法(ロジウム触媒).遷移金属錯体を用いた有機合成の例について理解することができる. 14 カルボン酸の合成:酸化によるカルボン酸合成法について説明できる. ニトリルの合成と反応:アミドから塩化チオニルを用いてニトリルを合成する反応機構を説明できる.ニトリルの塩基による加水分解、およびニトリルの酸による加水分解の反応機構を説明できる.ハロゲン化アルキルからニトリルを経由して一炭素長いカルボン酸を合成する方法を説明できる. 以下のニトリルとの反応を説明できる: LiAlH4による還元。Grignard 試薬との反応によるケトンの生成.ハロゲン化アルキルから、炭素‐炭素結合を形成させながらケトンを合成する方法。 10〜13回のまとめを説明することができる. 15 到達度評価 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
Signals ChemDraw(旧ChemOffice Professional)/Discovery Studio, Materials Studio
-
備考 Remarks
(注意)
重要な連絡をLETUSを通じて行うので、毎週必ず確認すること。 オフィスアワー:火曜日、土曜日 14:00−16:00 授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
Y
|

