シラバス情報
|
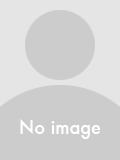
教員名 : 松田 学則
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
有機化学1B
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Organic Chemistry 1B
授業コード Class code
9916C36
科目番号 Course number
16CHORC102
教員名
松田 学則
Instructor
T. Matsuda
開講年度学期
2025年度後期
Year
2025年度
Semester
②Second semester
曜日時限
水曜2限
Class hours
Wed2
開講学科・専攻 Department
理学部第一部 応用化学科
Department of Applied Chemistry, Faculty of Science Division Ⅰ 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
⑧ [遠隔]オンライン授業(非同期)/ [Remote]Online (asynchronized remote)
概要 Description
有機化学を学ぶ上で重要な概念を理解する。アルキン、ハロゲン化アルキル、芳香族化合物の性質、合成法、反応および命名法について学ぶ。
目的 Objectives
「有機化学1A, 1B」では、必修科目「有機化学2」、「有機化学3」を履修するにあたり前提となる、有機化合物の構造の書き方、命名法、合成法、および反応に関する知識を習得することを目的としている。
到達目標 Outcomes
・アルキンの様々な反応を理解し、生成物の構造を正しく書けるようになる。
・簡単な有機分子について、合成経路が与えられるようになる。 ・有機ハロゲン化物の合成法、反応が理解できるようになる。 ・求核置換(SN1/SN2)、脱離(E1/E2)反応の特性を理解できるようになる。 ・基質、反応剤、溶媒の組み合わせから、起こる反応(SN1/SN2/E1/E2)が予測できるようになる。 ・求核置換、脱離反応において重要なWalden反転、カルボカチオンの安定性、アンチペリプラナー配座、Zaitsev則を理解できるようになる。 ・芳香族化合物の命名ができるようになる。 ・ベンゼンの安定性、Hückel則が理解できるようになる。 ・芳香族求電子置換反応、およびその置換基効果について理解できるようになる。 ・その他芳香族化合物の反応を習得し、多置換ベンゼンの合成経路が与えられるようになる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
この講義はオンライン(非同期遠隔授業)で行われます(が、小テストの開始時刻は講義時間内)。
講義に関する資料はすべてLETUS(およびリンク先のBOX)上にあります。 資料:前日(火曜)の12:00に公開します。必要であれば印刷の上、講義に臨んでください。 講義:講義日(水曜)10:30に公開されます。MP4, PDF, MP3を用意してあります。各自の学習スタイルに合わせて活用してくだい。 毎回、教科書に沿った講義動画(またはPDFファイル)を見た上で、(あれば)演習問題、確認テスト、小テストに取り組んでください。また、講義終了後(12:00)に宿題が公開されますので期限までに解答してください。補充問題、発展問題にも積極的に取り組んでください。 確認テスト、小テスト、宿題、補充問題、発展問題、模擬試験問題、webテストは、LETUSの小テスト機能を使用します(一部PDFで提出する例外あり)。 2024年度は合計11,553件の小テスト受験がありました。 =C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C= [重要事項]必ずA4紙に印刷したものに手書きで解答し、スキャンによりPDFを作成し、BOXに提出する(ファイルリクエストを使用します)。その際、以下の3点に注意してください。 1.白黒/グレースケールではないファイル(減点処理):課題ファイルはスキャナ、もしくはスマートフォンのスキャナ機能を使ってグレースケール(推奨)もしくは白黒のPDFファイルを作成してください。慣れない場合は、カラープリンタ(コンビニにもある)で事前に確認することをお勧めします。文字が読み取れ、影や背景が印刷されず、茶色に見える線等が入っていなければ、まず大丈夫です。写真のPDF化[×20%]、かなりの部分の背景が印刷される[×50%]、色付きの線がある[×80%]。 2.ファイル名の不備(減点処理):有機化学1Bで提出する電子ファイルのファイル名は必ず16XXXXX.pdf(16XXXXX = 自分の学籍番号)にしてください。学籍番号から始まっているが、余計なスペース、文字がある[×80%]。学籍番号から始まっていないが含んでいる[×50%]。学籍番号を含んでいない[×20%]。 3.解像度が不十分、ページが足りない(複数ページPDFが作れていない)、前の課題、他の科目の課題(減点処理):再提出を指示します[×50%]。 毎学期、ファイルの不備で到達度評価(ペーパーテスト)が大幅な減点になる学生が数名います。 PC/ITスキルが不足しており、BOXへのPDFの提出が(上の要件を守れるか)不安な方のために、封筒への提出も可能です。5号館5階510のドアにある封筒に提出してください。 =C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C= 質問、間違いの指摘等は全てLETUSのQ&Aフォーラムを使用してください。ただし、個人的なことに関してはこの限りではありません(本人からによる大学発行のメールアドレスのみ)。返信がない場合は、以下の理由が考えられます。 ・Q&Aフォーラムで問い合わせるべき内容 ・問い合わせ先が不適切(理学事務課へ) ・答える内容ではない(学修簿、履修の手引き等に書かれている) 講義資料に間違いを見つけた場合は、Q&Aフォーラムで報告してください。第一報告者にボーナス点0.5~1点が与えられます(各人各回1点まで)。LETUSの小テスト内の間違いについても同様に第一報告者にボーナス点0~0.5点が与えられます。第15回講義の3日後あたりに学籍番号と獲得ボーナス点を公表しますので、間違いがないか確認してください(確認期間が短いので注意)。 確認テストは、講義日(水曜)の11:15~11:30の間(通常11:30)に公開されます。簡単な4問からなっています。何回でも受験できます。100点にすることで、同じ回の小テストを受験できるようになります。 小テストは、講義日(水曜)の11:15~11:30の間(通常11:30)に公開されます。同じ回の確認テストの点数が100点になっていることが受験条件です。第1回の受験可能期間は24時間30分ですが、回が進むにつれ受験可能期間は短くなっていき、第13回では1時間になります。点数には、受験開始時間、解答に要した時間も影響します(早く開始して短時間で回答するほど高得点になる仕組み)。正答は締め切り後に公開されます。 宿題は、講義日(水曜)の12:00に公開されます。全て解答してください。解答の正誤は点数に影響しませんが、各回、宿題点を取るための最低点が設定されています。ブランク解答(未解答)が1つでもあれば0点になります。点数は完了までの時間により異なります。 日曜0:00(土曜24:00)まで10点 月曜0:00(日曜24:00)まで9点 火曜0:00(月曜24:00)まで8点 水曜0:00(火曜24:00)まで7点 水曜10:30(締切)まで5点 補充問題は、講義日(水曜)の6:00に公開されます。受験可能期間に注意してください。合計点(最高点を使用)に応じて最大11点付与されます。また、補充問題点の獲得には、各回の平均点が30点以上であることが条件。正答は公開1週間後をめどに公開されます。 発展問題は、講義日(水曜)の6:00に公開されます。受験可能期間に注意してください。合計点(平均点を使用)に応じて最大3点付与されます。2回目以降の発展問題には、同じ回の補充問題、前回の発展問題の点数が一定以上あることが条件となっています。正答は公開2週間後をめどに公開されます。 補充問題・発展問題は受験可能期間が設定されていますので、必ず期限内に目的の点数まで到達してください。解答最終期限は、2025/01/14 0:00を予定しています。 第13回の講義終了時に模擬試験問題が公開されます。模擬試験問題をやらずにwebテストで高得点を取ることは不可能なので、繰り返し受験して、頭と体を問題形式に慣れさせること。模擬試験問題にも5点が配点されています。 到達度評価はwebテストとペーパーテストがあります。 webテストは、第14回(本試験)、第15回(追試験)に行われます。本試験をパスし、追試験のみを受験することは可能です。LETUSの小テスト機能を用います。それぞれ35分の前半(500点満点)・後半(500点満点)に分けて行われます(合計1000点満点)。1回のみの受験の場合は、その点数が100%使用されます。2回受験した場合は、点数の高かったほうの2/3、低かったほうの1/3用いて点数とします。各回、受験の際は必ず前半・後半両方受験を完了させること。本試験、追試験どちらのwebテストも受験しなかった場合は、再試験の資格を失います。デバイス・通信環境に不備を理由とした受験取り消しはできません。本試験をパスし、追試験を受験する場合は、災害、病気、忌引き等を理由として受験できなくてもこれ以上の救済措置はありません。 ペーパーテストの問題は第13回の講義終了時に公表されます。PDFはBOXへ、A4紙に解答したものは封筒へ提出すること。webテストを受験していれば、ペーパーテスト未提出でも再試験の資格を失いません。 webテスト受験者で補正後の点数が60点に満たなかった者は再試験を受験することになります。再試験は、 (a) (補充問題の得点合計/(100 × 13))× 20 (b) (模擬試験問題の累積得点*/(500 × 2 × 20))× 20 *上限10000点 (c) (対面筆記式の再試験/100)× 60 (a)~(c)の合計で評価されます。補充問題点、模擬試験問題点が0点のままでは、対面筆記式の再試験で100点を取らないと合格できません(この制度の再試験で合格した人は過去いません)。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test/ディベート・ディスカッション Debate/Discussion
過去5年間のデータから、LETUSの小テストに取り組んだ時間と成績の間には大きな相関があることがわかっています。小テストはいずれも30分程度で完了させられるものがほとんどです。補充問題、模擬試験問題は、繰り返し受験して、点数を上げてください。
些細な疑問であっても放置せずに、Q&Aフォーラムで聞いてください。あなたが質問することによって、同様の疑問を抱えている人の役にも立ちます。 ペーパーテストは、問題から自分で作ることになりますので、正しく理解し、その知識が使えるものになっていることががとても重要になります。ユニークさ、オリジナリティあふれる解答で教員を驚かせてください。 準備学習・復習 Preparation and review
準備学習:教科書に目を通しておくこと。資料に目を通しておくこと。前回までの復習をやっておくこと。
復習:宿題をやること。LETUSにある問題で繰り返し学習すること。補充問題に取り組むこと(推奨)。 成績評価方法 Performance grading policy
成績は、
小テスト11点 宿題10点 補充問題11点 発展問題5点 模擬試験3点 webテスト48点 ペーパーテスト12点 ボーナス点の合計を、S評価とA評価の割合が50%程度に補正(平均点を約80点程度にかさ上げ)して決定します。 採点・集計完了後、個人成績表(希望者のみ)、成績講評を配布します。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
Y
書誌情報 Bibliographic information
マクマリー有機化学(上)第9版
マクマリー有機化学(中)第9版 MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
マクマリー有機化学問題の解き方第9版 英語版
授業計画 Class plan
この講義はオンライン(非同期遠隔授業)で行われます。
2008~2019年度の対面式と比較して、オンライン方式では、(1) 比較的速いタイミング(場合によっては即時)のフィードバックが可能になったこと、繰り返し(見返し)学習が容易になったことで勉強時間が増えた、(2) 習熟度に応じた対応が容易になったことで、(優秀な学生が)より高度な問題に取り組めるようになった、(3) 講義時間に拘束されることなく学生の旺盛な学習意欲に臨機応変に応えることが可能になった、(4) 厳密な機械採点になったことで、スペルミス等のエラーが格段に少なくなった、(5) 解答所要時間が点数に反映される設定のため、速く解答できるようになった、などの理由により、理解度が高まっています。 2022年度、2023年度に行ったアンケート結果(回答率80%)では、対面式との比較で、約2/3の学生が有機化学1Aおよび1Bの講義がオンラインで行われていることを支持していました(オンラインが向いていないという回答は約10%)。また、他の科目よりも多い時間勉強したという回答が70%でした。 =C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C=C= 教科書に沿った講義動画(またはPDFファイル)を見た上で、演習問題に取り組み、確認テスト、小テスト、宿題を期限内に完了してください。合わせて、補充問題、発展問題にも取り組んでください。 宿題は15回毎回、確認テスト、小テスト、補充問題は、講義1~13回の毎回あります。発展問題は、4回に設けられています。 非同期遠隔授業ですが、確認テストおよび小テストの開始時間は講義日11:30に設定されています。締め切りの時間は回ごとに短くなっていきますので注意してください。 宿題の開始時間は講義日12:00、締め切りは翌週水曜の10:30です。 補充問題、発展問題の開始時間は講義日6:00に設定されています。 問題数は約8,000あり、学習範囲、難易度に応じて約300のカテゴリに分けられています。LETUS上の小テスト(小テスト、宿題、補充問題、発展問題)はランダム、シャッフル出題です。 教科書に関する内容だけでなく、上記のLETUS上の問題に関する疑問、質問はQ&Aフォーラムで受け付けます。2023年度は200件近くの疑問、質問に回答しました。積極的な参加を希望します。 第1回 第9章『アルキン:有機合成序論』HX, X2の付加、アルキンの水和、還元、酸化的開裂、アルキンの酸性度、アセチリドアニオンのアルキル化について理解する(9·3~8)。 第2回 第9章『アルキン:有機合成序論』有機合成序説について理解する(9·9)。第10章『有機ハロゲン化物』命名法、ラジカルハロゲン化について理解する(10·1,2)。 第3回 第10章『有機ハロゲン化物』アリル位臭素化、アリルラジカルの安定性、ハロゲン化アルキルの合成、Grignard試薬、有機金属カップリング反応、有機化学における酸化と還元について理解する(10·3~8)。 第4回 第11章『ハロゲン化アルキルの反応:求核置換と脱離』Walden反転、SN2反応について理解する(11·1~3)。 第5回 第11章『ハロゲン化アルキルの反応:求核置換と脱離』SN1反応、E2反応について理解する(11·4~8)。 第6回 第11章『ハロゲン化アルキルの反応:求核置換と脱離』E2反応の立体化学、E1反応、E1cB反応について理解する(11·9,10,12)。第14章『共役ジエンと紫外分光法』共役ジエンの安定性、求電子付加について理解する(14·1,2)。 第7回 第14章『共役ジエンと紫外分光法』速度支配/熱力学支配、Diels–Alder反応について理解する(11·3~5)。PDFで提出する補充問題が用意されている(赤ペンを入れて返却する)。 第8回 第15章『ベンゼンと芳香族性』芳香族化合物の命名法、構造と安定性、Hückel則、芳香族イオンについて理解する(15·1~4)。 第9回 第15章『ベンゼンと芳香族性』複素環式芳香族化合物、多環式芳香族化合物について理解する(15·5,6)。第16章『ベンゼンの化学:芳香族求電子置換』芳香族求電子置換反応について理解する(16·1,2)。 第10回 第16章『ベンゼンの化学:芳香族求電子置換』Fridel–Crafts反応、求電子置換における置換基効果について理解する(16·3~5)。 第11回 第16章『ベンゼンの化学:芳香族求電子置換』芳香族求核置換、ベンザイン、芳香族化合物の酸化・還元について理解する(16·6~9)。 第12回 第16章『ベンゼンの化学:芳香族求電子置換』多置換ベンゼンの合成について理解する(16·10)。 第13回 第31章『合成ポリマー』連鎖成長ポリマー、逐次成長ポリマーについて理解する。模擬試験問題に取り組む。到達度評価(ペーパーテスト)に取り組み、期限までに提出する。 第14回 到達度評価(WEBテスト1回目:本試験)。第1回〜第13回の復習をする。 第15回 到達度評価(WEBテスト2回目:追試験)。第1回〜第13回の復習をする。 「分子の対称性」についての理解を深める教材が用意してあります。有機化学1Aでは発展問題として、有機化学1Bでは補充問題として取り扱います。 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
Mathematica/Signals ChemDraw(旧ChemOffice Professional)
ChemOffice (ChemDraw)
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

