シラバス情報
|
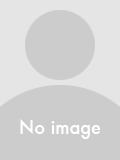
教員名 : 貞清 正彰
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
化学総論2
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Lectures on Current Topics in Chemistry2
授業コード Class code
9913338
科目番号 Course number
16UGRES403
教員名
築山 光一、高木 慎介、町田 英明、村田 正弘、松元 亮、貞清 正彰
Instructor
Koichi Tsukiyama
Shinsuke Takagi Masahiro Murata Hideaki Machida Akira Matsumoto 開講年度学期
2025年度後期
Year
2025年度
Semester
②Second semester
曜日時限
水曜2限
Class hours
Wednesday 2nd. Period
開講学科・専攻 Department
理学部第一部 応用化学科
Department of Applied Chemistry, Faculty of Science Division Ⅰ 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
これまで学んできた化学に関する基礎が、最先端の化学の研究や人間社会にどのように関わっているかを学ぶ。5人の講師の先生方が様々な分野の最新の化学研究のトピックスに関する講義あるいはセミナーを行なう。
目的 Objectives
化学の基礎学力をもとに、社会人基礎力としての問題解決力や職業観・就職意識、倫理観などを習得する。本学部のディプロマ・ポリシーに定める「ますます複雑化する社会情勢の中で、基礎学力を基盤として、現代社会における解決困難な様々な課題に対し、柔軟に応用展開できる力を身に付けた人材」を育成するための科目である。
到達目標 Outcomes
産学官の幅広い分野で活躍する講師陣を招いたオムニバス形式の講義をとおして、各分野における現実的な課題を多面的に学ぶことにより、創造的思考力を身につけ、広い視野に立ったキャリアパスの手がかりを得ることができる。産業界における現状や問題点についての知識を習得することによって、将来就職した場合における問題解決能力や分析力などを獲得することができる。
卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
各授業の詳細はLETUSで指示しますので必ず確認してください。
アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay
-
準備学習・復習 Preparation and review
各担当教員の指示に従って、予習・復習を行うこと。
成績評価方法 Performance grading policy
レポートにより評価する。詳細は講義にて説明する。
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
井上晴夫他著、丸善「光化学<1>」
石井邦雄著、羊土社「はじめの一歩の イラスト薬理学」 授業計画 Class plan
すべての履修学生に対して、半数以上の授業回を対面で受講することを求める。
諸事情によりオンライン講義となる回が発生する場合はLETUSで事前に指示するので必ず確認すること。 第1回:レーザーと化学反応(1)(築山) 講義形式:対面 第4回:CVD (Chemical Vapor Deposition、化学気相堆積)について(町田)(予定:対面) 薄膜作成技術の一つであるCVDの概要 CVDのメリット、および他の薄膜作成技術との比較 産業上での利用例 – 半導体(LED、ULSI、太陽光パネルなど) 第5回:CVDに用いる原料(前駆体)について(町田)(予定:対面) CVD原料の必要条件 様々な膜種と原料の関係 CVD原料としての有機金属化合物-MO原料の研究開発 第6回:ALD (Atomic Layer Deposition、原子層堆積)について(町田)(予定:対面) CVDの発展形であるALDの概要 ALDのメリット、および産業上での利用例(最先端半導体) ALD原料に適した有機金属化合物-MO原料 CVDおよびALDの今後 第7回:光化学の基礎とその応用(高木)(予定:対面) なぜ、化学を学ぶのかという根本的な部分から始まり、本講義では「光と物質の相互作用」に焦点をあて、主に量子化学的視点から下記の項目について解説する。 講義形式は全て対面を基本とする。 1) 人間の世界と原子・分子の世界 2) 原子・分子の電子状態 3) 光と物質、吸収と発光 4) 励起状態 5) 励起状態からの失活と反応 6) 光化学 7) 人工光合成などの光化学研究 第8回:光化学の基礎とその応用(高木)(予定:対面) 同上 第9回:光化学の基礎とその応用(高木)(予定:対面) 同上 第10回:ソフトマターの機能と応用(松元) 講義形式:対面 ソフトマターは、 物理、 化学、 生物、材料工学などにまたがる学際的研究分野である。 生体(材料)を理解する上で必須の概念であり、材料工学の発展に重要な示唆をもたらす。繊維タンパク質を実例に挙げながら、そのエッセンスを学ぶ。 第11回:ドラッグデリバリーシステム概論:ナノマシン、ナノデバイス(松元) 講義形式:対面 ドラッグデリバリーシステムとは、薬を必要な量、必要な時間、必要な場所へ届ける技術である。薬の有効性を高め、副作用を低減することを目的としている。最新の化学やナノテクノロジーを駆使して挑む診断・治療技術の最前線を概説する。 第12回:“ボロノレクチン”で開拓する医工学(松元) 講義形式:対面 ボロン酸は低分子ながら多様な生体分子と相互作用し、その強度と選択性は合成化学的にテーラーメードできる。糖結合性タンパク質の総称であるレクチンに準えて“ボロノレクチン”とも呼ばれる。講師らが展開する最新のバイオエンジニアリング研究を概説する。 第13回:「学問と創薬」の歴史を振り返り、最新の創薬研究を学び今後の創薬に求められる研究機能を考察する 〜Modality & Eco-system & 融合領域を担う人財の育成 〜 (村田)(予定:対面) ①演者が担当した創薬研究の経歴紹介を通して科学研究へ誘う <内容> 創薬テーマ設定での「病態ベースの仮説思考」と最新技術へのアクセスの重要性を学ぶ 第14回:学問と創薬」の歴史を振り返り、最新の創薬研究を学び今後の創薬に求められる研究機能を考察する 〜Modality & Eco-system & 融合領域を担う人財の育成 〜 (村田)(予定:対面) ②生命科学(ライフサイエンス)の誕生、進捗、実装システム(規制、政策)を学ぶ <内容> 歴史から見た学問の発展、技術革新に基づく学問領域の融合(ライフサイエンスの誕生)、ライフサイエンス誕生以降の革新的技術、技術進歩と規制 第15回:学問と創薬」の歴史を振り返り、最新の創薬研究を学び今後の創薬に求められる研究機能を考察する 〜Modality & Eco-system & 融合領域を担う人財の育成 〜 (村田)(予定:対面) ③創薬ベンチャー(アカデミア発)の成功に向けた必要な社会実装機能を学ぶ <内容> 最新科学技術・イノベーション政策、エコシステム、Modality、融合領域を担う人財育成 担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容 Work experience of the instructor
-
教育用ソフトウェア Educational software
Signals ChemDraw(旧ChemOffice Professional)
-
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

