シラバス情報
|
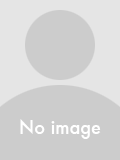
教員名 : (担当未登録)
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
English Seminar a (前期木4・田尻)※2024年度閉講
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
English Seminar a (前期木4・田尻)※2024年度閉講
授業コード Class code
99KT49Z
科目番号 Course number
L3FLENG107
教員名
(担当未登録)
Instructor
TAJIRI, Ayumu
開講年度学期
2024年度前期
Year/Semester
2024 / First semester
曜日時限
木曜4限
Class hours
The fourth period on Thursday
開講学科・専攻 Department
工学部(一般教養科目)、先進工学部(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Faculty of Engineering A course of liberal arts, the Faculty of Advanced Engineering 単位数 Course credit
1.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
近年、「批判的思考力」が必要と言われることが増えました。しかし、実際それは具体的にどんな能力を指しているのでしょうか? 目にする情報すべてを疑うことなのでしょうか? あるいは、見過ごされているが絶対的に正しい基準を見つけ出し、それに照らし合わせて判断していくことなのでしょうか?
このEnglish Seminarでは、英語文献の読解を通じて「批判的思考critical thinking」そのものについての理解を深め、身につけることを目指します。この授業は、日本語でも訳書が複数出ているアメリカ合衆国の著名な作家ベル・フックスが書いた英文の読解を中心に進めます。労働者階級出身でアフリカ系アメリカ人女性であるフックスの文章を読み取る中で、高度な語彙力・読解力だけでなく、社会階級、人種やジェンダーに関する知識も養います。本授業は、学生同士が意見を交換し合う対話的なゼミ形式でおこないます。 目的 Objectives
・英文を批判的に読み解く力を身につける
・論理的かつ批判的に思考する力を高める ・他者の立場に立って考えることができる想像力を高める ・他受講生と意見交換し自分の考えを伝えるスキルを身につける ・学術的な語彙や日常の場面で頻繁に用いられる表現を獲得する 本授業は、本学の「教養科目の編成方針」のうち(1)自然・人間・社会を幅広く俯瞰できる能力、(3)コミュニケーション能力の向上を目標としています。 到達目標 Outcomes
この授業が終了した時に、受講者は以下のような知識や能力を身につけることを具体的な目標とします。
・批判的思考がどういうものか、具体的に自分の言葉で説明できる。 ・学術的なテクストによく現れる基礎的な英語表現を知っており、意味を理解できる。 ・自分の経験と学術的な議論とを接続して平易な英語で表現できる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
・各学期で4回以上欠席がある場合は成績をつけることができないので注意するように。 ・授業においては、ペアワークやグループワークなどを取り入れながら進めていく。・辞書は必ず毎回使用すること。 ・障害その他の事情のために配慮を望む学生がいれば、面談をしますので申し出てください。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test/ディベート・ディスカッション Debate/Discussion/グループワーク Group work/プレゼンテーション Presentation/-
-
準備学習・復習 Preparation and review
予習
1)課題範囲をかならず事前に読むこと。 2)1の作業の中で理解できなかった固有名詞、語彙・熟語を調べて来ること。 3)自分が理解できなかった主張や疑問に感じた/納得できなかった部分を聞かれたら答えられるようにしておくこと。 →これらを毎回予習で行ない、授業で発言・意見交換することで、読解力、批判的思考力が習得されていく。 復習 予習した上で授業を受けたのち、 a)理解できなかった箇所が背景的な知識の不足によるものだったのか、 b)英文的な慣れによるものだったのかを判断する。 aの場合は、自分でネットや書籍で歴史や概念について調べてみたり、教員に参考文献を聞いたりと対応することができる。 bの場合、参考書や辞書を見て、次回同じような英文パターンが出てきたときの心づもりができる。 この予習・復習のサイクルを繰り返すことで、より読解力・理解力が向上していく。 成績評価方法 Performance grading policy
・授業への積極的参加・貢献度(授業内での発言・質問、グループワークでの取り組み、レスポンスペーパー)50%
・中間テスト(筆記)25% ・期末レポート(英作文あり)25% *出席そのものは成績評価には含まない。ただし、4回以上欠席した場合は成績評価の対象外となる。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
-
書誌情報 Bibliographic information
bell hooks, _Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom_ (London: Routledge, 2010)の一部を読み進めるが、購入の必要はない。読解対象のテクストは適宜授業で配布する。
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
本授業で主題となる批判的思考、生活と結びついた知識の獲得、対話的教育について知るのに、以下の文献が参考になる。
・ベル・フックス『学ぶことは、とびこえること : 自由のためのフェミニズム教育』 朴和美、堀田碧、吉原令子訳、筑摩書房、2023年。 ・パウロ・フレイレ『被抑圧者の教育学』三砂ちづる訳、亜紀書房、2011年。 授業計画 Class plan
第1回 ガイダンス
授業の内容と目的についてガイダンスを行い、自己紹介やアイスブレイク(緊張を解くこと)のアクティヴィティをします。 第2回 Teaching: Introduction 批判的読解(クリティカル・リーディング)の基礎を確認したあと、講読を進めます。 第3回 Critical Thinking 第4回 Democratic Education 第5回 Engaged Pedagogy 第6回 Decolonization 第7回 Integrity 第8回 Purpose 第9回 Collaboration 第10回 確認テストと振り返り 第11回 Conversation 講読を継続しつつ、この回から学期末のレポート課題の準備も進めます。 第12回 Telling the Story 第13回 Sharing the Story 第14回 Imagination 第15回 レポート準備 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
-
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
-
|

