シラバス情報
|
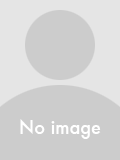
教員名 : 村上 学
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
哲学 (後期水2・村上)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Philosophy (後期水2・村上)
授業コード Class code
99KT22V
科目番号 Course number
L3HSHUM105
教員名
村上 学
Instructor
MURAKAMI, Manabu
開講年度学期
2024年度後期
Year/Semester
2024/Second semester
曜日時限
水曜2限
Class hours
Wednesday, 2nd period
開講学科・専攻 Department
工学部(一般教養科目)、先進工学部(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Faculty of Engineering A course of liberal arts, the Faculty of Advanced Engineering 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
【授業の概要】
この授業は本学部のディブロマポリシー及びカリキュラムポリシーに定める「豊かな人間性・想像力と国際性を備え、多面的にかつ新しい視点を持って科学技術の発展に貢献できる人材の育成」を実現するための科目です。現代社会における科学技術は、これまでの歴史上人類が体験しなかった規模と質と早さとで人間の生活を変えています。その変化は、時に個人や社会に難しい選択を迫り、その時人々に問題に直面して「どの様に考えたらよいのか」という反省を迫ることになります。そして、この「反省」の場面で何らかの「哲学」、あるいは「哲学的な思考」の召喚があち らこちらで行われているのです。 この講義ではとりわけ本学が提供する「論理的な思考」「コミュニケーション能力」にかかわる教養科目として、「情報化社会」や「コミュニケーションスキル」において問題となっている「言論の理解」の仕方に焦点を当てます。その際、哲学者プラトンやアリストテレス以来の伝統に倣って、論理 やレトリック(説得法)を手がかりに「思考法」について一緒に考えていきます。 目的 Objectives
【授業の目的】
この授業は本学部のディブロマポリシー及びカリキュラムポリシーに定める「豊かな人間性・想像力と国際性を備え、多面的にかつ新しい視点を持って科学技術の発展に貢献できる人材の育成」を実現するための科目ある。受講者は、この講義を通じて、日常耳にする言説にしばしば含まれる、間違った論理(「誤謬推理」)を見抜くことができるようになる。その上で、各自の哲学的な活動として「自分自身で考える力」「他人の話をよく聞き、理解する力」の礎を築き「論理的思考」「コミュニケーション能力」の涵養を目指す。 到達目標 Outcomes
【到達目標】
・「哲学的に考える」ことについて、一定の説明と実践例を提示することができる。 ・正常な会話(コミュニケーション)の成立用件を説明できる。 ・会話に不可欠な質問について、その種別や機能を説明でき、実際に会話中で適切な質問文を作ることができる。 ・「論理」や「論理的である」ことの意味が説明できるとともに、基本的なタイプである演繹法と帰納法を峻別できる。 ・授業各回で解説される誤謬推理について、日常会話中での使用に気づくことができる。 ・授業各回で解説される誤謬推理について、どこが誤謬であるのかを説明することができる。 ・授業各回で解説される誤謬推理について、間違いを正すことができる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
カテゴリーB科目(1、2年生対象)
アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
小テストの実施 Quiz type test
-
準備学習・復習 Preparation and review
各回で解説される推論や誤謬推理について、日常会話に応用できるように復習をすること(120分)。
予習については別に指示する(60分程度)。 成績評価方法 Performance grading policy
小テストと 到達目標の達成度(期末試験)により評価する。
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
授業内でプリント配布予定
授業計画 Class plan
授業は講義形式で実施する。しかし、受講者は必要に応じて不明な点を教員の話の途中でも適宜質問することができる。
1 ガイダンス: 授業の内容、進め方などについて説明する。 (復習)言葉や論理がどのような意味で哲学の問題であるのか説明できるようになる 2 推論の形式(タイプ)の概要。「因果律」や「相関性」、「集合」「確率」といった、論理的思考に関わる基本概念を学習する。 (復習)基本概念の理解を確かなものにする。 3 会話の理論1 :グライス等を参考に、会話の理論を概観する。どのような仕方で我々は意思疎通を行うのかを確認し、その上で相手の話を聞く時に留意すべき点を考える。 (復習)「協調の原理」と「四つの格率」が説明でき、また、発言のどの部分が格率に従っているのか/違反しているのかを峻別することができる。 4 会話の理論2 :「説得」と呼ばれる会話に注目し、情報化社会におけるコミュニケーションの問題を考える。そこから「非形式論理」の概要を学ぶ。 (復習)日常会話における会話の種類を説明できる。また、その中でも「説得」が現代社会のコミュニケーションにおいて果たす役割を理解した上で、その問題点を指摘することができる。 5 論理1 :「論理」とは何かを概観した上で、帰納法、演繹法といった論理学の基礎 を復習する。できるだけ日常会話での具体的な使用を参照しながら、特別な思考法でないことを確認する。 (復習)「考えること」が日常から「論理的」であることを説明できる。演繹法と帰納法との基本形式を理解し、いくつかの事例を挙げることができる。 6 論理2 :日本語における「接続詞」の使用を復習する。また、「証拠」と「仮説」の関係を確認し、まとまった文章全体の論理構成の問題を学ぶ。 (復習)いわゆる「論理的文章」において接続詞が果たす役割を理解するようになる。その上で、可能ならば個別の文章内で適切な接続詞を選択・使用できるようになるのが望ましい。 7 非形式論理1 :日常会話における誤謬推理に注目する。まず、「前提」の問題を取り上 げ、「多問の誤謬」「不当二分割」について学習する。 (復習)「二項対立」「不当二分割」について、どのような誤謬か、どこに問題があるのかを理解し、日常会話での例文をあげることができる。 8 非形式論理2 :日常会話における誤謬推理に注目する。演繹法の形式を備えた誤謬推理として「論点先取」を扱う。その際、相手の話に潜む隠された前提に注目することが重要であることを学ぶ。 (復習)演繹法の形式を備えた議論を識別できる。会話において「前提」がしばしば省略されることを理解した上で、日常会話でのそれぞれの発言において隠されている前提を指摘できるようになる。 9 非形式論理3 :日常会話における誤謬推理に注目する。3回連続で弱い帰納法の誤謬 を扱う。「軽率な一般化」「滑り坂理論」「ドミノ式理論」等、日々の報道や政治家のコメントにしばしば登場するタイプをあげながら、人間の経験の一般化の問題を学修する。 (復習)帰納法が「経験の形式である」ことを理解した上で、その限界を説明することができる。「軽率な一般化」が日常で頻繁に使用されることを理解し、身の回りの会話からいくつかの事例を挙げることができるようになる。 10 非形式論理4 日常会話における誤謬推理に注目する。「軽率な一般化」「滑り坂理 論」「ドミノ理論」等、日々の報道や政治家のコメントにしばしば登場するタイフ?をあげながら、人間の経験の一般 化の問題を考え、理解を深める。 (復習)滑り坂理論とドミノ式理論のおおよその形式を説明することができる。また、問題点を指摘した上で、いずれの理論に対しても適切な反論を組み立てることができる。 11 非形式論理5 日常会話における誤謬推理に注目する。言葉の「曖昧さ」に起因する誤謬推理、「ずるい言い回し」を取り上げる。差別発言等にみられる価値評価語の使用を検討しながら「ずるい言い回し」の構造をみてとり、問題点と反論法について学ぶ。 (復習)言葉の曖昧さの二種類を区別できる。ずるい言い回しが成立する構造を理解した上で、適切な反論を試みることができる。 12 非形式論理6 :日常会話における誤謬推理に注目する。この回は、対話への「参加者」 の人柄に注目しながら、「感情に訴える議論」「対人論法」等を学ぶ。特に、感情に訴える議論が成立する基盤として言語と感情の関係や説得と感情との関係等、哲学的心理学の理解を深める。 (復習)感情の種類について、説得との関連で数え上げることができる。感情の働きと、人間の思考や行為との関連を説明することができる。 13 非形式論理7:日常会話における誤謬推理に注目する。この回は、対話への「参加者」 の人柄に注目しながら、「憐れみに訴える議論」「対人論法」等を学ぶ。特に、対人論法が古典的な説得法と して有効でありつづけた理由を、倫理に関わる哲学的対話との関連させて考え、理解を深める。 (復習)対人論法の三つのタイプを説明できる。対人論法と「ソクラテスの対話」との関連性や違いを理解した上で、自己の一貫性(アイデンティティ)を言語の側面から説明することができる。 14 コミュニケーション能力 :「コミュニケーション能力」とは結局何かを議論し、さら にこの能力が過度に求められる社会的背景を展望する。そのうえで、「批判的態度」とはどのような話の聞き方なのかを確認して、建設的で有意義な対話のあり方を考えつつ、理解を深める。 (復習)現代社会がコミュニケーションを過度に求める背景を説明することができる。また、批判的態度とはどのような話の聞き方であるのか、その重要性、必要性を理解しつつ説明をすることができる。その上でこれまで学んだことを見直しながら、理解が及んでない部分を補い達成度評価試験に備える。 15 まとめ :達成度確認テスト。哲学が重要な教養科目となるのは、どのような人間像が描かれる故 になのか。この問いに答えながら、「対話」の重要性と、方法論の反省とが必要であることとをもう一度確認 する。 (復習)授業全体の意義を再確認する。 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
110名を超える学生が受講を希望した場合は受講を制限(抽選)することがある。
小テストは第2回の授業より開始する(実施は第3回目と同時期予定)。第3回目から受講を開始する学生は第2回の内容について各自で学習した上で受験すること。 授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

