シラバス情報
|
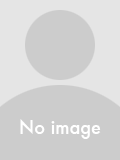
教員名 : 小林 真美
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
日本語プレゼンテーション 【日本語表現法2】(火・7)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Japanese Presentations 【日本語表現法2】(火・7)
授業コード Class code
99K2304
科目番号 Course number
L1CAECMb21
教員名
小林 真美
Instructor
Masami Kobayashi
開講年度学期
2024年度後期
Year/Semester
2024 Second Semester
曜日時限
火曜7限
Class hours
Tuesday 7th Period
開講学科・専攻 Department
理学部第二部(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Faculty of Science Division Ⅱ 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
「ことば」は単なる記号であり、文章はその羅列にしかすぎない。「ことば」に生命を与え、広大な表現世界を現出させるものは、表現者自身による「ことば」の選択と配列とに外ならない。「ことば」の的確な選択、統一性のある配列を実現させるためには、それ相応の知識と技術とが要求される。「書く」という行為は「話す」こととは本質的に異なるものであり、そこには独自の約束事が存在する。
「日本語表現」関連科目では、その基礎及び応用を身に付けつつ、正確で、他者にもわかりやすい日本語表現技術の修得を行う。 目的 Objectives
「基礎編」にあたる「日本語プレゼンテーション(日本語表現法2)」では、日本語学習のうち、コミュニケーション能力の向上に重点を置く。
口頭によるプレゼンテーションや文章構成に関する技術の修得を通して、他者を意識しつつ、物事を多角的な角度から捉えて考察し、それを伝える方法を身に付けるとともに、就職・進学いずれの進路においても不可欠である日本語表現能力や生涯学習力を養成する。 なお、本科目は、本学教養教育の編成方針に定める「自然・人間・社会を幅広く俯瞰できる能力」「論理的・批判的思考力」「コミュニケーション能力」「国際性」を涵養するための科目である。 到達目標 Outcomes
1.口頭(会話)及び文章における日本語の表現方法を区別し、説明できるようになる。
2.口頭(会話)及び文章によって、論理的な構成方法に基づいた自分の見解・意見を述べることができる。 3.他者による話し方や文章表現に関心を持つことができる。 4.他者に常に分かりやすいプレゼンテーションを行うことに取り組めるようになる。 5.日常的に、関心を持った言葉や物事について、自ら調べ、考える習慣を身につけられるようになる。 6.日本語表現能力の習熟によって、日常生活における、コミュニケーション能力の大切さを理解し、それを発揮することができる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
授業の主な実施形態は、「対面授業」である。
履修者は、出欠及び提出物管理を厳密に行うことが望ましい。 許可した場合を除き、対面授業実施時におけるパソコン等の使用、及び、スマートフォン等の電子機器による撮影は、禁止する。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test/プレゼンテーション Presentation
-
準備学習・復習 Preparation and review
授業時に出された課題に基づき、次回の授業に関する準備学習を進めるとともに、解答の誤った箇所や知り得た日本語常識に関する復習も行うこと(各回2時間程度)。
また、授業時に、「日本語検定」や「漢字検定」等、日本語に関する検定試験を紹介するので、興味を持った学生は、積極的に受験すること。 なお、日常的に、新聞・書籍等の活字を読むことや、テレビ・ラジオ等に登場する人びとの話し方に耳を傾けることによって、授業内容をより深く理解できると考える。それらを用いて、大学生らしい日本語表現能力を身につけて欲しい。 成績評価方法 Performance grading policy
到達度評価では、授業時における「口頭プレゼンテーション」(30%)及び「課題文作成演習」での執筆文章(30%)に、「毎回の受講姿勢(必要に応じて減点等を行う)・小テスト(原則、実施した授業時もしくは次回の授業時に解答・解説)」等を平常点(40%)として加味して評価する。
なお、第2回目の授業より、第15 回目の授業までの間に、欠席が5回以上の者や、口頭プレゼンテーションの未発表者、課題文の未提出者、授業態度に問題のある者(課題文における剽窃、代返等の関与も含む)については、採点の対象とせず、不可とする。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
「国語辞典」(電子辞書も可。あまり簡便なものでなければどこの出版社発行のものでもよいが、〈課題文作成演習〉の際は必携すること)
・『新しい国語表記ハンドブック』【第九版】、三省堂編修所編(三省堂、2021) その他の書籍に関しても、随時、指示する。 授業計画 Class plan
《項目及び内容》
1. 講義計画の説明 [内容:講義計画の概要を示すとともに、文章を作成することの意義、及び「日本語表現法(日本語表現法1)」の内容の概略について触れ、授業の流れを理解する。 また、正しい表現を理解するため、誤りやすい言葉遣い・表記等に関する簡単なテスト問題を課す。] 2.自己紹介・マインドマップの作成法 [内容:コミュニケーションの基本である「自己紹介」の意義や役割を考えつつ、口頭表現等においてより良くアピールできる方法について学ぶ。] 3.発音・発声・姿勢 [内容:口頭表現を行う上で重要となる発声・発音方法を学ぶとともに、話し方におけるアクセントや姿勢について理解する。] 4.朗読・話し方の技術 [内容:朗読における留意点、及びアイコンタクト等、口頭プレゼンテーションを行う上で大切な三要素について学ぶ。] 5.話の聴き方・スピーチ [内容:日常における話の聴き方について反省しつつ、傾聴力を養う。また、次回以降に実施する口頭プレゼンテーションに向けて、話の組み立て方に関する理解を深める。] 6.敬語(※以降、口頭プレゼンテーションと並行) [内容:敬語に関する小テストを行い、現代社会における正しい敬語法を身につける。] 7.文章の分類・書くことに慣れる [内容:文章の種類について知り、適切な使い分けを考える。また、書くことに慣れるための訓練を通して、文章作成に対する理解を深める。] 8.発想法 [内容:ブレーンストーミングなどを中心に、書くための材料を見つける方法を習得する。さらには、それを主題化させて、アウトラインに結びつけていく方法を考える。] 9.テーマ設定と目標規定文 [内容:より良いテーマ設定の方法について習得する。また、レポート・論文を書く上で、道筋をつける役割を果たす目標規定文の作り方を理解する。] 10.事実と意見 [内容:「事実」とは何か、「意見」とは何かを理解しつつ、論拠と推論との開わりについて、文章表現の上で注意すべきことを確認する。] 11.文体の統一 [内容:常体(だ・である・する体)と、敬体(です・ます・します体)の使い方を知り、論理的な文章を書く上において必要な文末表現を理解する。] 12.文章形式・アウトライン [内容:文章形式の基礎である三段論法や起承転結、五段論法等を学び、その特質を考える。また、アウトラインに関して、その準備作業の必要性や、課題に応じた基本形式、具体的に気をつけなければならない点を確認する。] 13.文献の引用・「引用」と「盗用・剽窃」の区別・チェックリストの活用 [内容:論文作成に欠かせない作業である参考文献の探し方や、それを上手に引用するコツ、及び引用した文献の示し方を習得する。 また、文章を書いたり、見直したりするときにどういう点を注意しなければならないのか、チェックポイントを考える。] 14.レポートの書き方・資料の作り方 [内容:レポートの構成や執筆時の留意点等を学ぶ。また、図解やチャート、グラフ等、レポート作成の上で必要とされる資料の種類について理解を深める。] 15.学習内容の総括・課題文作成演習 [内容:これまでの学習内容を振り返り、自らのコミュニケーション能力に関する不足点を補う。また、講義に基づく課題文作成演習を行い、授業に対する理解度をみる。] 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
高等学校教員(国語)、予備校・塾講師(国語)、家庭教師(国語)、書籍執筆・編集協力に関する勤務経験を活かし、日本語・日本文学を中心とする講義を行う。
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
授業計画は、あくまでも目安であり、諸事情により変更・圧縮がなされることがあり得る。
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

