シラバス情報
|
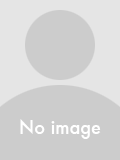
教員名 : 巻田 悦郎
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
論理学 (前・木5)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Logic (前・木5)
授業コード Class code
99K1602
科目番号 Course number
L1HSHUMc01
教員名
巻田 悦郎
Instructor
Etsuro Makita
開講年度学期
2024年度前期
Year/Semester
2024/Spring Semester
曜日時限
木曜5限
Class hours
Thursday 5th period
開講学科・専攻 Department
経営学部(一般教養科目)
A course of liberal arts, the School of Management 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
論理学は,正しい思考のための規則を考察する学問である。この場合,思考とは具体的には,推論(ある命題から別の命題を導き出すこと)である。正しい思考とは、妥当な推論、飛躍がない推論のことである。
本講義ではそのような論理学の初歩を学ぶ。 目的 Objectives
論理学を学ぶことには,論述展開や推論の論理的な妥当性に注意深くなるという意味がある。論理的思考は学問では不可欠である。たとえば,レポートや卒業研究はいくらデータが正しくても,議論の進め方が非論理的であれば,台無しである。
本科目は,教養科目として,教養教育の目標の(3)「課題を自ら発見し、主体的に考え、解決に取り組むための論理的・批判的思考力」の涵養に資する。 到達目標 Outcomes
命題論理と述語論理において,自然言語の命題・推論を正しく記号化し,論理式の恒真性を判定し,また,推論の妥当性を判定できるようにする。
卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
本科目は、カテゴリーCの教養科目で、2年生以上が履修可能。
私語が多い場合は座席指定制とする。 1)小課題を75%以上提出し,かつ,2)出席率が75%以上の履修者は履修意志あり,そうでない者は履修放棄と見なされる。 出欠は、CLASSに出席登録番号を登録する方法で、第1回目を除き毎回とる。出席率は,分子がその履修者の出席回数,分母が講義が行われた回数(1回目を除く)で計算される。 授業は講義形式であるが,テキストの練習問題を前に出てやってもらうなど,演習的要素も取り入れる。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/-
授業中の練習問題を当てて、ノートに書いたものを書画カメラで提示して皆でその検討する
テキストの練習問題の一部を小課題として課し,LETUSに提出する 準備学習・復習 Preparation and review
準備としては,事前にテキストを読んで練習問題を解いておくこと,復習としては,講義ではできなった練習問題を行うのが望ましい。
成績評価方法 Performance grading policy
成績は,学期中に課す小課題60%と,平常点40%の割合でつける。平常点は練習問題を当てられて答えるなど,講義に積極的に参加しているかどうかでつける。
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
テキストは担当講師作成のオリジナルなものを,LETUSの本科目のページからダウンロード可能にする。
授業計画 Class plan
1 はじめに・序章
はじめに(講義について)序章 論理学とは a)論理学と論理 b)諸科学との違い c)論理学の歴史と分類 d)演繹と帰納 e)伝統的論理学と記号論理学 f )推論・命題・概念 第1部 命題論理学 第1章 1)命題 a)命題と推論 — 論理学がどんな学問であるかを,その対象や歴史,分類などから知る — 推論が妥当であることと,推論の構成要素である命題が真であることとの違いを知る 2 第1部第1章1b,2ab b)命題とその真理値 2複合命題 a)単純命題と複合命題 b)記号化 — 命題の真偽はどのように決まるのかを知る — 命題には単純命題と複合命題があり,複合命題の記号化には論理結合子が必要なことを理解する 3 第1部第1章3a 3)論理結合子 a)5つの論理結合子 ア)否定 イ)連言 ウ)選言 エ)条件 オ)等値 — 5つの論理結合子のうち,否定と連言と選言と条件と等値がどんな論理的な関係かを理解し,自然言語で書かれた命題を記号化できるようにする 4 第1部第1章3bc,4 b)計算順序 c)二つの結合子への還元 4)真理関数と真理表 — 論理結合子の計算順序の方式を知り,また,5つの論理結合子を理論的にどれだけ減らすことが可能かを検討する — 複合命題の真理値が構成要素命題の真理値に対して真理関数となっていることを理解し,複合命題の真理表を書けるようにする 5 第1部第2章1,2a 第2章 論理式の恒真性 1)恒真性と論理法則 a)恒真性 b)論理法則 — すべての論理式は恒真か恒偽か偶然的かであることを理解し,また,基本的な恒真式である論理法則を知る 6 第1部第2章2b 2)恒真性判定の方法 a)真理表の方法 b)真理値分析 — 論理式の恒真性の判定の方法には真理表の方法など5つの方法があり,真理表の方法と真理値分析で、論理式が恒真かどうかを判定できるようにする 7 第1部第2章2d 3章1c c)割当法 — 推論の妥当性を推論のレベルにとどまって判定する方式のうち割当法を理解し,それを用いて推論の妥当性を判定できるようにする 8 第1部第2章2d 3章1d d)論理法則の方法 — 論理法則を使って論理式が恒真かどうかを判定できるようにする — 推論の妥当性を推論のレベルにとどまって判定する方式のうち割当法を理解し,それを用いて推論の妥当性を判定できるようにする 9 第1部第3章1b,2 b)論理式レベルへの還元 2)論法——妥当な推論形式の類型 — 推論の妥当性を論理式のレベルに還元して判定する方式を理解し,それを用いて推論の妥当性を判定できるようにする — 妥当な推論形式のパターンである論法にどんなものがあるのかを知り,それを活用できるようにする 10 第2部第1章1,2,3 第2部 述語論理 第1章 述語論理の基礎 1)文から語へ 2)単称命題・命題関数 3)量化命題 a)量化命題の表現 — 命題論理学では対処できない問題を解決するために,命題論理学を補完するものとして述語論理学が必要になることを理解する — まず単称命題を述語論理学で記号化できるようにする 11 第2部第1章3,4 b)個体領域 c)作用域・恒真性 d)作用域及び自由/束縛変項 4)量化命題の一般的表現 — 類称命題(全称命題・存在命題)を記号化できるようにするために,個体領域や作用域の概念を学ぶ — 類称命題を述語論理学で記号化する方法を理解し,実際にそれができるようにする 12 第2部第2章1,2 第2章 恒真性判定の方法 1)有限解釈の方法 2)割当法 — 述語論理学で記号化された論理式の恒真性を判定する方法として,有限解釈の方法と割当法を学び,それを用いて実際に恒真性を判定できるようにする 13 第2部第3章 第3章 論理法則 1)全体と部分 2)否定 3)連言 4)選言 5)条件 6)まとめ — 述語論理学の論理法則を,全体・部分,否定,連言,選言,条件などを手がかりとして引き出すことを学ぶ 14 第2部第4,5章 第4章 推論の妥当性の判定 1)多項述語 2)同一性 3)2階の述語論理 — 述語論理学において推論の妥当性を判定する方法として,割当法を理解し,それを用いて実際に推論の妥当性を判定できるようにする — 多項述語,そのうちの一種である同一性の論理学,そして,述語に変項を導入した2階の述語論理の基礎を学び,自然言語で書かれた簡単な命題をそれらで記号化できるようにする 15 まとめと達成度確認 — これまでの講義内容を総括するとともに,命題論理学および述語論理学において、自然言語で与えられた命題や推論を記号化し、論理式の恒真性や推論形式の妥当性を判定する能力を達成できたかを確認する 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
テキストのダウンロードや小課題の提出などは,LETUSの「論理学」のページで行う。
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

