シラバス情報
|
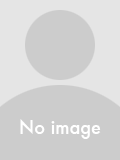
教員名 : 松本 朋子
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
現代政治論 (政治学2)(後・火2)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Contemporary Politics (政治学2)(後・火2)
授業コード Class code
99K1229
科目番号 Course number
L1HSSSCc23
教員名
松本 朋子
Instructor
Tomoko MATSUMOTO, Ph.D.
開講年度学期
2024年度後期
Year/Semester
2024/Second Semester
曜日時限
火曜2限
Class hours
Tuesday, 2nd period
開講学科・専攻 Department
理学部第一部(一般教養科目)、経営学部(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Faculty of Science Division Ⅰ A course of liberal arts, the School of Management 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
本講座では、国際政治の歴史を紐解き、世界をリードするアメリカとEUの政治を学ぶことで、国際社会の現状と課題に対する理解を深めることを目的とします。歴史は私たちにどのような教訓を残しているのかを検討する中で、みなさんが自分なりに将来の国際社会への展望を抱けるようになることを目標とします。
目的 Objectives
本授業の目的は、国際政治の歴史と米欧の政治を学ぶことで、国際社会を客観的に論理的に分析し、国際社会の課題に対して自らの主張を展開する力を養うことです。
到達目標 Outcomes
理解力:国際政治史と米欧政治の基礎的内容と授業で扱う政治概念を高校までで習う語彙を用いて説明できる
分析力:近現代の国際社会の動向から得られる議論・理論をもとに、現代の国際社会の課題を分析できる 判断力:正解のない課題に対して多角的な視野から判断できる 論述力: 自らの思考を論理的に説得的に伝えることができる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
特に予備知識は必要ありません。
授業への参加が求められます。遠隔ですが毎週積極的に参加してください。 講義中に発言を求めたり、ミニレポートを課したりすることがあります。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test/-
-
準備学習・復習 Preparation and review
【準備学習】(毎週1時間程度)
適宜紹介した参考文献について読んできてください。 【復習】 (毎週3時間程度) ・本講義ではほぼ毎週ミニテストを行います。必ず期限内に取り組んでください。 ・本講義では小課題を学期中に4回程度課します。(ただし、課題によっては授業時間中に提出のものもあり ます。) 翌週までに提出の課題については、設問をよく読み、自分の見解をまとめてきて下さい。 ・授業中で習った歴史や理論について、必要に応じて授業中に紹介する参考文献を読み、復習してくださ い。 【その他】 現代国際社会に関心を持つよう、新聞やテレビ等で政治の動向に注意を払って下さい。 成績評価方法 Performance grading policy
<すべてLETUS上でのオンライン提出です>
課題(40%)+ミニテスト(30%)+オンライン最終テスト(30%) ・課題(小課題25%+最終課題15%) 本講義では、学期中に小課題を4回程度、最終課題1回を課します。授業内容の理解を深めるとともに、自分の見解を論理的に記述する能力を向上させること、そして、みなさんが授業への能動的参加する機会を提供することを目的 とします。提出期限は、課題の内容によって、授業時間中か翌週かに分かれます。なお、小課題については授業中に講評、もしくは採点の上 返却します。 最終課題は告知から2週間程度、提出期限までに時間を空けます。この課題は返却しません。本最終課題の目的は、近現代の社会動向から得られる議論・理論をもとに、現代の政治経済社会を分析する力を養うこととします。 ・ミニテスト及び授業参加度(30%: 2.1点*14回) ほぼ毎週この授業ではミニテストを行います。選択式3問で授業課題教材を各位振り返りながら答えていただきます。このミニテストの目的は、授業内容について理解を深めることです。授業への欠席が多いとこの構成点に影響が生じます。 ・オンライン最終テスト(30%) 14回目授業で最終テストを行います。ミニテストから既出の問題と新出の問題をそれぞれ出します。このミニテストの目的は、授業内容について理解を深めることです。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
-
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
適宜、参考文献を紹介します。
授業計画 Class plan
第1回 イントロダクション
講義の概要、受講方法について紹介します。 <第一部 国際政治の展開> 私たちは今どんな国際社会に生きているのでしょう。第一部では、国際社会の基盤となる主権国家が誕生した17世紀から21世紀までを四回かけて俯瞰します。 第2回 戦争による主権国家の登場と世界の一体化 (17-19世紀) 国際政治の基本概念である主権国家概念の歴史は浅く17世紀のことです。主権国家はなぜヨーロッパで登場し、そして誕生した主権国家はどのように主権国家間の関係を築いたのでしょうか。三十年戦争から世界の一体化を進めた帝国主義までを解説します。 第3回 二度の世界大戦 (20世紀前半) 第一次世界大戦が始まった際、多くの人は短期の局地戦だと思っていました。ではなぜ第一次世界大戦は世界大戦に発展し、そして第二次世界大戦をも人々は防ぐことができなかったのでしょうか。世界史に残る二度の世界大戦を振り返ります。 第4回 冷戦と「平和」 (20世紀後半) 第二次世界大戦で共闘した米ソは戦争終結期から亀裂の兆しを見せ、そして冷戦へともつれ込みました。国家はどんな国も同じではなく、イデオロギーによって世界が二分されるようになったのです。冷戦をギャディスは「長い平和」と称しました。冷戦はなぜ「長い平和」であったのか、その「平和」は世界に共通する現象であったのかを検討します。 第5回 冷戦後の社会 (20世紀末から21世紀へ) 冷戦の終結で多くの人々は、世界の和解と平和を臨みましたが、米ソ後の世界を誰が率いるのか、国連なのか、アメリカなのか、それとも新興国なのか。混乱は続いています。現代世界を捉えるには学問的な蓄積はたりませんが、この三十年で新たに生じている問題をいくつか紹介します。 <第二部 超大国アメリカの政治と外交> 冷戦期の西側陣営の盟主でありそして現在も世界の超大国であるアメリカ合衆国を理解することは国際社会で生きる上で不可欠のことと言えるでしょう。第二部では、アメリカという国の理解を深めます。 第6回 アメリカの成り立ち アメリカ合衆国は先進国の中で最も「歴史」の短い国の一つといえるでしょう。アメリカはどのような歴史背景から生まれ、どのような特徴を有するのか一緒に学んでいきましょう。 第7回 アメリカの政治制度 アメリカは日本とは違い内閣議院制ではなく大統領制を取り、強い地方自治を有し、共和党と民主党という二大政党のもとに政治が運営されています。第7回はアメリカの説明をしつつ、比較政治的視野からその特徴を捉えていきたいと思います。 第8回 アメリカのマイノリティー問題と再分配問題 アメリカの大きな社会的テーマの一つはマイノリティー問題です。この人種問題、移民問題は同時に、アメリカの再分配問題や社会福祉のあり方にも影響を及ぼします。なぜ21世紀にもなって人種差別という問題が生じるのか、歴史を紐解きつつ解説したいと思います。 第9回 アメリカの安全保障と外交 アメリカは世界の警察であるべきなのかそれとも孤立主義を取るべきなのでしょうか、この非常に古くて新しいアメリカの外交姿勢をめぐる議論を紹介します。 <第三部 主権国家統合の実験場としてのEU> 西ヨーロッパは世界に主権国家という概念を持ち込んだ地域であり、3世紀に亘って国際社会の基盤としてきた主権国家概念に対して、主権国家の統合という挑戦を突きつけている地域です。日本の一大取引相手であり、そしてアメリカとよく対比されるEUで何が起きているのか、一緒に学びます。 第10回 ヨーロッパ統合の成り立ち ヨーロッパという概念はどのように登場し、統合実現に向けた動きはいつどのように進んだのでしょうか、ヨーロッパ統合の動きと課題も含めて検討します。 第11回 EUの政治制度 EUは主権国家の連合体です。ではどのように政治は運営されているのでしょうか。そこではどのような選挙制度のもとにどのような政党が存在し、どのように政策が決定されているのでしょうか。日本ともアメリカとも違う一つの先進国のあり方としてEUの政治制度を議論します。 第12回 EUの移民政策と再分配問題 EUの中にも先進国もあれば中進国も存在します。様々な多様な社会を包摂し、そして移民もまた受け入れているEUにおいて移民は、そして所得再分配や社会福祉はどのように議論されているのでしょうか。一緒に眺めたいと思います。 第13回 EUの安全保障と外交 一つの国ではなし得ないことも多国が共闘して単一アクターとして働きかければ、それは世界に大きなインパクトを与えるかもしれない。そのことを体現しているのがEUということもできます。EUが世界に果たす役割を議論しましょう。 第14回 到達度の確認と総括 (パソコン・タブレットの持参を忘れないでください) 本講義の到達度を確認し、これまでの内容について総括します。 第15回 演習 (パソコン・タブレットの持参を忘れないでください) 授業内容を踏まえて、現代の国際社会の方向性について皆さんに参加してもらう形で議論します。 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
・前提知識はいりません。楽しく参加してください。
・毎回モバイル出席登録をしてもらいます。 授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
-
|

