シラバス情報
|
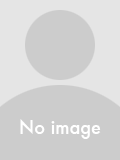
教員名 : 渡邉 万里子
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
イノベーション・チーム・ラボ
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Inovation Team Lab
授業コード Class code
9986K08
科目番号 Course number
教員名
平塚 三好、梅澤 正史、山口 順之、森本 千佳子、家田 雅志、高島 健太郎、佐藤 治、椿 美智子、照井 伸彦、渡邉 万里子
Instructor
Mariko Watanabe, Osamu Sato, Michiko Tsubaki
開講年度学期
2024年度後期
Year/Semester
2024/ 2nd Semester
曜日時限
月曜4限
Class hours
Monday/ 4th
開講学科・専攻 Department
経営学部 経営学科
Department of Management, School of Management 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
演習
Seminar 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
④ [遠隔]ハイフレックス型授業(キャンパス間配信)/ [Remote] Hybrid-Flexible format (with inter-campus streaming)
概要 Description
現在、世界規模で深刻化している気候変動、海洋・水質汚染、森林伐採などの環境問題の解決を抜きにして、今後国や企業の成長はもはや不可能である。環境問題のような複雑な社会課題を解決するためには、思わぬ副作用を伴う部分最適解ではなく、自然科学と社会科学の知見を融合した全体最適解を実現するイノベーションが鍵となる。本学の大学院生・学部生に求められることは、その優れた研究力に加え、全体最適なイノベーションを創造するための、問題発見力、問題解決力とビジネスに仕立てあげる企画力に他ならない。そこで、本科目では、全体最適なイノベーションを創造するうえで欠かせない異なる分野の知見や視点を持ったメンバーとの協働を通じて、研究「シード」を基に、持続可能な「ビジネス」として社会実装するビジョン構想力を養う。 理工学系の複数の専攻から成る大学院生がプロジェクトリーダーとなり、自身の研究シードを起点とした社会問題解決のための持続可能な事業案を検討する。チームメンバーには経営学部3学科の学部生が入り、各学科の専門的視点からプロジェクトの社会性・事業性・実現性を高める。 It is only possible for countries and companies to grow in the future by solving environmental problems such as climate change, ocean and water pollution, and deforestation, which are now becoming more severe on a global scale. The key to solving complex social issues such as environmental problems lies not in partially optimized solutions with unexpected side effects but in innovations that realize holistically optimal solutions by integrating the knowledge of natural and social sciences. What is required of our graduate and undergraduate students is not only their excellent research skills but also the ability to discover and solve problems and plan for business to create a holistically optimal innovation. Therefore, in this course, students will cultivate the ability to conceive a vision for social implementation as a sustainable "business" based on a research "seed" through collaboration with members with knowledge and perspectives from different fields, which is indispensable for creating holistically optimal innovation. Graduate students from multiple majors in science and engineering will serve as project leaders and examine sustainable business proposals for solving social problems based on their research seeds. Team members will include undergraduate students from the three departments of the College of Business Administration to enhance the social, business, and feasibility of the project from the specialized viewpoints of each department. 目的 Objectives
将来、起業家あるいは大企業のリーダーとなって、世界、日本の持続的な発展を可能とする全体最適型のイノベーションを実現することを念頭に、複雑な社会問題の全体像を俯瞰し、本質的な課題を発見して、自身の研究成果を社会実装できるイノベーション力と経営能力を養うことを目的とする。 本学科のディプロマ・ポリシーに定める「グローバル化や地球環境問題など広範かつ多様なビジネス環境で発生している諸々の問題に対して自然科学及び社会科学の知識を活用して解明するという基本的方針の下で理論的かつ実践的な考え方を身に付ける」を実現するための科目である。The objective of the program is to cultivate innovation and management skills that enable students to look at the big picture of complex social problems, discover essential issues, and implement the results of their research in society to become entrepreneurs or leaders of large companies in the future and realize holistically optimal innovation that will enable the sustainable development of the world and Japan. 到達目標 Outcomes
(1)社内起業家やプロジェクトリーダになる上での基本的な知識を身につける。
(2)専門性の高い技術シーズの内容を十分理解し、研究者に適切な質問ができる。 (3)技術シーズで解決できそうな問題を見つけ出し、具体的な解決策を提案できる。 (4)専攻が異なる学生とグループワークを通して、チーム力によって問題解決策を提案できる。 (5)インタビューや専門家からのフィードバックを通して、客観的な視点を持てる。 (6)第3者に対してアイデアピッチを行い、自分のアイデアを魅力的に伝える。 Outcomes are expected as follows, (1)Obtain the fundamental knowledge for entrepreneur and project leader (2)Understand technical seeds in laboratories and ask questions to researchers (3)Find a problem to be solved by technical seeds and propose a realistic solution (4)Build a team with students in various departments to propose a solution for the specific problem (5)Collect opinions from others by conducting the interview (6)Engagingly communicate your ideas in your pitch presentation. 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
・基本は葛飾キャンパスと神楽坂キャンパスをZoomで繋いだハイブリッド型授業とするが、最終プレゼンの準備、最終発表は1つのキャンパス内で対面授業とする。※グループ内の調整によって可能な場合は、どちらかのキャンパスに集まって授業を受けることが望ましい。 This class is held in Katsushika campus or Kagurazaka campus. Students can attend the class through remote lecture distribution system from either campus. It is strongly recommended to join the final presentation held in Katsushika campus.・定員は50名程度とし、希望者が多数の場合には抽選とする。 - 工学研究科/先進工学研究科:9名、経営学部:40名 Maximum number of students is limited to 50.- Advanced Engineering 9, Management 40. - 両キャンパス同士のグループワークはネットを介したビデオミーティング、チャット、SNSを利用して行う。 The group work will be done through video meetings, chat systems, SNS, and so on.・LETUS上で配布する資料を内容を理解の上、当日閲覧できるようにすること。出席して聴講し、討議に参加し、アンケート記載、レポート提出を行うことで成績評価する。 - なお、講義中に電子的に回答を求めることがあるので、学内ネットワークを利用できるPC/スマホを持参すること。 All copies for this class are distributed on LETUS. Students are recommended to understand copies, join discussions, answer questionnaires, and submit reports. All students should bring their device such as a PC and smartphone to answer questionnaires in real-time. ・最終回は14回・15回の合同授業(3時間)とし、その前週は最終プレゼンに向けた準備期間とする。 The final session will be a joint session of 14 and 15 (3 hours), and the week before that will be a preparation period for the final presentation.アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
グループワーク Group work/プレゼンテーション Presentation/PBL (課題解決型学習) Problem-based learning/-
準備学習・復習 Preparation and review
・LETUS上に事前登録される資料を、予め読んでおくこと。特に英語の資料は、事前に内容を理解しておくこと。 - レポート提出の指示があった場合には、復習の上必ず提出のこと。 Copies on LETUS are written in Japanese or English. Before the class, students should understand the copies. If needed, report submission is requested for evaluation. 成績評価方法 Performance grading policy
・プレゼン(事業構想の最終成果)70%+個人レポート(グループワークへの貢献)30%
- プレゼンは、最終発表に参加した教員が評価者となり、発表資料/発表内容/プレゼンの出来などをその場で採点し、それを集計して評価する。 - プレゼン内容は、①特定の授業回で指定されたコンテンツを必ず入れる、および②毎回の授業での学びをグループで議論した内容を含むこととする。 - 個人レポートは、自身のグループワークへの貢献やメンバーの貢献について自己評価する内容とし、それをグループワークへの貢献として評価する。 Group Presentation (final business plan result) 70% + Individual report (contribution to group work) 30%. 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
毎回、必要に応じて指示する。
References will be given each time as necessary. 授業計画 Class plan
1. (9月16日)イントロダクション 【講義担当:佐藤】
・講義の目的/概要の説明 ・技術を社会に還元することの大切さ 2~4. (9月23日、30、10月7日)研究シーズの紹介(1)〜(3)【講義担当:山口】 ・各研究室の研究シーズの紹介 ・即席チームでアイデアブレスト 5. (10月14日)チームビルディング【講義担当:渡邉】 ・プロジェクトチームの結成 6. (10月21日)アイデア創造【講義担当:高島】 ・アイデアの発想 ・アイデアの仮説検証 7. (10月28日)アイデア評価【講義担当:渡邉】 ・シナリオプランニング ・アイデアの評価 8. (11月4日)マーケティング【講義担当:照井】 ・市場セグメンテーションとターゲティング ・STPアプローチ 9. (11月11日)知財戦略【講義担当:平塚】 ・知財戦略の成功例と失敗例 ・J-Platpatを使った競合分析 10. (11月18日)ビジネスモデル【講義担当:渡邉】 ・バリュープロポジションマップ ・ビジネスモデルキャンバス(BMC) 11. (12月2日)ミクロ経済学【講義担当:梅澤】 12. (12月9日)ファイナンス【講義担当:家田】 13. (12月16日)プロジェクトマネジメント【講義担当:森本】 ・プロジェクト管理方法 ・ステージゲート 14/15. 最終発表【講義担当:山口、ゲスト講師※調整中】 1. Introduction 【Lecturer: Sato】 Purpose of this program Importance of giving back to society through technology 2~4. Introduction of research seeds (1)-(3) 【Lecturer: Yamaguchi】 Introduction of research seeds of each laboratory Idea brainstorming in impromptu teams 5. Team building【Lecturer:Watanabe】 ・Project team formation 6. Idea creation【Lecturer:Takashima】 ・Idea creation ・Hypothesis testing of ideas 7. Idea Evaluation 【Lecturer: Watanabe】 ・Scenario planning ・Idea evaluation 8. marketing 【Lecturer: Terui】 ・Market segmentation and targeting ・STP approach 9. Intellectual property strategy 【Lecturer: Hiratsuka】 ・Successful and unsuccessful examples of IP strategy ・Competitive analysis using J-Platpat 10. Business model【Lecturer:Watanabe】 ・Value proposition map ・Business Model Canvas 11. Microeconomics 【Lecturer: Umezawa】 ・Price Strategy and Product Differentiation ・Price differentiation 12. finance 【Lecturer: Ieda】 ・The life of a company ・NPV and investment decisions 13. project management 【Lecturer: Morimoto】 ・Project Management Methods ・Stage gate 14/15. Final presentation 【Lecturer: Yamaguchi, Guest lecturers *to be determined】 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
-
|

