シラバス情報
|
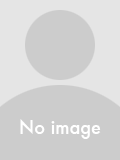
教員名 : 齋藤 智彦
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
電磁気学2
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Electromagnetism 2
授業コード Class code
9984003
科目番号 Course number
12PHELE202
教員名
齋藤 智彦
Instructor
Saitoh, Tomohiko
開講年度学期
2024年度後期
Year/Semester
2nd Semester, 2024
曜日時限
木曜3限
Class hours
3rd period, Thursday
開講学科・専攻 Department
先進工学部 物理工学科
Department of Applied Physics, Faculty of Advanced Engineering 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
⑤ [対面]ブレンド型授業/ [On-site] Blended format (must include 50%-or-more classes held on-site)
概要 Description
電磁気学は自然界の電気的・磁気的現象をわずか4組の式(マックスウェルの方程式)で記述する美しい理論体系です。すべての物質は正電荷を持つ原子核と負電荷を持つ電子から成るので、物質の成り立ちを理解する上で、電磁気学は不可欠のものです。また、場・エネルギー等、現代物理学の重要な概念を内包し、応用物理学の各分野への基礎知識として欠かせません。さらに特殊相対論との深いかかわりもあります。
以上のことから、物理学を応用する全ての研究・開発職に就く為にも、電磁気学は必要不可欠な知識/問題解決の道具であると言えます。 目的 Objectives
電磁気学の基礎的知識(特に静電磁場についての知識)を身につけ、最終的にマックスウェルの方程式に到達することが本講義(とそれに先立つ電磁気学1)の目的です。時間変動する電磁場、すなわち電磁波については「電磁気学3」で扱います。
本講義は、本学科のディプロマポリシーに定める「専門分野に捉われない幅広い基礎学力を身につけた人材」を育成するための科目です。 到達目標 Outcomes
(1) 電磁気学で扱う物理数学、即ち偏微分・多重積分・基礎的ベクトル解析等が使えるようになる。
(2) 誘電体の性質、および誘電体内外の静電場の振る舞いを説明できるようになる。 (3) ビオサバールの法則とアンペールの法則を説明できるようになる。 (4) 電磁誘導の概略を説明できるようになる。 (5) 交流回路の基本的動作を説明できるようになる。 (6) 磁性体内外の静磁場の振る舞いの概略を説明できるようになる。 (7) 電磁場がエネルギーを持つことの意味の概略を説明できるようになる。 (8) マックスウェルの方程式の意味の概略を説明できるようになる。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
(1) 前提とする知識
高校物理と高校数学。 (2) 講義の進め方 ほぼ教科書に沿って進み、式番号は教科書と同一にするので、これを利用して効率的にノートを取り、講義に集中してください。もちろん復習は不可欠です。教科書の内容の一部を、適宜増補・省略することもありますので、注意してください。また、時間の都合上、教科書にある式を板書で省略する場合があるので復習時に必ず自分で埋めてください。 (3) 学習の進め方 電磁気学(の一部)は高校でもやっている内容ですが、高校とは違って大学では数学的に現象を扱うようになり、難度も上がります。従って毎回必ず予習をして講義に臨み、復習では、毎回必ず自分で手を動かして計算し、内容を追うことが必要です。講義では例題を十分に扱うことはできないので、電磁気学1演習Bを合わせて受講することを強く推奨します。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
-
-
準備学習・復習 Preparation and review
準備学習:教科書を読んで、理解できるところとできないところを把握する。毎回2時間程度。
復習:教科書と講義ノートを用いて毎回2時間程度。毎回必ず自分で手を動かして計算を確認すること。 成績評価方法 Performance grading policy
授業の提出物20%+中間レポート30%+期末の到達度評価50%
学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
Y
書誌情報 Bibliographic information
兵頭俊夫 著 「電磁気学(増補修訂版)」(裳華房2021)
https://www.shokabo.co.jp/mybooks/ISBN978-4-7853-2274-8.htm MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
LETUS上の講義資料:
(1) 講義概要、過去問、補足事項等 (2) 過去の講義スライドPDF (3) 過去の授業動画 参考書・演習書: (1) 荒木修・齋藤智彦 著 「本質から理解する数学的手法」(裳華房2016) https://www.shokabo.co.jp/mybooks/ISBN978-4-7853-1570-2.htm 理工系の大学の1, 2年次に登場する数学についての解説です。特に3-5章は本講義での数学の解説を基にしています。なお電子版もあります。 (2) 前野昌弘 著 「よくわかる電磁気学」(東京図書2010) http://www.tokyo-tosho.co.jp/kikan/04/index.html 講義の教科書と同レベルの分かりやすい参考書。 (3) 砂川重信 著 「物理テキストシリーズ 電磁気学」(岩波書店1987) https://www.iwanami.co.jp/book/b260765.html (4)の「理論電磁気学」の初学者版。本も小さくコンパクトで便利。その分、凝縮された含蓄のある表現があり、(2)よりハイレベルです。。 (4) 砂川重信 著 「理論電磁気学 第3版」(紀伊國屋書店1999) https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784314008549 伝統的名著であり、教科書より進んだ内容も網羅(もうら)した、All in oneの定番教科書です。ハイレベルですがいつまでも使えます。 (5) 霜田光一・近角聰信 編 「大学演習電磁気学 全訂版」(裳華房 1980) http://www.shokabo.co.jp/mybooks/ISBN978-4-7853-8010-6.htm 簡潔なまとめと豊富な演習問題。レベル別に並んでいるので、自習しやすく、かつ大学院入試まで使えます。しかしオンデマンド印刷・製本となってしまいました。 授業計画 Class plan
以下、教科書の対応する章を[ ]で示します。なお、教科書では「付録」の章となっている、微分形のマックスウェルの方程式の導出は、第13章として講義で扱います。数学の内容については、参考書(1)の対応章も示しました。
1. 誘電体と静電場(1) 内容:誘電体についての実験事実を知り、誘電率、誘電体のミクロな性質とマクロな電場について理解する。また分極という概念を理解する。[7.1, 7.2, 7.3, 7.4] 2. 誘電体と静電場(2) 内容:分極がつくる電場を計算できるようになる。誘電体中の電束密度、誘電体境界面での電束密度と電場の接続条件を学ぶ。強誘電体を理解する。[7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9] 3. 電流の周りの磁場(1) 内容:電流の周りの磁場に関する実験事実を学ぶ。ベクトル積、ローレンツ力について理解する。[8.1, 8.2, 8.3],ベクトル積は参考書(2) 第1章 4. 電流の周りの磁場(2) 内容:ビオサバールの法則を理解し、これを応用できるようになる。アンペールの法則を理解し、これを応用できるようになる。[8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9] 5. 電流の周りの磁場(3) 内容:磁気モーメントの周りの磁場を計算できるようになる。磁束密度に対するマックスウェルの方程式を導出できるようになる。[8.10, 8.11, 8.12] 6. 時間的に変化する場(1) 内容:電磁誘導についての実験事実を学び、マックスウェルの方程式との関係を説明できるようになる。磁束が変化する場合に誘導電流が生じることを定式化できるようになる。[9.1, 9.2, 9.3] 7. 時間的に変化する場(2) 内容:回路が変化する場合にも広義の誘導電流が生じること、および時間変化に対するレンツの法則を理解する。[9.4, 9.5] 8. 時間的に変化する場(3) 内容:相互インダクタンス・自己インダクタンス・変異電流密度について理解する。[9.6, 9.7, 9.8] 9. 過渡現象と交流回路 内容:基本素子を学ぶ。過渡現象を理解する。複素インピーダンスを用いて交流回路の基本的問題が解けるようになる。[10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5](2年生の「電気回路」で扱うので概略のみ。) 10. 物質の磁気的性質(1) 内容:軌物質の磁性の基本的事実、および原子・分子・イオンの(ミクロな)磁気モーメントと物質の(マクロな)磁化の関係を理解する。[11.1, 11.2, 11.3] 11. 物質の磁気的性質(2) 内容:物質中の磁束密度と磁場、および磁化の関係、常磁性体、反磁性体、強磁性体、物質境界での接続条件について理解する。[11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9] 12. 電場・磁場のエネルギー 内容:静電場・静磁場がエネルギーを持つことを理解し、これを導出できるようになる。[12.1, 12.2, 12.3](時間の都合上概略のみ。) 13.マックスウェルの方程式の微分形(1) 内容:ベクトル場の発散と回転を学び、ガウスの定理とストークスの定理を理解する。[A.1, A.2, A.3, A.4, A.5],参考書(1) 第5章 14. マックスウェルの方程式の微分形(2) 内容:微分形のマックスウェルの方程式をガウスの定理・ストークスの定理から導出できるようになる。[A.6, A.7, A.8],参考書(1) 第5章 15. 講義内容に関する到達度の確認と解説 内容:講義内容の到達度の確認と、その解説を行う。 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

