シラバス情報
|
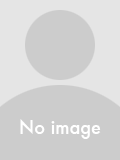
教員名 : 橋本 永手
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
コンクリート工学実験 (1組)
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Experiments on Concrete Engineering (1組)
授業コード Class code
9976220
科目番号 Course number
76CESMM203
教員名
加藤 佳孝、平間 昭信、西村 和朗、橋本 永手
Instructor
Nagate HASHIMOTO, Yoshitaka KATO, Akinobu HIRAMA and Kazuaki NISHIMURA
開講年度学期
2024年度後期
Year/Semester
2024 Second Semester
曜日時限
火曜3限、火曜4限
Class hours
Tuesday 3rd and 4th period
開講学科・専攻 Department
創域理工学部 社会基盤工学科
Department of Civil Engineering, Faculty of Science and Technology 単位数 Course credit
1.0単位
授業の方法 Teaching method
実験
Experiment 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
⑤ [対面]ブレンド型授業/ [On-site] Blended format (must include 50%-or-more classes held on-site)
概要 Description
本授業では,班で協力しながら,コンクリート工学で習得した基礎知識(コンクリートの配合設計,コンクリートの製造)を,実験および動画を通して理解を深めるとともに,レポート作成,プレゼンテーション,ディスカッションを通じて,コンクリート工学の理論に基づいた思考のプロセスをわかりやすく説明し議論する.
目的 Objectives
設計で定められたコンクリートの特性値を実現するためには,材料,フレッシュコンクリートの性状などの基礎知識を踏まえた上で,適切な材料を選定し,配合設計する必要がある.そこで,実験やデータ分析等からこれらの知識を学ぶとともに,与えられた課題に対して考察し,またその結果を相手にわかりやすく伝え,建設的な議論ができる力の基礎を習得することを目的とする.また,設計では倫理観も重要であることから,これに関する技術者倫理についても考える.
到達目標 Outcomes
目標 (F)
1. 配合条件がコンクリートのフレッシュ性状に与える影響について説明できる. 2. フレッシュコンクリートの品質評価手法について考察することができる. 3. 自分自身またはチームで協力して実験の結果を整理し,考察することができる. 4. 与えられた情報に対する分析・考察を論理的に構築することができる. 目標 (G) 1. 文章をわかりやすく構成し,論理的に記述することができる. 2. 自らの考えを他者にわかりやすく説明できる. 3. 他者からの質問に,適切に答えることができる. ※社会基盤工学科が定める学習・教育目標との関連 上記【到達目標】は,下記の主として関連する学習・教育目標に基づいている. 主として関連する学習・教育目標: 目標 (F) 自分自身で,またはチームで協力しながら,土木工学に関する課題を見出し,与条件の下でそれを解決するための計画を立て,試行・検討・実行できるようになる. 目標 (G) 分かりやすく論理的に記述する力,プレゼンテーション力,建設的な議論ができる力を身につける. 他の関連する学習・教育目標: 目標 (B) 土木工学のすべての主要専門分野(構造・材料,地盤,水理,環境・情報,計画)の基礎知識を習得するとともに,応用できるようになる. 目標 (D) 土木技術が自然・社会に及ぼす影響・効果を理解し,その社会的役割と責任を認識し,技術者倫理に基づいて判断できるようになる. 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
コンクリート工学を履修していることが望ましい.
教科書,テキストは必ず持参すること. その他の詳細や注意点は,1回目の授業で説明する. 正当な理由のある欠席の判断については,学科のルールに従う.学科の掲示板を参照すること. 実験器材等の関係上,全ての学生が同時に同じ実験をすることはできない.そのため,授業内容の実施順は班によって異なる. アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test/ディベート・ディスカッション Debate/Discussion/グループワーク Group work/プレゼンテーション Presentation/PBL (課題解決型学習) Problem-based learning/実験 Experiments/実習 Practical learning
-
準備学習・復習 Preparation and review
準備学習:各回の授業内容について教材,教科書の内容について確認しておくこと.授業によっては,小テストを行う場合があり,適切に答えられるように準備学習をすること.
復習:授業内容を復習し,小テスト,レポートおよびプレゼンテーション資料作成に取り組むこと.質問機会も積極的に活用すること. 成績評価方法 Performance grading policy
・課題毎のレポートと小テストおよびプレゼンテーションの合計点で評価する.成績評価の割合は次の通り.
レポート50%+小テスト20%+プレゼンテーション30%=100% ・レポートは,提出期限より遅れて提出した場合,その回のレポート点をゼロ点とする. ・実験項目の際に正当な理由なく欠席した場合は,該当授業の成績は評価しない.また正当な理由のある欠席の場合は,必要に応じて補講を実施し,通常とは異なるレポートを課す等の対応をする予定であるが,詳細については,欠席の証明書を提出する際に教員から指示する.その他の詳細については,1回目の授業で説明する. フィードバックの方法 ・座学は,授業マテリアルの視聴や実験結果を考察し,レポートを作成する内容を1回,レポートについて口頭で説明をし,スタッフとディスカッションをする内容を1回として,フィードバックを行う. ・実験,ディスカッション,プレゼンは,授業内でスタッフとディスカッションを行い,フィードバックを行う.<!--[endif]--> 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
LETUSにアップロードするテキスト.
鉄筋コンクリートの材料と施工,鹿島出版,加藤佳孝,他. 理工系の基礎 土木工学,丸善出版 授業計画 Class plan
1 ガイダンス/製造全般
この授業で対象とする内容を理解する. 技術者倫理について理解する. ★小テストを実施(授業内で説明したことに関する問題) 2 特殊コンクリート 特殊環境でのコンクリートや材料の概要を知り,様々な環境の適用事例を理解する. ★小テストを実施 3 文献調査の練習 材料分野の最新の研究動向の調査方法を学び,一例を調べまとめる. ★レポートを実施 4 研究事例 コンクリート工学に関わる研究事例を聴講し,課題に対する解決方法の例について理解する. 5 実験:粉体・骨材 水セメント比や減水剤の有無,F.M.がフレッシュ特性に与える影響を考察できるようになる. ★小テストを実施 ★レポートを実施 6 実験:フレッシュコンクリート コンクリートの製造に使用する骨材を準備する. 骨材の表面水率から,現場配合を求めることができるようになる. コンクリートを実際に製造するとともに,スランプ試験,空気量試験をできるようになる. 目視・触感評価を実施し,配合毎の違いを体感する. ★小テストを実施 ★レポートを実施 7 課題提示(個人考察) フレッシュコンクリートに求められる品質について理解する. フレッシュコンクリートの性状をモルタルの性状評価から予測する方法について教員,TAとディスカッションし,個人でレポートにまとめて提出する. ★レポートを実施 8 グループ議論 14, 15回目のプレゼンに向けて,7回目課題提示で与えられた課題について,グループディスカッションする.追加の実験が必要であれば,その計画を作成する. 9 検証実施 8回目の授業で計画した実験を実施する 10 考察 9回目の授業で実施した結果を議論し,考察する. 11 改善案検討 10回目の授業で実施した議論の結果をまとめ,改善案を提案する.追加の実験が必要であれば,その計画を作成する. 12 課題議論 11回目の授業で計画した実験を実施し,その結果を受けて,提案する手法についてまとめる. 13 プレゼン資料作成 プレゼン資料を作成する. 14 プレゼン(1) 7回目課題提示で与えられた課題に関する各グループの考察について論理立てて説明し,教員・TAからの質問に適切に答えることができるようになる. 15 プレゼン(2) 同上 なお,授業の順番は上記の通りでは無いが,1回目の授業で説明する. 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
橋本:国内研究機関の研究員(建設材料系)の勤務実績を活かし,建設材料について講義する.
加藤:国内研究機関の研究員(建設マネジメント系)の勤務実績を活かし,建設プロジェクトにおけるコンクリート工学の位置づけについて講義する. 平間:建設会社の研究員の勤務実績を活かし,建設工事におけるコンクリート工学の位置づけについて講義する. 西村:国内企業(材料系)の勤務実績を活かし,建設材料について講義する. 教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
特に無し
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

