シラバス情報
|
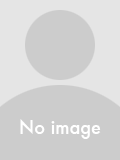
教員名 : 中尾 元紀
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
日本国憲法
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Constitution of Japan
授業コード Class code
9960340
科目番号 Course number
L2HSSSCn01
教員名
中尾 元紀
Instructor
Genki NAKAO
開講年度学期
2024年度前期
Year/Semester
2024/ First semester
曜日時限
水曜1限
Class hours
Wednesday, 1
開講学科・専攻 Department
創域理工学部(一般教養科目)
A course of liberal arts, the Faculty of Science and Technology 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class
概要 Description
国家は、私たちが社会生活を送るうえで欠くことのできない存在であり、それを形作っているものが憲法である。
本講義は、日本国憲法の二本柱である統治機構・基本的人権に関する基礎知識を説明するともに、現実の社会問題に対して憲法的規制がどのように及ぶかを、主要な学説・判例に照らして検討することを内容とする。 特に人権保障システムを通じて、「国家が個人の生活にどこまで介入でき、どのラインを越えてはならないか」という国家と個人との「距離感」を、憲法がどのようなものとして構想しているかについて解説することを試みる。 なお、本講義の受講生は法学を専攻していない学生がほとんどであると思われる。そこで本講義の序盤では、法学的な思考法(法の定義や解釈の必要性など)について概説し、もって憲法の内容・特殊性を理解するための基礎を構築する。そのため、まったくの初学者であっても安心して受講されたい。 目的 Objectives
現代社会の諸問題について正義や公正、公共性といった観点から考察する力を養い、もって各人の社会に対する認識を深めること。
特に、(1)人権問題においては、常識や素朴な正義感に基づく「裸の価値判断」が、他者の人生を不可逆的に破壊してしまうことや、社会や当事者に重すぎる負担を課してしまう場合があることを理解し、(2)このような事態を避けるために、当事者の主張やその背景を十分に検討し、法的な根拠を揃えた上で、緻密に論理を組み立てる能力(リーガル・マインド)を養うこと。 到達目標 Outcomes
前記の「目的」を達成するために、以下3点を到達目標とする。
(1)法の機能・役割について理解すること。 (2)憲法の概要(統治機構および基本的人権)を理解すること。 (3)社会や身の回りの具体的な問題について、憲法的な視点を踏まえつつ自らの見解を説得的に展開できること。 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
第一回の講義が終了した時点で、履修希望者が教室の収容人数を超えたと判断した場合には、履修者の抽選を行います。初回講義に登録されている履修者の中から抽選を行いますので、履修を希望する場合は、必ず第一回の講義終了時刻までに履修登録を行って下さい。初回講義での抽選の結果は、第二回講義の前までに、抽選対象となった者にのみ、CLASSを通じて連絡します。なお、抽選を行う場合、他学科履修は認められません。
【第一回の講義後に抽選を行う場合】 ●抽選で当選した学生 当選した場合、どのような事情があっても後から履修登録を取り消すことはできません。 熟慮した上で履修登録するように気をつけてください。 ●抽選で落選した学生 落選した場合、単位認定はできません。必ず自分自身で、履修登録を削除してください。履修登録を削除した後は、他の講義に履修登録をやり直すことができます。ただし、初回で履修抽選の行われた講義には履修登録ができませんので、2回目の授業に必ず出席し、担当の講師に履修可能であるか確認するようにしてください。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test/ディベート・ディスカッション Debate/Discussion/グループワーク Group work
講義形式を基本とするが、授業内でグループディスカッションを実施する場合がある。
準備学習・復習 Preparation and review
授業外の事前・事後学習として次のような作業を求める。詳細は各回で指示する。
(1)教科書の指定箇所や配布資料の熟読。 (2)授業後、質問・コメント等をLETUSから提出する。その際、内容について指示がある場合は、それに従うこと。たとえば、新聞記事やウェブサイトで授業に関連する問題を調べた上で、コメントをするよう求めることがある。 成績評価方法 Performance grading policy
平常点(授業後課題やコメントの提出状況、グループディスカッションへの参加度)と、学期末の試験から評価する。
成績評価における割合は、平常点を20%、学期末試験を80%とする。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
Y
書誌情報 Bibliographic information
中村睦男・佐々木雅寿・寺島壽一 編著『はじめての憲法学(第4版)』(三省堂、2021年)/978-4385321936
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
下記の文献は購入の必要はありません。活用法については授業内で説明します。
早川吉尚『法学入門』(有斐閣、2016年)/978-4-641-15032-4 安西文雄、巻美矢紀、宍戸常寿『憲法学読本(第3版)』(有斐閣、2018年)/978-4-641-22761-3 小山剛『「憲法上の権利」の作法(第3版)』(尚学社、2016年)/978-4860311285 授業計画 Class plan
【第1回 ガイダンスと日本国憲法の概要】
講義の形式や成績評価の方法等の説明を行う。その後、日本国憲法の全体像を簡潔に示し、憲法を学ぶことにどのような意義があるのか、なぜ統治機構・基本的人権が憲法の二本柱であるかについて解説する。 【第2回 法学入門】 法の定義・機能について概要を示し、今後の学習の基礎を作る。特に、(憲)法を具体的事実に適用する際に避けられない、法の解釈という営為の意義と必要性について理解し、実際に体験してもらう。 【第3回 基本的人権総論】 人権という観念がいかにして誕生し、発展してきたかを学ぶ。たとえば、「第一世代の人権」等と称される人権の概念的区分を紹介し、憲法における人権(法的なシステムとしての人権)がいかにして成立したかを理解する。 【第4回 幸福追求権① 総論とプライバシー権、自己決定権】 幸福追求権の憲法における位置づけを学ぶ。特に当該権利から派生する自己決定権について、修徳高校パーマ禁止校則事件や昭和女子大事件を素材として検討する。 【第5回 幸福追求権② 自己決定権の展開】 医療等の専門家としての見識・良心に基づいた行為が、個人の自己決定権を侵害しうるのはどのような場合か。エホバの証人輸血拒否訴訟を紹介し、職業倫理と自己決定権との緊張関係について検討する。 【第6回 法の下の平等① 平等概念と差別の禁止】 法的に禁止されるべき差別とはどのようなものか。尊属殺重罰規定違憲訴訟や非嫡出子法定相続分差別訴訟の紹介を通じて、平等概念の基本的な考え方を学習する。 【第7回 法の下の平等② 差別の禁止とアファーマティブ・アクション】 人種差別の問題を取り上げ、小樽入浴拒否訴訟の解説を通じて差別問題の憲法的規制のあり方(私人間効力論を含む)を検討する。さらに、アファーマティブ・アクションの意義について、女性差別を題材に学習する。 【第8回 身体的自由権】 日本国憲法では、身体の完全性(物理的暴力の禁止)や刑事手続に関する規定は比較的充実しているとされる。これら身体的自由権の概要を示すとともに、死刑問題を取り上げ、死刑そのものの是非と死刑囚の処遇という2つの観点から検討する。 【第9回 精神的自由権① 思想・良心の自由、信教の自由】 他者の考え方や信仰を尊重して無暗に口出ししない、という学生は多いであろうが、精神的自由権の保障内容はそれに尽きるものではない。特に教育権場における信教の自由の行使とその限界について、神戸高専剣道拒否事件等を題材に検討する。 【第10回 精神的自由権② 表現の自由】 表現の自由は、最も重要な権利の1つとして位置付けられているが、それはなぜか。表現の自由が社会においてどのような機能を果たしているかや、表現の自由に対する制約はいかなる場合に許容されるかを学ぶ。 【第11回 在留外国人と憲法】 日本国内に滞在・居住しているのは日本人(=日本国籍者)だけではない。日本の出入国管理法制の現状について概観した後、国際人権法的視点を交えながら、外国人の出入国の権利や家族生活の保護に関する法規範について検討する。 【第12回 統治機構① 統治の基本原理】 権力分立・国民主権・法の支配といった中核的概念について、それぞれの有機的連関や歴史性をワイマール憲法の紹介等を通じて解説し、これらに関する現代的理解を示す。 【第13回 統治機構② 国会・内閣】 国会議員の「代表」性に関する論争や、議院内閣制における議会と政府の関係について学ぶ。 【第14回 統治機構③ 裁判所】 裁判所の地位と機能について、大陸法と英米法の相違、司法権の独立といった諸点から説明する。さらに、憲法訴訟(違憲審査制)のあり方について検討する。 【第15回 講義の総括】 到達目標の達成度を確認した上で、これまでの内容について総括する。 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
本科目は、教育職員免許状取得に必要な文部科学省令で定める科目「日本国憲法」に該当します。 実際の授業の進行は、シラバスの内容と若干前後する場合があります。その際には、授業内でアナウンスします。 授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
-
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
-
|

