シラバス情報
|
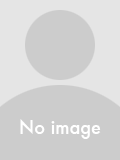
教員名 : 愼 蒼健
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
大学論
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
大学論
授業コード Class code
993K411
科目番号 Course number
教員名
本田 宏隆、村上 学、神野 潔、伊吹 友秀、西倉 実季、井上 敬介、愼 蒼健
Instructor
Chang-Geon SHIN, Kiyoshi JINNO, Miki NISHIKURA, Hirotaka HONDA, Manabu MURAKAMI, Tomohide IBUKI, Keisuke INOUE
開講年度学期
2024年度前期
Year/Semester
2024 First Semester
曜日時限
火曜5限
Class hours
Tuesday, 5th
開講学科・専攻 Department
薬学部(一般教養科目)
Faculty of Pharmaceutical Sciences 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
④ [遠隔]ハイフレックス型授業(キャンパス間配信)/ [Remote] Hybrid-Flexible format (with inter-campus streaming)
概要 Description
本学教養教育の目標の一つである、「ノブレスオブリージュの精神のもと、高い志をもって世界の発展・持続に率先して貢献する能力」の涵養を目指す。葛飾では2023年前期のゼミ科目「教養演習」において、東京理科大学の歴史を含めた大学論をテーマとした。2024年度からは授業形式をゼミから講義へと変え、4キャンパス横断授業として、科目名も「大学論」に変更し、専門家によるオムニバス形式で開講する。本学教員の他、ゲスト講師を招聘する回もある。
講義では、「東京物理学講習所」を出自とする本学創設時の状況とその後の歴史的展開を、より広いコンテクストの中に置き(大学史、近現代日本高等教育史、科学教育史など)、深みのある自校教育を行う。同時に、「大学とは何か」、「近現代日本の大学にはどのような問題が存在するのか」、「これからの大学はどこへ向かうのか」を問う。学生は、複数の教員と共に考える経験を通じ、「大学」の一員であることの自覚や自分の立ち位置、そしてこれからの学びの可能性への気づきを獲得する。 <担当教員一覧> 愼蒼健(科学史・科学論) 神野潔(法学・日本法制史) 西倉実季(社会学・ジェンダー研究) 本田宏隆(ライフサイエンス・化学) 村上学(哲学・倫理学) 伊吹友秀(倫理学・生命倫理学) 井上敬介(歴史学・近代日本史) 目的 Objectives
この授業の目的は、研究者あるいは責任ある社会人として必要になると思われるスキルや知識を身につけ、ゆたかな人間性や想像力、そして多面的な視点で問題を考える力を養うことにある。また、話題を大学に特化することにより、受講生は「大学」という普遍的な学びの場の一員であることの自覚を高め、現実の学びの場である東京理科大学への理解を深めていく。
到達目標 Outcomes
具体的には次の力の向上を目標する。
(1)自明性を疑い、疑問を明らかにしていく「疑問力」 (2)物事を徹底的に吟味し、判断を下す「批判力」 (3)筋道を立てて考えることができる「論理的思考力」 (4)「プレゼンテーション能力(表現力)」 (5)ディスカッションができる「コミュニケーション能力」 (6)自分とは違う考えを受け入れる「寛容さ」と、「他者の立場に立って考えることができる想像力」 (7)レポートを書く力 さらに、 (8)現在の自分を時間的・空間的そして社会的に位置付け、説明できる「自己認識力」 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
4キャンパス横断でディスカッション可能な空間を創出するため、各キャンパスの受講生は40名程度に制限することがある。
アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/ディベート・ディスカッション Debate/Discussion/グループワーク Group work/-
-
準備学習・復習 Preparation and review
<準備(予習)>
LETUSに提示される授業用資料に目を通し、キーワードや課題について検討しておく。さらに、質問や議論のポイントを考えることによって「臨戦態勢」を整える。 <復習> 要点をノートにまとめ、自分の言葉で問題となった事柄について説明し、さらなる疑問(問題)を提示できるようにする。教員が提示するFurther Reading用書籍やwebサイトを通じて知識や思考を拡張する。 <付記> 詳細はLETUS上の各回案内、または授業中に指示する。 成績評価方法 Performance grading policy
授業内の課題や小テスト: 80%
最終回(第15回)で出される課題(小レポート) : 20% 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
天野郁夫『大学の誕生』上・下、中公新書、2009年。
天野郁夫『帝国大学—近代日本のエリート育成装置』中公新書、2017年。 寺崎昌男『日本近代大学史』東京大学出版会、2020年。 吉田文『大学と教養教育:戦後日本における模索』岩波書店、2013年。 広田照幸他編『シリーズ大学5 教育する大学:何が求められているのか』岩波書店、2013年。 C.H.ハスキンズ『大学の起源』青木靖三・三浦常司訳、八坂書房、2009年。 吉見俊哉『大学とは何か』岩波新書、2011年。 苅谷剛彦・吉見俊哉『大学はもう死んでいる?:トップユニバーシティからの問題提起』集英社新書、2020年。 授業計画 Class plan
第1回(4月16日) ガイダンス(オリエンテーション)
内容:授業の狙い、進め方などを確認する。 第2回(4月23日) 大学生の生態と文化 内容:教養主義、弊衣破帽、大学進学率の上昇、対抗文化、1980年代—1990年代の大学生 第3回(4月30日) 東京理科大学の歴史:明治、大正、昭和前期 内容:東大物理学科(仏語)卒業生の創設者たち、物理学講習所から物理学校へ、物理学校の特徴 第4回(5月7日) 古代ギリシア・中世の高等教育 内容:パイデイアとソフィア、アカデメイア(プラトン)、イソクラテス、三学四科、神学とスコラ 第5回(5月14日) 大学の誕生、衰退、再生 内容:12世紀ルネサンス、14世紀以降の大学衰退、フランス革命と教育改革、ドイツ近代大学、専門と教養の「対決」 第6回(5月21日) 近代大学の登場(日本) 内容:帝国大学令、専門学校令、大学令、カリキュラムと講座制、帝大教授と学生たちの生活 第7回(5月28日) 戦後新制大学の登場(日本) 内容:帝大・旧制高校の解体、新制大学の登場、アメリカ式一般教育の導入、東京理科大学の設立 第8回(6月4日) 大学とジェンダー 内容:男女平等教育、女子の特性教育、「女子大生亡国論」、 進学率と専門分野のジェンダー格差 第9回(6月11日) 大学・裁判と自治 内容:東大ポポロ事件、富山大学事件、昭和女子大事件、学問の自由、大学の自治、部分社会 第10回(6月18日) 大学と社会の緊張 内容:1968年、学生運動、70年代・80年代大学の風景、京大「タテカン」・「寮」問題 第11回(6月25日) 大学と地域の親和性 内容:「キャンパス」と都市、大学街・学生街、北海道・長万部キャンパス、地域連携、「学生さん」 第12回(7月2日) 大学からの道 内容:大学院(修士、博士)、就職、インターンシップ、自己PR、エントリーシート、自己分析 第13回(7月9日) 大学とスポーツ・体育会 内容:大学スポーツの歴史、スポーツと体育、日大アメフト問題 第14回(7月16日) 理科大人を超えて 内容:卒業・中退後のノーマル・モデルを超えて、 第15回(7月23日) 大学の存在理由と未来(まとめ) 内容:大学の価値、大学はどこへ向かっていくのか SBOsコード(薬学部薬学科のみ 2023年度以前カリキュラム適用者対象)
学修事項(薬学部薬学科のみ 2024年度以降カリキュラム適用者対象)
授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
-
教育用ソフトウェア Educational software
-
-
備考 Remarks
-
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
N
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
N
|

