シラバス情報
|
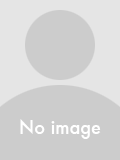
教員名 : 佐藤 喜一郎
|
科目授業名称(和文) Name of the subject/class (in Japanese)
情報科学概論1
科目授業名称(英文) Name of the subject/class (in English)
Information Science 1
授業コード Class code
9912B5C
科目番号 Course number
12MAISS101
教員名
小林 翔悟、佐藤 喜一郎
Instructor
Ki-ichiro Sato
Shogo Kobayashi 開講年度学期
2024年度前期
Year/Semester
2024 1st Semester
曜日時限
水曜5限
Class hours
Wednesday 5th Period
開講学科・専攻 Department
理学部第一部 物理学科
Department of Physics, Faculty of Science Division Ⅰ 単位数 Course credit
2.0単位
授業の方法 Teaching method
講義
Lecture 外国語のみの科目(使用言語) Course in only foreign languages (languages)
-
授業の主な実施形態 Main class format
⑦ [遠隔]オンライン授業(同期)/ [Remote]Online (synchronized remote)
概要 Description
高校で必修の「社会と情報」や「情報の科学」などの情報系科目で習得した基礎的な情報/コンピューター活用能力を前提に、理工系大学の大学生活および将来の研究・仕事に不可欠な、情報/コンピューター利用スキルを身につける。 インターネットにおける情報の取り扱いに関する一般知識の講義を行うとともに、実際にBYOD機での活用演習を行う。さらに、様々な媒体での情報発信の技術を演習を中心に習得し、プレゼンテーションについてもカバーする。さらに、コンピュータにおける数式処理・可視化を専用のソフトウェアを用いて実践する。 目的 Objectives
学科のカリキュラム・ポリシーに記載の演習を行う情報系科目である。また、学科のルーブリックの3、問題発見、解決能力、4プレゼンテーション能力に対応する科目である。
コンピュータは計算をするための道具であるとともに情報を処理するための道具であるという視点から、講義と演習を行う。演習は、各自のコンピュータを用いて行う。コンピュータの基本操作に関する基本知識を習得する。また、Mathematicaを使って数式処理および数値計算ができるようにする。 到達目標 Outcomes
・BYOD機を含むコンピュータを活用するためのOSの働きを理解できる
・情報の蓄積、情報交換に必要なファイル形式と符号化の方法などを理解できる ・インターネットメールの特徴を理解したうえで、社会の一員としてふさわしい利用ができるようになる ・インターネットの情報検索について、一次情報源と二次情報源の区別、ソーシアルメディアの特性などを説明できる ・デジタル署名、暗号化技術、生成系AIやなどに関する最新技術について重要点を説明できる ・インターネットでの情報の利用・発信について、著作権や個人情報保護、情報倫理などの観点で正しい使用が行えるようになる ・インターネット社会における様々な危険から身を守るすべを身に着ける ・実験レポートの作成に代表される理工系での図表を含む文書作成において、Word, Excelなどを活用法して求められる体裁にあわせて文書を作成できる ・将来の卒業研究発表や学会発表を念頭に置いて、理工系での実験・研究成果の口頭発表やポスター発表のための資料作成において、PowerPointを活用し作成する技術を身に着けるとともに、プレゼンテーション時にもPowerPointを活用する技術を身に着ける。 ・コンピュータを利用して問題解決ができるようになること。特に理工系において重要な数式の取り扱いに関して、数式の記述のままでの様々な演算や方程式の解法などがMathematicaでできるようになる ・さらにMathematicaによる数式の可視化を、単なる一変数のグラフにとどまらず多変数関数の分析に使用できるようになる 卒業認定・学位授与の方針との関係(学部科目のみ)
リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます(学部対象)。
履修登録の際に参照ください。 You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments). https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/ 履修上の注意 Course notes prerequisites
・授業の前提となるBYOD機の推奨については「(重要:2024年度入学予定の皆様)「ノートパソコンの必携(BYOD)」について」を参照し、授業に支障のないように準備をすること。
・講義の概要、毎回の授業内容、音声付き電子教材、各種教材、課題の内容はLETUSの内容を閲覧すること。 ・授業計画は予定であり、授業の進度によって変更する可能性があるので、LETUSの内容を 参照すること。 ・Microsoft365 メール、Microsoft Office、Mathematicaを各自のパソコンにインストールすること。 インストール方法は、「東京理科大学 ITサービスのご案内」を参照し、インストールに関してわからない場合は、「情報システム課ITサービスデスク」にメール等で相談すること。 アクティブ・ラーニング科目 Teaching type(Active Learning)
課題に対する作文 Essay/小テストの実施 Quiz type test/プレゼンテーション Presentation/実習 Practical learning
-
準備学習・復習 Preparation and review
大学の授業は、時間割上の授業時間に加え、その2倍にあたる授業時間外の学習(予習・復習)をもって構成される。
本授業は2単位なので、以下のように、予習・準備学習と復習であわせて4時間の学習を行う必要がある。 【準備学習】 毎回の授業内容は、LETUS(コース: 情報科学概論1 (9912B5C) (tus.ac.jp) )に掲載されている。電子教材や動画を使って、各自の理解度によって、予習・復習することができる。また、各種ソフトウェアの使い方などもLETUSに、掲載されているので活用できる。 【復習】 各授業終了後に、板書や講義録画などで復習をおこないつつ、練習問題と確認問題を行い、最終的な課題提出までを行う。 成績評価方法 Performance grading policy
インタネットのリテラシについては、確認問題とINFOSSの受講をもって判断する。(20%)
大きな課題は3つ出題される。課題1〜課題3は、期限までにLETUSにアップロードすること。 期限を過ぎた場合は提出できない。 課題1 30% Excel 課題2 20% プレゼンテーション 課題3 30% Mathematicaとその出力応用 で評価を行う。 学修成果の評価 Evaluation of academic achievement
・S:到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A:到達目標を十分に達成している ・B:到達目標を達成している ・C:到達目標を最低限達成している ・D:到達目標を達成していない ・-:学修成果の評価を判断する要件を欠格している ・S:Achieved outcomes, excellent result ・A:Achieved outcomes, good result ・B:Achieved outcomes ・C:Minimally achieved outcomes ・D:Did not achieve outcomes ・-:Failed to meet even the minimal requirements for evaluation 教科書 Textbooks/Readings
教科書の使用有無(有=Y , 無=N) Textbook used(Y for yes, N for no)
N
書誌情報 Bibliographic information
-
MyKiTSのURL(教科書販売サイト) URL for MyKiTS(textbook sales site)
教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store). https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/ 参考書・その他資料 Reference and other materials
個々の授業に必要な資料は、LETUSで提供する。
情報科学全般の話題については、以下の参考書を挙げておく。 田中琢真著、「情報科学概論」、学術図書出版社、2019年発行、ISBN 978-4-7806-0702-4、定価2400円 授業計画 Class plan
第1回:ガイダンス
・授業の進め方について ・コンピュータ、とりわけ、BYOD機の構成と機能 ・OSの果たす役割 ・アカウントとユーザ認証、ユーの権限について ・インターネットの仕組みとネットワークサービスの概略 ・本学における情報サービス(CLASS, LETUS)とBox、Microsoft 365、ZOOMの利用 ・アカウントとセキュリティ 【予習課題】 Microsoft Officeを各自のPCにインストールすること。 各自のPCへのインストール方法は、「東京理科大学 ITサービスのご案内」を参照し、インストールに関する質問は、「情報システム課ITサービスデスク」に相談すること。 【確認問題】ソフトウェアの起動ができた証拠となるファイルを提出する 第2回:情報倫理および電子メールの利用 「インターネット事件事例集」を用いて情報倫理について解説する。 コンピュータを利用するための倫理(マナー)、電子メールの使い方の注意点などについて理解する。 演習:電子メールの練習を行う。 【予習課題】インターネット事件事例集を読んでおく。 【確認問題】指定された電子メールアドレスに送受信し、情報が取得できた証拠となるファイルを提出する 【課題0】INFOSSの受講をもって到達度を確認する 第3回:表計算ソフトによる情報の集計方法と操作 ・ 表計算ソフトの歴史、表計算の概念と表計算ソフトを用いた情報集計に関して理解する。 ・Excelを使用して、ワークシート、セルとセル範囲、値と式、セルの複写などの表計算ソフトの基本事項を学ぶ。 ・表計算の本来の集計、データベースとしての利用、数値計算への応用の基盤を作る。 ・保存ファイル形式として、csvと表計算ソフトの独自ファイル形式(Excelなら)などがあることを学ぶ。 第4回:表計算ソフトの応用1 ・合計や平均などの関数を利用し、表計算の本来の集計、データベースとしての利用、数値計算への応用を具体的に考える。 ・Excelによるデータの可視化の方法を学び、実験データの解析の足掛かりを得る。 第5回:表計算ソフトの応用2 実験データ解析とデータの可視化についてExcelを利用して具体的に行う(演習) 第6回:表計算ソフトの応用3 実験データ解析とデータの可視化についてExcelを利用して具体的に行う(演習) 【課題1】ExcelファイルとPDFの提出を行う 第7回:プレゼンテーションの基礎 プレゼンテーションの基本的な考え方を学ぶ。 オーラルプレゼンテーションとポスタープレゼンテーションについて、それぞの基本的な考え方を学ぶ。 PowerPointの使用を前提に、発表形態に応じたスライドのデザインやプレゼンテーションの基本的な考え方を学習し、プレゼンテーションができるようになる。 ・発表形態別の資料の準備 ・デザイン、会場の雰囲気、(オーラルの場合の)話し方、オブジェクトの操作など ・ 第8回:プレゼンテーションへの活用1 プレゼンテーションソフトを使った発表技法を学習し、様々な表現ができるようになる。 ・図による表現、グループ化、アニメーションなど 【課題】中間段階の資料提出 第9回:プレゼンテーションへの活用2 プレゼンテーションソフトを使った発表技法を学習し、様々な表現ができるようになる。 ・スライドショー実演による相互評価 ・SmartArt、ナレーションの録画など付加機能、時間管理について 【課題2】パワーポイントスライドファイルとPDFの提出を行う 第10回:数式処理1 数式処理の基礎 Mathematicaを利用して、数式処理ができるようになる。 四則演算、有理式、微分、リストとベクトル・行列演算 演習:基本操作、素数、因数分解、微分積分、グラフの作成 第11回:数式処理2 Mathematicaにおける、級数、微分方程式の解法、特殊関数の取り扱いを学ぶ。 第12回:数式処理3 数式の可視化、次元解析と処理用の数式の準備について学び、Mathematicaによる数式の可視化関数を使用して可視化を行う。 第13回:数式処理4 Matehaticaによる、数式の可視化、媒介変数表示、多変数関数などよく使われる数式への応用を学ぶ。 【課題3-1】Mathematicaでの処理の結果を提出する 第14回:数式を含む文章作成1 LaTeXの利用 ・Word・PowerPointの数式エディタ・Moodleのatto数式エディタと文書組版ソフトLaTeX ・LETUSによる数式表現の演習 ・数式の言語処理-TeX. LaTeX系の記述 第15回:数式を含む文章作成2 LaTeXの実際 ・LaTeXでの数式の記述を演習習得する ・Mathematicaによる数式の出力と合体させる ・数式・グラフをプレゼンテーション資料の作成への応用 【課題3-2】Mathematicaでの処理の結果と、それを用いた資料を提出する 授業担当者の実務経験 Work experience of the instructor of the class
教育用ソフトウェア Educational software
Mathematica
Microsoft365 メール、Microsoft Office、Meryエディタ、Mathematicaの各自のPCへのインストール方法は、「東京理科大学 ITサービスのご案内」を参照し、インストールに関する質問は、「情報システム課ITサービスデスク」に相談すること。
備考 Remarks
授業でのBYOD PCの利用有無 Whether or not students may use BYOD PCs in class
Y
授業での仮想PCの利用有無 Whether or not students may use a virtual PC in class
Y
|

